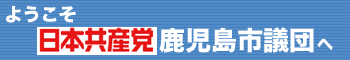P.133 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
初めに、8月の台風10号で被災された方々に党市議団を代表し、心よりお見舞いを申し上げます。本市でも強風被害が長時間に及んだことから市民生活に大きな影響を受けました。県内はじめ九州各地でも強風による建物の崩壊など被害が多数出た地域もあったことから、被災者の一刻も早い生活再建を祈るものです。
質問に入ります。
生産緑地制度の導入に向けての取組状況を伺います。
全国で深刻な米不足が発生し、この鹿児島市にもその影響が広がっています。政府は、そのうち新米が出る、米不足は解消する、慌てることはないなどとして対策は全く行われず、私の地元スーパーでも品切れが相次いでいました。米が置いてあるスーパーでも購入制限がある上、価格も2割から4割も高くなっていて、市民が安心できる状況とは到底言えない状況です。米だけではありません。今年は酷暑に加え、物価高などで野菜や果物なども軒並み値上がりしています。市民への安定した食料供給について、本市としても真剣に向き合わなければならない時期に来ているのではないでしょうか。
私は、平成29年第3回定例会で本市の食料自給率を伺ったところ、僅か4%だったことからも市街地の農地をこれ以上減らすわけにはいかない、この思いで生産緑地制度の導入を求めてまいりました。この制度は、市街化区域内の農地の固定資産税が宅地並みに課税されていることから、その負担軽減を目的とする制度ですが、農家の負担軽減や都市農業を守るという本市のメッセージにもなることから、以下伺います。
まず、本市がこれから行う予定である農家への意向調査です。
1点目、意向調査の概要。
2点目、対象者と対象者数をお示しください。意向調査の対象となる農家の分布はどのような特徴かお示しください。
3点目、都市農地の保全につながるよう制度の意義を伝え、意向調査に取り組むことへの当局の見解をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.134 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) お答えいたします。
意向調査は、市街化区域内の農地所有者に対し、年齢や後継者の有無のほか、農業継続や農地ごとの制度利用に対する意向を把握するために実施するものでございます。
対象者は、令和5年8月時点の農地台帳を基に抽出した総経営面積が1千平方メートル以上、かつ市街化区域内に一定規模以上の農地を有する農家およそ290名で、対象となる農地は吉野地域に7割、谷山地域に2割が分布しております。
調査に当たっては、調査票に制度の目的や指定要件のほか、30年間の営農の継続を前提としていることや税制面での優遇措置などをお示しすることとしており、制度内容を御理解の上、御回答いただくことで対象者の意向を把握できるものと考えております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.134 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
対象者の分布としては吉野地域が7割を占め、谷山地域に2割分布しているとのことですが、中央地域などの市街地は対象となる農地がほぼないということが分かりました。ただ、今回の対象は1千平米の農地が基準です。生産緑地制度の対象面積は500平米、あるいは条例で300平米まで引き下げることが可能ですので、意向調査の対象となっていない1千平米以下の農地も生産緑地制度の対象であるということは指摘をしておきます。
また、税制面での優遇措置はもちろんのことですが、農家の皆さんにとっては30年の営農の継続という決断は大変大きな挑戦です。だからこそ、対象者の方々に制度の意義を深く理解していただく必要があるのではないでしょうか。そのことを踏まえて意向調査に取り組むよう要望いたします。
次に、産業局に伺います。
中央地区、市街地には対象がほぼなかったということについての課題認識をお示しください。
また、米不足の解消や食料自給率の向上が叫ばれている中での制度導入による効果をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.134 ◎答弁 産業局長(新小田洋子君)
◎産業局長(新小田洋子君) お答えいたします。
市街地につきましては、都市化の進行に伴い、農地の分散化や混住化が進み、農地の減少や小規模化により持続的な農業経営を行うには厳しい生産環境となっているものと考えております。
制度導入による効果としましては、生産緑地の指定により、長期にわたって農地が守られることで安心して農業が継続できるほか、農産物の安定供給や身近なところで農業生産が行われることにより、農業に対する理解が進むことなどが期待されます。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.134 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
固定資産税の負担から農地を手放さざるを得ず、農地面積が縮小していく方がおられます。また、当局が示された混住化で、住宅地にある農地は近所から砂ぼこりがする、臭いがするなどの苦情もあり、農業を継続したくても市民の十分な理解が得られない場合もあると伺っています。市街地で今回の意向調査の対象となる1千平米の農地がほとんど残っていないということが明らかになり、もっと早く手を打つべきだったことは指摘をしておきます。
最後に、市長に伺います。
生産緑地制度の導入は喫緊の課題ではないかと考えますが、市長の見解をお示しください。
以上、御答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.134 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 園山えり議員にお答えいたします。
私は、人と自然が共生する都市環境の構築に向けて、都市内に残る緑を保全するとともに、新たな緑を創出し、緑豊かな環境を次世代に継承していく必要があると考えております。都市農地は農産物を供給する機能のみならず、防災や良好な景観形成など様々な機能を有する身近な緑地であり、都市づくりの観点からこれらを計画的に保全し、緑豊かな潤いのある都市環境の形成を図るため、引き続き、生産緑地制度の導入に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
[園山えり議員 登壇]
P.135 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
市街化区域の農地が防災にも役立つという新しい観点からの評価も含め、市長にお示しいただいたことは評価するものです。生産緑地制度の検討をスピード感を持って進めていくためにも、市長のその思いが農家に伝わるような意向調査を行うよう強く要望し、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
本市による自衛隊への本人同意のない名簿提供について、まず、令和6年度の取組を伺います。
1点目に、除外申請を行った人数をお示しください。
2点目に、当局が自衛隊へ名簿提供した人数をお示しください。
3点目に、今年度は自衛隊はこの名簿をどのように利用されたのか、昨年との比較と併せてお示しください。
以上、御答弁願います。
P.135 ◎答弁 総務局長(遠藤章君)
◎総務局長(遠藤章君) お答えいたします。
6年度の除外申請については、受付期間終了後になされた申請を含め101人となっております。
また、自衛隊に提供した募集対象者情報は、除外申請分を除き5,934人分で、自衛隊によりますと、これまでどおり採用説明会の開催案内に使用したとのことでありますが、今年度は封書ではなく、はがきで郵送したとのことでございます。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.135 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
今年度は最終的に101人が除外申請の手続をしたということでした。昨年は168人でしたが、2年連続して100人を超える除外申請が行われ、全国でも高い申請率が続いていることを市長は重く受け止めていただきたいと思います。また、今年度は自衛隊に対して5,934人分の名簿が提供されたということを確認いたします。昨年は約6千人のうち半数の約3千人の18歳市民に封書が送られたということを確認していましたが、今年度はほぼ全ての約6千人にはがきが送られたということを当局からは伺っています。
そこで、こちらを御覧ください。今年度、18歳の市民に送られてきた自衛隊からのはがきを拡大してまいりました。保護者の方から、「こんなはがきが娘宛てに来た」と情報提供があったものです。このはがきには、平和を、生活を、「守」という字が強調されています。さらにこちらには、「このハガキを持って来てくれたら、もれなく自衛隊グッズプレゼント!!」などと書いてあり、私は大変違和感を覚えました。自衛官には命をかける賭命義務があるということは一切示されていません。
教育長とはさきの第2回定例会において質疑も交わしましたが、その後、私ども党地方議員団は直接文科省に伺ってまいりました。文科省と厚労省が防衛省に対して申し入れた就職活動については、教育的観点から民間事業所と同様に、学校を通じて学校の協力の下に行われるということが適当であり、募集活動について行き過ぎないよう特段の理解と協力を願いたいという申入れについては今でも生きているかと直接伺ったところ、そのとおりだとお認めになりました。しかし、本市では、18歳市民にダイレクトメールが勝手に送りつけられています。文科省などが求めている公正なルールの遵守に照らせば文書での募集は禁止されており、もってのほかだということは改めて指摘しておきたいと思います。
次に、自衛官募集事務重点市町村について伺います。
1点目、自衛官募集事務重点市町村とは何か。
2点目、名簿提供との関連性についての当局の認識をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.136 ◎答弁 総務局長(遠藤章君)
◎総務局長(遠藤章君) お触れの重点市町村とは、自衛隊法に基づき都道府県知事が指定することとなっており、指定された市町村は、自衛官等の募集に関する模範的な広報宣伝活動を行うこととされております。
また、重点市町村と名簿提供との関連性については特にないものと認識しております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.136 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
特に関連性はないという御認識でした。
そこで、今年度、名簿提供をやめた他都市の取組について伺います。
質問の1点目、太宰府市が今年度名簿提供をやめた主な理由をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.136 ◎答弁 総務局長(遠藤章君)
◎総務局長(遠藤章君) 太宰府市によると、名簿提供をやめた主な理由としては、重点市町村の指定期間が5年度末で終了したことや近隣市の対応状況などを踏まえて変更したとのことでございます。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.136 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
太宰府市は募集事務重点市町村から外れたことから名簿提供をやめたということが分かりました。本市は継続して重点市町村となっているようですが、他都市は期間を区切って指定されている一方で、本市は毎年、重点市町村として指定されており理解ができません。私どもは名簿提供についても圧力をかけることはやめるよう防衛省に直接求めてまいりました。その際、この重点市町村については国と県で指定しているという回答でした。重点市町村の指定が解除されたことを理由に名簿提供をやめることの理由に挙げられた市長が出てきたのですから、本市を重点市町村に指定しないよう求めることは可能だと考えます。
そこで、質問の2点目、本市も重点市町村の指定をやめるよう国や県に求めるべきと考えますが、見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.136 ◎答弁 総務局長(遠藤章君)
◎総務局長(遠藤章君) 重点市町村の指定と名簿提供については特に関連性はないものと認識しており、お触れのことについては考えていないところでございます。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.136 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
改めて関連性はないので考えていないということでしたが、実際に太宰府市はそれを理由に名簿提供をやめています。
そこで、最後に、法定受託事務ではないことから、名簿提供を市長の決断によってやめた太宰府市長に対する市長の見解をお示しください。
以上、御答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.136 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 太宰府市の状況は承知しておりますが、本市におきましては、自衛隊法や同法施行令、国の通知などを踏まえ5年度から名簿提供をしているところであり、今後におきましても法令等に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。
[園山えり議員 登壇]
P.136 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
今後も法令等に基づき適切に対応していくとのことですが、明確な法的根拠がないことから太宰府市長は自らの判断で名簿提供をやめる決断ができたというこの経験から学ぶべきだということは指摘をしておきます。憲法13条に基づく個人の尊厳、プライバシー権など、憲法で保障されている権利を侵害する名簿提供は直ちに市長がやめる決断をするよう強く求め、この質問を終わります。
次に、台風10号における本市の対応について伺います。
台風10号の接近により、8月28日正午に本市は警戒レベル3、高齢者等避難、午後3時には警戒レベル4、市内全域に避難指示を発令、避難所が開設され、避難が呼びかけられました。
本市の災害救助法の適用について、以下伺ってまいります。
1点目、災害救助法第2条第2項のいわゆるおそれ適用の目的と支援内容をお示しください。
2点目、今回、本市は当条項が適用されたものか、その理由をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.137 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) お答えいたします。
災害救助法第2条第2項のいわゆるおそれ適用は、災害が発生するおそれがある段階において、市町村における避難先の確保を促すことなどを目的に県が適用を決定するもので、国、県による支援の対象経費として民間施設等の避難所設置に要する借り上げ費などが定められております。
令和6年台風10号については、本県において特別警報が発表されるなど、災害による被害を受けるおそれが生じたことから、8月28日付で県内全ての市町村に対して当条項が適用されました。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.137 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
おそれ適用は、災害が発生するおそれがある場合に避難先の確保を促すことなどを目的に県が適用を決定するということでした。今回、本市も含めて県内全ての市町村に対して適用されたのは、第2条第2項のおそれ適用だったことを確認いたします。
次に、質問の3点目、今回の避難所運営における人件費等の国からの支弁の見込みと課題認識をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.137 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 本市においては、今回、当条項が適用されたものの、対象経費が発生しなかったことから国からの支弁はない見込みです。当条項の主な課題としては、今回のように避難所の借り上げ費が発生しないケースにおいては、避難所運営に要する市職員の時間外勤務手当等が多額となっても人件費は支弁の対象とならないことと考えております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.137 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
災害救助法のおそれ適用の場合、本市では今回のように避難所運営における人件費は対象外であることが分かりました。本市は100か所近くの避難所を開設しましたが、国や県からの支援対象とならないことは課題であるという御認識もお示しいただきました。
そこで、4点目に伺います。
当条項、いわゆるおそれ適用で対象外となっている人件費に関して、これまで本市はどのように対応してきたものかお示しください。
以上、答弁願います。
P.137 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 当条項が適用された令和4年台風14号の際にも、避難所運営に要する人件費については、国、県による負担の対象外とされたところです。また、本市が加入している全国市長会の防災・減災費用保険においても、当条項が適用された場合は保険金の支払い対象外であったことから、県市長会等を通じて要望を行った結果、国、県による一部の費用負担が行われたところです。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.137 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
本市は、全国市長会の防災・減災費用保険に入って対応していることも分かりました。おそれ費用となっても、その当時保険適用が行われなかったことから国に要望し、費用負担が行われたことも明らかになりました。
災害救助法が適用された場合、これはおそれ適用の場合であっても国の法定受託事務に切り替わると伺っていますので、県や国が避難所開設についての経費を支援すべきと考えるものですが、現在、自治体が保険に入って災害に備えなければならない状況となっています。
そこで、全国市長会の防災・減災費用保険制度について伺います。
質問の1点目、制度の概要と本市が加入した経緯をお示しください。
2点目、本市が負担した保険料の推移を令和2年度から6年度でお示しください。また、課題認識をお示しください。
3点目、避難所開設にかかった経費と本市への支払い金額の実績を令和元年度から5年度でお示しください。また、台風10号での対象経費と本市への支払い金額の見込みをお示しください。
以上、答弁願います。
P.138 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 防災・減災費用保険は、大雨や台風など自然災害の発生等において、避難指示または高齢者等避難の発令を要件として、市が負担した防災費用等の一部に対し保険金が支払われるものです。当保険は平成29年度に創設され、本市においては費用負担の軽減を目的に30年度から加入しております。
本市負担の保険料を令和2年度から6年度まで順に申し上げますと、492万6,504、492万3,672、491万9,700、491万2,134、874万3,350円です。課題としては、6年度から保険料が大幅に引き上げられていることから、本市の財政負担が重くなっていることが挙げられます。
防災・減災費用保険では、避難所開設に要した人件費が主な対象経費となっており、保険対象のその経費と本市の保険金収入を令和元年度から5年度まで順に申し上げますと、経費が3,405万3,365、4,971万779、1,286万7,049、109万4,517、1,593万7,121円、保険金収入が700万9,185、1,427万356、629万6,354、87万5,613、1千万円となっております。また、今回の台風10号での対象経費は現在集計中ですが、500万円を上限に経費の8割が保険金として支払われる見込みです。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.138 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
保険料は約500万円で推移してきましたが、今年度は400万円近く引き上がったことが分かりました。九州では災害が相次いでいることから自治体の保険料の負担も大きくなっているようです。また、国や県から費用負担があった令和4年度を除いて1つの災害につき上限500万円の保険が支払われるものの、それ以上かかった場合には持ち出しが発生しています。5年度は経費が約1,600万円、そのうち1千万円を保険金収入で補い、約600万円を市費で支払っているということも分かりました。
私は、法定受託事務であることからも、本市の避難所開設の人件費は支援対象とするように対象項目を拡大するべきと考えます。対象となれば予算の心配なく避難所を開設できるとともに、今回のように長引く停電が起きた場合でも避難所を延長し、住民の安全を確保することが可能となるのではないでしょうか。
そこで伺います。
これまで本市においては、おそれ適用では対象外となっている避難所の運営経費の人件費についても対象とするよう国に求めるべきではないでしょうか、御見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.138 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 人件費など避難所の運営経費については、国、県から適切な財政負担が行われるよう、引き続き、国、県の動向や他都市の要望状況を注視してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.138 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
他都市の要望状況を注視するということでした。災害救助法が本適用となったとしても被災の状況によって積算根拠が変わるため、今回の本市のように甚大な被害が起きなかった場合、必要経費を補うことができないという根本的な課題もあると考えます。災害救助法の抜本的見直しを図ることが必要ではありますが、現行では本市は保険に頼らざるを得ない状況だと思いますので、この実態をぜひ県や国などに共有していただくよう要望しておきます。
次に、災害時のメッセージ発信の在り方について伺います。
1点目、今回の台風10号で停電が起きた際の本市の対応をお示しください。
2点目、停電が継続している中で避難所を閉鎖した理由と市民への発信内容及び周知方法をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.139 ◎答弁 危機管理局長(水之浦達也君)
◎危機管理局長(水之浦達也君) お答えいたします。
停電の対応につきましては、特別警報級の台風第10号の接近に備え災害対策本部を設置し、避難指示の発令や避難所の開設を迅速に決定したほか、台風による被害状況の把握に努めるとともに、停電について市民から問合せがあった際には、九州電力の連絡先やホームページ等を案内したところでございます。
避難所につきましては、特別警報の解除や暴風域を抜けたこと、その後の大雨や暴風の予測などを総合的に判断し、大雨による土砂災害、洪水の危険性が低下したことから避難指示を解除し、開設していた98か所の避難所を順次閉鎖したところでございますが、閉鎖に当たっては、閉鎖時刻等を避難者に直接お伝えしたほか、本市のホームページやLINEなどで周知を図ったところです。なお、停電などの理由から自宅に帰ることが困難な避難者に対応するため、9か所の避難所については継続して避難者を受け入れたところでございます。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.139 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
避難所を閉鎖した後も停電対策として9か所の避難所は引き続き開設したことは評価できるものの、周知徹底されていないために市民には伝わらなかったのではないでしょうか。市内の2万世帯で停電が解消されず取り残されている方々への本市の対応やメッセージは極めて弱かったということは指摘しておきます。
そこで、最後に、市長に伺います。
停電で不安に思っている市民や台風による家屋被害等に遭った住民に対して、市長はメッセージを発するべきではなかったでしょうか、市長の見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.139 ◎答弁 危機管理局長(水之浦達也君)
◎危機管理局長(水之浦達也君) 台風第10号につきましては、特別警報が発表されるなど、記録的な暴風や大雨などのおそれがあったことから、市民の皆様に早めの避難行動や台風対策等を実施していただくよう市長からメッセージを発するとともに、停電に係る九州電力の連絡先や家屋被害などを受けた際の被災者支援制度一覧を市ホームページに掲載するなど、各種情報の周知を図ったところでございます。災害時における情報発信の在り方につきましては今後も工夫を重ねてまいりますが、市長メッセージにつきましては、災害の規模や被害状況等に応じて適宜適切に発することが重要であると考えております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.139 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
局長からの御答弁でした。
市民からは停電で電波状況も悪く、情報が取れずとても不安だったこと、家族に高齢者がいて暑さで体調が心配だったことなど伺っています。枕崎市では、停電により困っている市民に対し、避難所等で携帯の充電ができるよう対応したことなども報道されていました。本市でも猛暑をしのぐためにも避難所の延長などの対応を積極的に行う必要があったのではないでしょうか。また、本市が避難所を閉鎖した時間帯でしたが、県知事は公式LINEにメッセージを発信されました。市長も今後、停電でお困りの方への対策や情報を案内することなどを優先していただき、住民に寄り添った情報発信をするよう要望しまして、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
被災者の住宅支援等について伺います。
令和3年第1回定例会において、私は、真砂町で起きた火災の消火水損による被災者からの相談を受け、生活圏での生活再建ができるよう近くの真砂本町や三和町、鴨池新町などの市営住宅に入居ができないか質疑を交わしました。そのときも入居できる住宅は限りがあり、真砂からは遠い星ケ峯などの住宅を案内されましたが、高齢で車もないことから利便性も悪く、住宅の5階に上ることが大変難しいということで諦めた経緯があります。今回は三和町や松元地域で起きた火災による被災者や周辺住民からの相談を受けましたので、以下伺います。
まず、火災で被災した方についてです。
1点目、罹災証明の発行される対象範囲と支援制度の周知方法をお示しください。
2点目、自宅に住めなくなった方や周辺にお住まいの方で被害に遭った方への支援はどのようなものがあるのかお示しください。
以上、答弁願います。
P.140 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 火災の罹災証明書の発行される対象範囲は、被害を受けられた方で消防職員が火災現場を確認及び調査したもののうち、申請があったもの全てを対象としております。また、支援制度の周知方法については、市ホームページで発信しているほか、発災時には地域福祉課、または各支所の職員が現場へ赴き、被災者に対し、支援策を掲載した被災者支援ガイドブックをお渡ししております。
火災の被災者への支援としては、発災現場において救援物資の提供や必要に応じ緊急避難先の確保などを行うほか、後日、被害の状況に応じて見舞金の支給や税や保険料の減免などを行っております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.140 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
対応をお示しいただきました。
松元地域のある団地で起きた火災では、私も周辺住民へ声かけをしたところ実は被災されていたことが分かりましたので、火災で被災した場合どのような支援が受けられるのか。また、火災保険の申請も考えられますので、火元だけでなく周辺住民にもしっかりと声かけをし、被災者支援ガイドブックを積極的に渡していただくよう対応を求めておきます。
次に、罹災後の住居に関する支援について伺います。
まず、市営住宅の行政財産目的外使用の考え方をお示しください。
次に、同住宅の随時募集についての考え方をお示しください。
そして、当局の課題認識をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.140 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) お触れの住宅については一時的な避難施設として提供するものであり、収入基準等の入居者資格要件は問わないこととしているほか、敷金や退去時の修繕費用は求めていないところでございます。
また、市営住宅の随時募集は定期募集において申込みがなかった住宅について先着順で募集を行っているものでございます。
罹災後の住宅に関する支援については、被災者の事情を踏まえ、迅速に対応することが課題と考えております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.140 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
課題認識としては、被災者が生活圏で引き続き生活を再建することができないことや、随時募集では敷金を支払うことから経済的負担が大きいということは共有ができませんでした。一方で、行政財産目的外使用であれば速やかに住むことができ、経済的にも負担が軽くて助かります。
次に、台風等の自然災害等で被災した方について伺います。
1点目、市営住宅における今回の台風被害での相談件数の状況をお示しください。
以上、答弁願います。
P.140 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) お触れの相談件数は、9月10日時点で、住戸内の雨漏り182件、ベランダの隔壁板破損70件、倒木25件でございます。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.140 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
雨漏りだけでも180件に上る相談があったことが分かりました。今回のように市営住宅にお住まいの方が台風などの自然災害で被災された場合でも、行政目的外使用で市営住宅に入居できると伺っています。
そこで、2点目、行政財産目的外使用の内訳と5年度と直近の実績を火災、風水害等、DV被害者等ごとにお示しください。
3点目、同住宅の確保戸数はこれまで35戸と伺っていますが、足りるとお考えか、本市の認識をお示しください。
以上、答弁願います。
P.141 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) お触れの住宅について、5年度と6年度の実績を火災、風水害及びDV被害者別にそれぞれ順に申し上げますと、5年度、2、ゼロ、8、6年度は9月10日時点で、1、4、6件でございます。
同住宅は入居が短期間であり、これまで逼迫する状況もなかったことから現在の戸数で運用可能と考えております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.141 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
今回の台風被害で4世帯が行政財産目的外使用の実績があったということを確認いたしました。35戸でも足りているという御認識ですが、対象住宅は日当平、武岡、星ケ峯、辻ケ丘の4つの住宅であり、被災者は入居したくても生活圏から大幅に離れてしまうことから、諦めざるを得ない状況があるということを課題としてぜひ認識するべきではないでしょうか。
そこで伺います。
被災した市民が生活圏内を大きく変えることなく緊急の住宅を提供できるよう確保戸数を増やし、対象住宅の拡充を求めるものですが、見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.141 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 目的外使用住宅の選定については、地域ごとの入居率などを踏まえ、検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.141 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
入居率を踏まえるとはいえ、対象住宅の拡大については検討されるという前向きな御答弁でした。被災された方の住まいの確保は最優先されるべき課題だと思います。行政財産目的外使用のそのほとんどがエレベーターなしの高層階であり、高齢者にとっては5階まで階段を上ること自体が大変厳しい状況となっています。今回、相談のあった方も星ケ峯住宅を見に行きましたが、75歳の高齢であり、「階段で5階はきつい」と言って諦めざるを得ませんでした。このような実態にも配慮していただくよう要望して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
特定利用空港・港湾の指定についてです。
本年第2回定例会に引き続き、鹿児島港の指定に反対する立場で、以下伺います。
まず、県内の指定の状況と確認事項の内容をお示しください。
以上、答弁願います。
P.141 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 県内では、鹿児島、徳之島の2空港と鹿児島、川内、志布志、西之表、名瀬、和泊の6港湾が先月26日に特定利用空港・港湾とされたところです。また、国と県が確認した文書には、港湾管理者は、平素において自衛隊・海上保安庁の運用や訓練等による港湾施設の円滑な利用について、港湾法等を踏まえ、適切に対応すること。自衛隊・海上保安庁と港湾管理者は、国民の生命・財産を守る上で緊急性が高い場合等は、民生利用に配慮しつつ、緊密に連携しながら、自衛隊・海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるよう努めること。防衛省・海上保安庁・港湾管理者との間において連絡・調整体制を構築し、円滑な利用に関する具体的な運用のための意見交換を行うことが記載されております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.141 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
鹿児島県は鹿児島港の指定を受け入れたということでした。
そこで、鹿児島港の指定について伺います。
1点目、本市への説明とその内容をお示しください。
2点目、説明に対する市の意見はどのようなものだったのかお示しください。
以上、答弁願います。
P.142 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 先月7日に県土木部長ほかが来庁され、県から、円滑な利用に関する枠組みは民生利用を主とするものであり、管理者の権限が変わるものではないこと。整備や既存事業の促進は既存の制度に基づき進められること。災害対応時に迅速に対応でき、能力を最大限に発揮できることなどを国に確認したこと。県としては、今回の国の取組は必要な整備が着実に行われるものと期待するところ、また、災害時における迅速な対応にも資するものであると期待するところであり、国と円滑な利用に関する枠組みを確認する方向で調整を進めたいとの説明があったところでございます。
本市からは、県に対し、市民の不安が生じないよう国と連携しながら丁寧な対応をしていただくとともに、必要に応じた情報提供を求めたところでございます。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.142 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
県が指定を受け入れるということを市長はお認めになったということを確認いたします。丁寧に対応するよう求めたということでしたが、市民には昨年の検討段階から一切説明もない、内容も全く明らかにされていません。市民の不安が広がるのは当然ではないでしょうか。そのような中で、市長がこのような県や国の姿勢を認めることは許されないのではないでしょうか。
そこで、改めて伺います。
質問の3点目、対象港区は明らかになっているものかお示しください。また、今後の工事内容については港湾計画にのっとって行われるものか。その場合、負担金の考え方をお示しください。
質問の4点目、既存事業の促進に加え、安全保障上の観点からの重要性も加味されるとありますが、その場合でも負担金を支払うのか、御見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.142 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 対象となる施設については幅広く検討すると国から説明があったところで、工事内容についても示されていないところでございます。なお、国によると、「特定利用港湾における整備や既存事業の促進は民生利用を主とするものであるため、港湾整備事業の既存の制度に基づくこととしている。このため、整備費についても既存の制度に基づいて、これまでどおり国とインフラ管理者等がそれぞれ必要な費用を負担することとなる」とのことでございます。
特定利用港湾における整備や既存事業の促進は、既存の制度に基づくこととされていることから、負担金については受益者負担の考え方から関係法令等に基づき支出することとなります。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.142 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
負担金の考え方をお示しいただきました。既存事業であれば受益者負担の考え方から、これまでも負担金は支払ってきているので一定理解することはできます。しかし、安全保障上の観点ということで軍事利用ができるように港湾の改良などが新たに事業として加わった場合でも、その負担金を支払うことには納得がいきません。何を根拠に受益者負担とするのか、本市が港の軍事利用に加担するということになりかねません。
次に、意見交換会について、質問の1点目、防衛省と3つの特定利用港湾が指定された高知県が行った意見交換会の内容をお示しください。
2点目、今後、鹿児島県における意見交換会が行われるものかお示しください。
以上、答弁願います。
P.142 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) お尋ねの意見交換会は今月4日に開催されており、内容は連絡・調整のための連絡先の確認のほか、国から年度内の利用計画表が示されるとともに、本表への記載対象となる事業等に関する説明があったと高知県のホームページに公表されております。
国との確認文書には、防衛省、海上保安庁、港湾管理者との間において連絡・調整体制を構築し、円滑な利用に関する具体的な運用のための意見交換を行うと記載されていることから、今後、鹿児島県においても意見交換会が行われるものと考えております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.143 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
今後、鹿児島県でも意見交換会は開かれるということでしたが、先日、高知県で行われた意見交換会は非公開だったと報道されています。これでは何が話し合われたのかが市民に明らかにされず、改めてこのような閉鎖的な国のやり方は大変問題だということは指摘しておきます。
次に、特定利用港湾に指定されることによる危険性について伺います。
質問の1点目、防衛省のQ&Aでは、武器や弾薬の輸送と明記されていることから、さつま町はじめ計画が相次ぐ弾薬庫建設との関連性は否定できないのではないでしょうか。当局の見解をお示しください。
2点目、平時とは何か。自衛隊が米軍に補給等ができる重要影響事態や米軍と共に自衛隊が武力攻撃、いわゆる後方支援ができる存立危機事態が含まれると考えますが、当局の御認識をお示しください。
以上、答弁願います。
P.143 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 弾薬庫建設との関連性については分からないところでございます。
平時については、円滑な利用に関する枠組みには定義されておりませんが、高知県から国への、国民の生命・財産を守る上で緊急性が高い場合又は艦船の航行の安全を確保する上で緊急性が高い場合には、存立危機事態や重要影響事態が含まれ得ると考えてよいか、含まれる場合には、港湾法等の既存法令に基づき、利用調整を行うものと考えてよいかとの質問に対し、国からは、おただしのとおり相違ないとの回答がなされております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.143 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
防衛省は、これまで平時の民生利用が主などと繰り返しごまかしてきましたが、この平時には存立危機事態、重要影響事態まで含まれることが明らかになりました。国は、武力攻撃事態や武力攻撃予測事態以外を平時といって危険性を覆い隠し、実際は自衛隊と米軍が必要なときにいつでも港湾や空港が利用できるようにし、かつ軍事利用しやすいようにあらかじめ整備しておくことを目的としています。弾薬庫との関連性については否定されませんでした。防衛省のQ&Aには武器や弾薬の輸送も可能であり、弾薬庫の運用のために鹿児島港が利用されることは十分に想定され、加えて、後方支援の際にその弾薬を積んでいくことも可能となります。
最後に、市長に伺います。
市民へのリスクを想定した説明は一切なされておらず、懸念が払拭されていない中で、今後なし崩し的に軍事的に利用される懸念があり、特定利用港湾は攻撃対象となる可能性があると考えますが、市長はそれをお認めになるのか、市長の見解をお示しください。
以上、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.143 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 国によると、特定利用港湾は新たに自衛隊の基地や駐屯地を設置するものではなく、自衛隊、海上保安庁はこれまでも港湾を利用してきており、今回、円滑な利用に関する枠組みが設けられた後も自衛隊、海上保安庁による平素の利用に大きな変化はなく、そのことのみによって当該施設が攻撃目標とみなされる可能性が高まるとは言えないとのことでございます。本市としましては、引き続き、国や県に対し、市民の不安が生じないよう丁寧な対応と必要に応じた情報提供を求めてまいりたいと考えております。
[園山えり議員 登壇]
P.143 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
改めて、今回、武力攻撃されるような事態以外は全て平時と位置づけられ、軍事的な利用が可能だということが明らかになりました。そのことを市長はお認めになったにもかかわらず、そのリスクを市民には一切伝えられていないということは重大な問題です。市長はこの鹿児島港を危険な港湾にさせないためにも、今からでもぜひこの指定に反対するべきではないでしょうか。
また、市長は、丁寧な対応を求めると繰り返されておりますが、国や塩田県知事にもっと強く求めてください。少なくとも高知県は県独自のQ&Aをつくり、県知事が防衛省に直接質問するなどし、その回答を県民に公表しています。また、高知県と特定利用港湾に指定された3港湾の3自治体との意見交換の場を行い、市民に公表しています。鹿児島県は情報が少な過ぎます。災害対応時に迅速に対応できるなどというごまかしも許されません。
市長、国言いなり、県言いなりの姿勢では市民が戦争に巻き込まれる危険性が増すばかりであり、市民の命と財産は守れません。市長が指定のこの撤回を求めるよう強く要請し、質問を終わります。
以上で、私の全ての個人質疑を終わります。