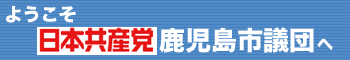P.174 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
質疑の流れ上、重複する部分があることをあらかじめ御了承ください。
最初の質問は、市長の政治姿勢についてです。
質問の1点目、下鶴市長は、観光資源となる「稼げる」スタジアム整備を公約とし、この4年間取り組まれてきました。多機能複合型スタジアム、いわゆるサッカー等スタジアムは、代表質疑でもるる質疑が交わされているように鹿児島サンロイヤルホテルの移転の方針が発表され、その跡地が候補地となる可能性について新たな局面を迎えています。しかしながら、スタジアム需要予測等調査・整備検討支援業務で検討された本港区の3つの候補地が白紙に戻って以来、北埠頭など事業費が膨れ上がっていると感じています。鹿児島サンロイヤルホテル跡地についても代表質疑で明らかになった路線価を基に土地代だけは報道が試算していましたが、建物の撤去費用や店舗などの補償費用などが想定される上、債務超過に陥っているホテルの移転自体に財政支援を求められる可能性もあるのではないかと考えます。このような現状を踏まえると、そもそも鹿児島市が孤軍奮闘でやるべき事業なのか甚だ疑問です。
そこで、多機能複合型スタジアムを物心両面で共に整備を目指せる企業・サポーターを探し、民間主導にする考えはないか見解をお示しください。
質問の2点目、明和小中一貫校につきましては、本市議会に付託された明和小・中学校の一貫校化の動きについて地域住民・団体が十分な議論をできる場を求めることについての陳情が不採択となり、市長、教育長から地域の方々の相応の理解や合意が得られているとの答弁が示されているところですが、地域住民から成る希望に満ちた明和を創る会の皆さんが改めて地域住民の不安や懸念の声を届けようと明和地域に住民アンケートを全戸配布し、2週間ほどの結果を取りまとめ、報告する記者会見を行いました。
ふれあいトークの際、地域住民の声を大切にしたいと述べられた下鶴市長は、この記者会見についてどのように受け止められ、地域でのアンケートの内容についてどのように考えられたのか見解をお示しください。
以上、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.174 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 大園たつや議員にお答えいたします。
スタジアムの整備につきましては、オール鹿児島での取組が前提になるものと考えており、県、市だけでなく、クラブを含む民間の果たす役割も大変大きなものと考えております。現在、県と一緒になって候補地選定を進めているところでございますが、検討の状況に応じて財源確保、機運向上など民間と連携してまいりたいと考えております。
お触れの記者会見につきましては、明和小中一貫教育に反対のお立場の団体が地域住民に対して行った回答率約7%のアンケート結果を報告されたものと伺っており、様々な御意見があることを承知したところでございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.174 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
鹿児島市議会で調査を行ってきた豊田スタジアムやヨドコウ桜スタジアムはまさに企業主導で、自治体は維持管理を支援する手法です。鹿児島市に大企業はないと諦めずにどうしてもスタジアムを造りたい市長の熱意を企業に伝え、口だけでなく心も寄せてお金も出す企業を支援する方針に変えられないものでしょうか。スタジアム建設の問題は、増大する事業費、財源なき提案、役割分担なきオール鹿児島です。このままでは建設的な議論すら困難ということははっきりと申し上げておきたいと思います。
明和小中一貫校については、会の皆さんが地域で行ったアンケートは現時点では251件の回答総数ですが、乳幼児や児童生徒の保護者の意見が23%あること、賛成の意見も寄せられていることから、恣意的なものではないということ、酌み上げるべき意見もあると思います。特に2年ほど前まで義務教育学校に勤務していた中学校教諭から、「中学生の幼児化が顕著だった」、「小学生もリーダーシップを発揮する6年生は中学生がいるために力を発揮できない」、「節目となる卒業式や入学式がなくなる」、「授業時間が45分と50分で違い、ノーチャイムにすると時計の読めない1年生はスムーズに学校生活を送ることが難しい環境」など、具体的な課題も寄せられています。私は、地域の将来を決める大事なことだからこそ、反対の声やよく分からないという皆さんを置き去りにしない丁寧な対応が必要ではないかということを申し上げておきます。
新しい質問に入ります。
こども医療費助成制度の充実については、代表質疑でもるる質疑が交わされているところですが、今回提案された思い切った充実の内容や今後の課題について、以下伺ってまいります。
質問の1点目、市独自の現物給付実施など思い切った拡充に踏み切ったことやその効果についての市長の思いをお示しください。
以上、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.175 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 私は、少子化人口減少時代に対応する中、特に子育て中の世帯や若い世代に選ばれるまちの実現を目指し、これまで子育て支援の充実に重点的に取り組んできており、こども医療費の助成は安心して子供を産み育てることのできるまちづくりを進めるための重要な施策の1つであると考えております。このため、マニフェストに掲げたこども医療費のさらなる負担軽減策について各面から検討を進めてきたところでございますが、今般、子育て中の世帯に寄り添うより一層の支援として、助成方法を現物給付方式とするとともに対象者全ての自己負担額をゼロとする制度拡充を行うこととしたところでございます。この取組により子育て世帯の負担軽減と利便性・向上を図り、次の世代を担う子供たちの未来を全力で応援してまいりたいと考えております。
[大園たつや議員 登壇]
P.175 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 市長の思い、そして、効果を述べていただきました。
保護者の皆さんをはじめとした制度充実を求める市民運動は30年以上続いており、長年の市民要望が結実しました。長年運動に取り組んできた市民団体の皆さんに私が取材をしたところ、歓迎の声を寄せていただきましたので紹介したいと思います。
「お財布のお金では足りなさそう、今日は受診を諦めようと受診抑制を起こす償還払い方式は子供たちが健康に育つ権利を侵害している。早くみんな窓口無料にと長年かけて訴え、運動してきたことがやっと実現します。とてもうれしいです。季節の変わり目にはよく熱や喉の痛みを訴える我が子たち、心配だけど何度も行けない。もう少し様子を見ようと、自分で何とかしようとして症状がひどくなってしまい、後悔し自分を責めることが多かったですが、これからはひどくなる前に病院へ連れていくことができます。このような政策が広がり、安心して子育てがしやすい環境になるよう、ますます充実していってほしいと願います。」3つの医療費の窓口無料で安心して医療が受けられるかごしまをつくる会、木下加奈さん。
以上です。
私も鹿児島市議会に初めて席をいただいた16年前から機会あるごとに取り上げてきましたが、本来、県の制度であるにもかかわらず、県は自治体独自の現物給付の実施を阻んできました。その上、今回も自己負担について不十分な充実にとどまりました。市長をはじめ、関係局長、当局の皆さんがこれらを乗り越えて決断されたことを心から歓迎いたします。
質問の2点目、本市の拡充後の制度は中核市の中でどのような位置づけになるものか、本市と都市の規模が類似する人口50万人以上の自治体でお示しください。
以上、答弁願います。
P.176 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) お答えいたします。
本市を除く人口50万人以上の中核市6市における令和6年4月1日時点のこども医療費助成制度で申し上げますと、助成対象を中学生までとする都市は2市で、いずれも自己負担はなく、高校生までとする都市は4市で、自己負担ありが2市、なしが2市となっております。拡充後の本市制度は助成対象を中学生まで自己負担なしとしている川口市や姫路市と同じグループに位置づけられます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.176 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
これまで全国で一番遅れている制度だと指摘してきましたが、人口50万人以上の自治体と肩を並べる制度となりました。私が今回注目したのは県制度との関係です。八王子市のある東京都や姫路市のある兵庫県は自己負担があるものの、それぞれ高校卒業まで、宇都宮市がある栃木県は中学校卒業まで自己負担なしとなっているのに比べて、松山市のある愛媛県や鹿児島県は対象が未就学児までの上、自己負担を求める制度となっています。つまり、同じ中学校卒業まで窓口負担なしといっても、県の制度次第では自治体の大変な努力と財源が必要になる。加えて、本市も含めた7市の中で14歳以下の人口比率が13.5%、出生数も4,410人で本市はトップであり、このような条件の下での拡充の意義をぜひ皆さんに知っていただきたいと思います。
質問の3点目、代表質疑でも質疑が交わされた県制度との課題について伺います。現物給付を独自に実施した場合、制度から外れてもらうとの県のこれまでの見解と制度の実施時期が来年4月からとした関係をお示しください。
以上、答弁願います。
P.176 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 県の制度との関係でございますが、県に伺ったところ、現行制度においては、本市が独自に現物給付方式を導入した場合、県補助事業の対象外になるが、県の制度見直し後は現物給付方式の対象年齢を本市が独自に拡充した場合においても未就学児については対象となるとのことでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.176 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
今年から市独自の現物給付をスタートさせた垂水市などは制度から外され、補助金が支給されませんでしたが、来年度の県制度の充実を待つことで、制度から外れることなく約3億円の補助金を確保したと考える必要があります。県が現制度を2分の1補助ではなく全額責任を持てば約6億円、本市と同様に中学校卒業まで自己負担なしにして2分の1の補助とした場合は約10億円の財源が生まれます。今後は県が自らの制度にいかに責任を持つかが県下自治体の負担軽減につながることを踏まえ、県市長会で引き続き強く求めるよう要請いたします。
質問の4点目、今後の課題について、以下伺います。
令和6年度、国は、自治体が独自に現物給付を実施した場合、国保会計から補助金を減額するペナルティーについて、自治体の子育て支援を後押しする立場から18歳まで全廃し、全国で拡充が進んだことは前回の質疑で御承知のことと思います。ところが国は、国保の保険者努力支援制度に受診頻度や医療費が減少したかの指標を設け、窓口負担をさせることで加算するインセンティブを持ち出すという、これまでの動きに逆行する方針を打ち出しています。
このような対応が受診抑制につながらないよう国に求めるべきと考えますが、見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.177 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 国保の保険者努力支援制度につきましては、こどもの医療の適正化等の取組という新たな指標が設けられたと承知しておりますが、本市におきましては、今回のこども医療費助成制度の拡充を着実に推進し、子育て世帯の負担軽減等を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.177 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
当局としてはそのようなインセンティブでせっかくの窓口負担なしを後退させるつもりはないとの強い意思と受け止めました。様々な子供施策の中で命に直結する制度として、県の制度拡充による財源の確保や国の逆行を乗り越えて大切にしていただきますよう強く要請し、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
児童発達支援・放課後等デイサービスのいわゆる障害児通所支援の一部有料化の検討についてです。
障害児通所支援について、昨年から始まった一部有料化の検討に去る6月13日、通所支援を利用する保護者の皆さんが市当局を訪れ、「当事者抜きで声を聞かずに進めてほしくない」、「子供が笑顔で通学しているので、ほかのお母さんにも不安なく鹿児島市で子育てが障害があってもなくてもできる状態であってほしい」と切実な声を届け、現在無料となっている市の独自助成の継続を求められました。その後、1万筆を目標に署名活動に取り組まれ、9月2日に市当局に直接署名が届けられたことから、第2回定例会に引き続き、以下伺ってまいります。
質問の1点目、現行制度の継続を求める署名の数や要望など、その内容と併せて一言メッセージを添えておられたとお聞きしていることから、特徴的な市民の声をお示しください。
質問の2点目、署名についての当局の受け止めをお示しください。
以上、答弁願います。
P.177 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) お答えいたします。
署名の内容は、児童発達支援・放課後等デイサービスに通う全ての子供たちが安心して利用できるように利用者負担無料を継続し、恒久無料化を実現することを要望するもので、市内外の方から合計で2万2,592筆の署名が提出されました。特徴的な声としては、「現在まで無償で通わせていただき感謝している」、「引き続き支援の継続をお願いしたい」や「有料化になると本当に療育を必要とされるお子さんも敬遠してしまうこともあると思う」などの声がありました。
今回寄せられた署名やメッセージは、通所支援を実際に利用している保護者や関係者からの率直な声として受け止めております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.177 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
8月には天文館図書館で児童発達支援や放課後デイの日頃の活動の様子や子供たちの生き生きとした笑顔を写真で展示し、また、鹿児島市の療育の場づくりについての歩みを紹介する「こどものえがおいっぱい!パネル展」を開催するとともに猛暑の中を長時間汗だくになって街頭から切実な訴えと署名のお願いに取り組んで市民団体から届けられた署名は2万2,592筆、目標の倍にも及んだ切実な声を率直な声と当局も受け止めてくださったものと理解します。
そこで、質問の3点目、署名を踏まえて、有料化の検討状況及び質の確保についての今後の対応をお示しください。
以上、答弁願います。
P.177 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 障害児通所支援の利用者負担独自助成については、令和5年9月の防災福祉こども委員会で今後の在り方の検討を行うことの報告を行うとともに、市障害者自立支援協議会など、様々な場を通じて関係者から御意見をいただきながら検討を進めてまいりました。このような中、6年9月2日にはお触れの署名が提出されるなど、現在においても様々な御意見や御要望が寄せられていることなどを踏まえ、引き続き検討を続けているところです。また、質の確保については、国のガイドラインに即した運営が図られるよう事業所へ指導や助言を行っているほか、国の基準を超えて専門指導員等を配置した事業所への助成や公開療育による事業所のスキルアップ促進等も行っており、これらの取組を通じて、引き続き対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.178 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
市民からの切実な声を踏まえて、9月議会で提案予定だった方向性については出さないということに一定の評価をするものですが、市民団体の要望は、今後も子どもの権利条約に則ったこのすばらしい取組、利用者負担無料を継続し、恒久無料化を実現してくださいであり、引き続き、在り方を検討していくということが理解できません。
私ども日本共産党の鹿児島県の地方議員団は、8月20日、21日に政府に直接、鹿児島独自の課題への対応を求める対政府交渉を行いました。その中で私は、子どもの権利条約第23条第3項に基づいて、国の責任で療育を無償化してはどうかと求めたところ、自己負担の上限額の設定や3歳から5歳の障害児の無償化に取り組んでいると前置きした上で、慎重に議論することが必要と回答しました。これは子どもの権利条約を批准している日本が簡単に無償化は考えておりませんと回答できる立場ではないことと理解しました。また、鹿児島市をはじめ、全国で療育の利用者は増加していると思うが、それを抑制する方針を厚生労働省は持っているのかとの問いには、そのような方針は持っていませんし、考えていませんと回答されました。
このようなことを踏まえ、この質問の最後に市長に伺います。
質問の4点目、市民団体から市長に寄せられた手紙の内容と市長の所感をお示しください。
質問の5点目、子どもの権利条約第23条第3項の内容とそのことを踏まえ現行制度を継続すべきと考えますが、市長の見解をお示しください。
以上、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.178 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 署名とともにお寄せいただいた手紙には、これまで利用者負担無料を継続してきたことに対する感謝の言葉や無料継続への思いなどが記されており、保護者の皆さんなどの率直な御意見をいただいたものと考えております。
子どもの権利条約第23条には、障害を有する児童の特別な必要を認め、与えられる援助は、父母または当該児童を養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えられるものなどと規定されております。利用者負担独自助成については、これまでの市議会での議論や他都市の状況を踏まえるとともに、サービス利用者や関係者の御意見も参考にしながら、事業の持続可能性や利用者への影響など、引き続き各面から在り方を検討してまいりたいと考えております。
[大園たつや議員 登壇]
P.178 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 市長、私はこれまでこの独自助成が子どもの権利条約を体現するものであること、同条約を全ての取組の基礎とするこどもの未来応援条例を持つ自治体であること、有料化で質がよくなるわけではないことなど議論を尽くしてきましたし、署名によって切実な市民要求も示され、これ以上検討する余地はないと思っています。私も、必死に署名を集められた皆さんも、市長に当局の方針をなぞった答弁を聞きたいわけではありません。こどもの未来応援条例を提起・提案した市長として、次期市長選への決意を固めた政治家としての決断を聞きたいのです。
一部有料化の検討を続けるのか、現行の制度を継続するのか、再質問いたします。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.178 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 先ほども申し上げましたとおり、利用者負担独自助成については、お触れの署名が提出されるなど、現在においても様々な御意見や御要望が寄せられている状況であることから、これまでの市議会での議論や他都市の状況を踏まえるとともに、サービス利用者や関係者の御意見も参考にしながら、事業の持続可能性や利用者への影響など、引き続き各面から在り方を検討してまいりたいと考えております。
[大園たつや議員 登壇]
P.179 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
同じ答弁の繰り返しであり、残念です。せっかく拡充されたこども医療費助成制度と併せて、鹿児島市は子供の命と発達に責任を持ち、可能性とその未来を応援する自治体ですよと声を大に全国に発信できる日が一刻も早く訪れることを強く要望いたします。
また、市民団体の皆さんとは公務でお会いできなかったとお聞きしておりますが、ぜひ会う機会をつくっていただき、その思いを聞いてくださいますよう最後にお願いを申し上げまして、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
児童クラブの待機児童解消と課題についてです。
質問の1点目、今年5月1日に本市の待機児童数が公表されていますので、以下伺います。
まず、過去3年間の待機児童数をお示しください。
次に、直近の待機児童数の校区別、学年別内訳をお示しください。
また、待機児童の特徴と課題をお示しください。
以上、答弁願います。
P.179 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 5月1日現在の児童クラブの待機児童数につきまして、令和4年度から6年度まで順に申し上げますと、34、64、59人でございます。
6年度の待機児童数の内訳でございますが、校区別では、福平13人、坂元台12人、西谷山6人、大明丘と原良は5人、谷山、西田、郡山は4人、西紫原、中郡、中洲は2人となっており、学年別では、4年生26人、5年生19人、6年生14人でございます。
児童クラブは3年生までの利用希望が多く、低学年の児童から優先的に受け入れているため、4年生以上で待機児童が発生している状況にあり、その解消を図ることが課題であると考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.179 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
今年度は保育所等利用待機児童がゼロになったことが注目されていますが、一方で児童クラブの待機児童はいまだに生じており、特徴としては、低学年の児童を優先しているためか高学年の児童が待機している状況のようです。こども家庭庁と文部科学省では、この間、次代を担う人材を育成し、加えて共働き家庭が直面する小1の壁を打破する観点から、放課後児童クラブの待機児童の早期解消、放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的な実施の推進等による全ての児童の安全安心な居場所の確保を図ることを内容とした新・放課後子ども総合プランに基づく取組を推進してきたようです。
そこで、質問の2点目、放課後児童対策パッケージについて、以下伺います。
まず、同パッケージの内容と期間をお示しください。
次に、本市での同パッケージにおける取組をお示しください。
次に、学校施設内の設置や特別教室の一時的利用、いわゆるタイムシェアの事例と数をお示しください。
以上、答弁願います。
P.179 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 放課後児童対策パッケージは、児童クラブを開設する場や運営する人材の確保などにより152万人分の早期の受皿整備の達成に向け、5年度と6年度におけるこども家庭庁と文部科学省が連携した取組をまとめたものでございます。
同パッケージに基づく本市の主な取組でございますが、補助率が3分の1から6分の5にかさ上げされた補助制度の活用により専用施設を整備したほか、業務負担の軽減を図るためのICT化に要する補助制度の活用により保護者連絡等のシステムを導入することとしております。
学校施設内への設置等につきましては、特別教室の一時的な利用、いわゆるタイムシェアによる事例はございませんが、学校敷地内に原良第四・第五児童クラブの2クラブを整備したほか、余裕教室等の活用により皇徳寺児童クラブなど4クラブを移設したところでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.180 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
新・放課後子ども総合プランでの目標である152万人分の受皿整備が困難な見込みとなっていることを踏まえ、その達成に向けて本パッケージは令和5年、6年度に取り組む内容をまとめたもので、今年度が最終年度となっています。
本市の取組も明らかにしていただきましたが、そもそも児童クラブの設置は、候補地の選定、用地の買収、場所によっては用途の変更、人材確保、建設と時間がかかるものです。同パッケージでは即応性があるものとして余裕教室の活用や特別教室や図書館などの一時的利用、タイムシェアなども提案されています。私自身も学校敷地内への設置や移設、余裕教室の活用を求めたときに学校側からよいお返事がいただけず、長い時間を要した経験もありますし、最近でもそのようなお話を耳にする機会があることから、教育委員会の協力なしには進まない課題ではないかと考えます。
そこで、同パッケージに対する教育委員会の認識と待機児童解消のための連携についての見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.180 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) お答えいたします。
放課後児童対策パッケージでは、待機児童の解消に向けて学校教育に支障が生じない範囲での余裕教室等の活用が示されており、学校の実情に応じた教室等の活用については学校や関係部局と連携して検討することが必要であると考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.180 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
他の自治体では児童クラブを教育委員会が所管しており、自らの責任として積極的に学校敷地内の活用を推進している事例もあるようです。児童の安心安全な放課後を確保する居場所づくりへの協力を言葉だけではなく具体的に学校に対して求めてくださいますよう強く要請いたします。
質問の3点目、待機児童数のカウント方法の課題について、以下伺います。
まず、ある児童クラブ運営委員会からの要望と意向調査の内容をお示しください。
以上、答弁願います。
P.180 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) お触れになった調査等でございますが、運営委員会によりますと、3年生以下の児童が利用しているが、待機児童がいない状況にあるため、全ての児童を対象に利用希望の有無について調査を行ったもので、その結果、高学年にも利用希望があったことから、本市に対し学校施設の活用などによる施設整備を要望したとのことでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.180 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
本市の待機児童の公表ではこの児童クラブ運営委員会の校区は待機児童ゼロとなっているようですが、意向調査によれば、現在の利用者55人とは別に、一刻も早く利用したいが28人、余裕があれば利用したいが56人となっており、本市の公表が実態を反映していないことが分かるとともに、この課題はこの校区だけの問題ではないと考えることから、待機児童が表面化しない課題について当局はどのように捉えているものか認識をお示しください。
以上、答弁願います。
P.180 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 児童クラブは低学年から優先的に受入れを行っていることから、高学年の児童の保護者などが申請状況から利用が難しいと考え、申請を控えるケースもあるところでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.180 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
市が直接利用調整する保育所等と違い、児童クラブの利用調整は各運営委員会に任されており、各運営委員会は候補地の確保や人材の確保などに苦慮された上で、居場所が確保されない場合、その責任感から保護者に対して自宅で安全に過ごせるようにとお願いすることもあるとお聞きしています。その結果、保護者は諦め、希望すら出さず、結果として待機児童が表面化しないということになっているのではないでしょうか。
このような課題を踏まえて、潜在的な待機児童を可視化するために独自の利用意向調査をすべきと考えますが、見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.181 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 利用意向調査の実施については考えておりませんが、利用を希望する児童の状況について、定期的に開催される連絡協議会や主任支援委員会で情報共有を行うなど、各児童クラブと連携を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.181 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
こども家庭庁のホームページに放課後児童対策の事例集が掲載されていますが、その中に適切な利用調整(マッチング)の項目があります。そこには沖縄市が市域内の児童クラブへの利用調整を一手に行い、ニーズを適切に把握する放課後児童支援センターの事例が掲載されています。実態が把握できないという課題は全国的にあるもののようですが、本来、小学6年生まで入ることのできる児童クラブにどれほどのニーズがあるのか、どれだけ居場所が不足しているのかを正確に把握することが第一歩だということは指摘いたします。
これまでの質疑を踏まえて、子供たちの安心安全な放課後を確保するため児童クラブの待機児童を解消すべきと考えますが、見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.181 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 今後とも校区ごとの需要予測の精度をさらに高め、余裕教室の活用等による施設整備や民間事業者の活用による受皿確保、支援員等の処遇改善や業務負担の軽減による人材確保に努めるなど、待機児童解消に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.181 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
保育所等利用待機児童のゼロに続き、子供たちの安心安全な放課後を確保するために児童クラブの待機児童のゼロを目指して取り組まれますよう強く要請し、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
夏の風物詩である全国高等学校野球選手権大会は、昨年に続く酷暑の下で、開幕から3日間、日中の暑い試合を避け、午前と夕方の2部制が実施されました。兵庫県では35度以上の酷暑が続き、熱中症警戒アラートが連日出される下で、熱中症疑いで手当を受けた選手は56人、観客らは282人を数え、この5年間で最も多かったと言われています。スポーツや教育にとって安全は一義的な課題であり、その対策は急務と考えることから、記録的な猛暑と学校体育館への空調の設置について、以下伺ってまいります。
質問の1点目、熱中症警戒アラートの回数と本市の現状をお示しください。
以上、答弁願います。
P.181 ◎答弁 環境局長(森崎浩文君)
◎環境局長(森崎浩文君) お答えいたします。
奄美地方を除く鹿児島地域における熱中症警戒アラートの発表回数について、全国で運用が開始された令和3年度から5年度まで順に申し上げますと、26、48、41回、6年度は9月11日現在で56回と過去最高を記録しており、本市においても連日、記録的な暑さが続いております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.181 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
熱中症警戒アラートの回数は奄美を除いた県全体の回数ということですが、全国でも5本の指に入る回数ということを認識し、熱中症対策を重要な施策として位置づけるべきです。
質問の2点目、避難所としての空調の必要性について認識と課題をお示しください。
以上、答弁願います。
P.181 ◎答弁 危機管理局長(水之浦達也君)
◎危機管理局長(水之浦達也君) お答えいたします。
指定避難所である市立学校の体育館につきましては空調設備が整備されておらず、避難者の健康管理などの観点からは空調機器等の設置が望ましいと考えておりますが、その利用頻度に対して設置費用が高額であるなどの課題がございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.182 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
望ましいと考えているが、課題については利用頻度と財源とのことです。確かに災害だけを考えると利用頻度は多くないと考えますが、最近の猛暑は体育の授業等にも影響を及ぼしているのではないかと考えることから、質問の3点目、学校施設としての観点について、以下伺います。
まず、学校における熱中症対策ガイドライン(鹿児島県版)の内容と本市の対応をお示しください。
以上、答弁願います。
P.182 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) 熱中症対策ガイドラインは、学校の管理下において熱中症事故の発生を未然に防ぐため、暑さ指数に応じた行動指針や熱中症の予防措置など、児童生徒等の安全を確保する体制を確立するために必要な事項がまとめられたものでございます。本市においては、本ガイドラインを参考に各学校で熱中症対策を適切に行うとともに危機管理マニュアルの見直し、改善を行う際に活用するよう指導しているところでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.182 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
今年3月に本県独自のガイドラインが作成され、本市もそれを参考に対応を行っているようです。
引き続きお伺いします。
次に、熱中症となった児童生徒の数と例年との比較をお示しください。
また、体育の授業や校外学習などへの猛暑時の対応をお示しください。
以上、答弁願います。
P.182 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) 6年度、市立学校において熱中症の疑いにより救急搬送された児童生徒数は9月10日時点で5人となっており、例年と同程度でございます。
猛暑時の対応につきましては、国からの通知や県のガイドラインに基づき授業などの前にはグラウンド、屋内運動場などで必ず暑さ指数を測定し、活動時間や内容の変更などの対応を行っております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.182 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
熱中症になった児童生徒が例年並みということは、学校での先生方の対応がしっかりしておられるということではないかと思います。現在、猛暑時の体育の授業は日陰を活用して行ったり、ほかの授業と振り替えたり、時には中止することもあるようですが、今後さらに暑くなるようなことがあれば体育の授業時間を確保すること自体が難しくなります。
そのことを踏まえて、体育館に空調を設置することによって体育の授業の安全性と時間の確保ができるのではないかと考えます。
そこで、体育の授業の安全確保のための空調の必要性についての認識をお示しください。
以上、答弁願います。
P.182 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) 屋内運動場への空調設備の設置により室温等の調整が可能となり、快適な環境で活動に取り組むことができるものと考えておりますが、各学校におきましては、大型扇風機等による換気や小まめな水分補給、時間割の変更など、実情に応じた対応により児童生徒の健康管理がなされていると承知しております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.182 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
体育館への空調設置について、教育委員会としても快適にできるものと考えているということが分かりました。
しかしながら、課題は財源ということで、この猛暑を踏まえて、学校体育館への空調の設置への補助の充実など国の動向はないものかお示しください。
以上、答弁願います。
P.182 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) 屋内運動場への空調設備の設置に係る国庫補助につきましては、5年4月の国からの通知によると、5年度から7年度にかけて、建物に断熱性があることを要件として新設に係る補助率を3分の1から2分の1に引上げを行っております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.183 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
令和5年度の4月以降、まだ国の動きはないようですが、その期間が令和5年度から7年度となっていることから、学校関連、防災関連、火山対策関連とあらゆる財源の可能性やそれらを複合的に組み合わせて活用できないのかなど、具体化に向けて真剣に検討する時期が来ていると思います。
これまでの質問を踏まえて、学校体育館への空調の設置を計画的に進めるべきと考えますが、見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.183 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) 屋内運動場への空調設備の設置につきましては、使用頻度や財政上の制約もあることから難しい状況にあると考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.183 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
難しい状況とのことですが、今を逃せばさらに難しい状況となるのではないかと懸念するところです。記録的な猛暑の下で災害に強いまちづくりと子供たちの安心安全な学校環境づくりにも寄与する学校体育館への空調の設置は待ったなしの課題だということを申し上げて、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
市営住宅行政について、この間、私は4か所で市営住宅相談会を開催したところ、それぞれでたくさんの相談が寄せられましたので、以下伺います。
まず、台風第10号での被害について、以下伺います。
質問の1点目、被害件数と主な要因をお示しください。
質問の2点目、復旧の状況と修繕費用の見通し及び財源をお示しください。
以上、答弁願います。
P.183 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) お答えいたします。
お触れの被害件数は9月10日時点で、住戸内の雨漏り182件、ベランダの隔壁板破損70件、倒木25件であり、主な要因は猛烈な風雨が長時間続いたことと考えております。
復旧は緊急性等を考慮し順次進めており、修繕費用は現在集計中でございます。財源は指定管理者の管理委託料に計上されている復旧・修繕費などでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.183 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
私も台風の直後、窓から雨が吹き込んでくるという相談を受け、当局に対応していただいているところですが、以前、同じような相談を受けて改善したところだったようです。しかしながら、大雨のたびに雨が吹き込んでいるということで、私は構造上の問題もあると考えています。ぜひその部屋だけを見るのではなく、全体の構造上の問題はないのかも含めて復旧されるよう要請しておきます。
質問の3点目、今回の台風は非常に強い風が特徴でしたが、最近の市営住宅にも雨戸はついていないようです。台風の強い風に際して雨戸の設置についての考え方をお示しください。
以上、答弁願います。
P.183 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 市営住宅の雨戸設置については、民間マンションでもほとんどないことなどから考えていないところでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.183 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
最近の台風の強さを目の当たりにしたときに一考する必要があるのではないかと思います。また、一部の市営住宅には雨戸が設置されていますが、経年劣化で壊れたり、閉まらなくなったりしているところも見受けられますので、修繕の相談があった場合には迅速に対応されるよう要請しておきます。
次に、昨年は市営住宅駐車場使用料の新設をめぐって質疑を交わしてまいりましたが、その後の駐車場管理について、以下伺います。
質問の1点目、来客用駐車場管理の再委託の状況と各駐車場管理組合の現状をお示しください。
以上、答弁願います。
P.184 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 本市が駐車場管理を委託している指定管理者によると、来客用駐車場の管理を53の福祉会等に再委託しており、そのうちおよそ4分の1が駐車場管理組合とのことでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.184 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
ほとんどの駐車場管理組合が解散、福祉会の中に駐車場係をつくったり、縮小という形を取っています。駐車場使用料の新設のときにこれまで組合が管理してきた自治がなくなると指摘してきましたが、現状は誰が管理に責任を持つのか放置状態にあるということは指摘いたします。
質問の2点目、現時点で1か所だけ直営をされている市営住宅があるようですが、その考え方及び管理の方法をお示しください。
以上、答弁願います。
P.184 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 指定管理者によると、来客用駐車場の管理について福祉会等と協議した結果、1つの住宅において指定管理者による直接管理となり、日常点検や指導などを行っているとのことでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.184 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
私は、当局の駐車場使用料の新設に係る進め方が駐車場管理組合の皆さんの信頼を失い、管理不在の状況になっているのであれば、高い使用料を取るわけですから、全ての駐車場を直営にしてもよいのではないかということは申し上げておきます。
質問の3点目、駐車場管理の課題について相談会で寄せられた事例を申し上げますと、ある市営住宅の駐車場は、白線は入居者、オレンジの線は来客用として毎年きちんと色を塗り替えていたそうですが、指定管理になってからオレンジの線に入居者が指定され、違う車が止まっているなど苦情が来るそうです。しかし、どこに誰の車が指定されているか福祉会には知らされていないので管理ができないとのことでした。
そのことを踏まえて、以下伺います。
まず、管理組合がこれまでしてきた管理が引き継がれていないことへの認識をお示しください。
次に、駐車場の配置が福祉会等に知らされていないことから日常点検ができないということですが、実態はどうかお示しください。
次に、駐車場周辺の管理として草刈りなどの対応をしていただきたいという要望が寄せられているが、見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.184 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 駐車場管理については令和6年4月から市の管理に変更していることから、利用者の要望等に適切に対応してまいりたいと考えております。
駐車場に関する福祉会等への情報提供は、個人情報保護の観点から空き状況などに限定しているところでございます。
駐車場を含む敷地内の草刈りについては、入居者の皆様で御対応いただくこととしております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.184 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
まさに手数料あって管理なしの答弁です。これでどうやって日常的な管理をすることができるのか分かりません。
この質問の最後に、駐車場の適切な管理について当局はどのように考えているのか見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.184 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 駐車場の管理については、指定管理者や福祉会等と連携しながら、引き続き適切な管理に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.184 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
市営住宅の駐車場管理は始まったばかりですが、適切な管理をするために定期的な駐車場管理の方々との意見交換を行うべきということを強く要請し、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
吉野地域のまちづくりについてです。
質問の1点目、中別府一ケ谷線の側溝の溢水に対するこれまでの対応をお示しください。
質問の2点目、今年7月の大雨でさらに下流側で側溝が溢水し、敷地内に浸水した状況についての認識をお示しください。
以上、答弁願います。
P.185 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) お触れの市道においては、これまで梅雨前や台風時期前の職員によるパトロールや地域の方からの情報提供を踏まえ、側溝屈曲部の解消や路面勾配の変更などの局部的な改善を図ってきたところでございます。
令和6年7月の大雨時において家屋への被害はなかったものの、側溝が溢水し民有地へ流入したことを確認しております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.185 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
以前、大雨のたびに側溝から溢水して住宅敷地内に流れ込んでいた事例があり、当局にグレーチングの設置や側溝の改良、溢水した場合の土のうなどを置いて対応していただいた経過がありますが、今回はその下流側で溢水したことから、既存側溝の容量が不足してきているのではないかと考えています。
質問の3点目、吉野東小学校区周辺の宅地開発の件数を過去3年間でお示しください。
質問の4点目、宅地開発に伴う接続先排水路の許可に当たっての要件をお示しください。
以上、答弁願います。
P.185 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) お触れの学校区における開発許可と宅造許可の合計件数を令和3年度から5年度まで順に申し上げますと、3、10、11件でございます。
開発区域内の排水施設は放流先の道路側溝や河川等の排水能力を考慮して有効に排出する能力を持った構造とし、施設計画に当たっては接続先排水路の管理者と協議を行い、同意を得る必要がございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.185 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
その宅地だけを見れば既存側溝への流量は足りているのかもしれませんが、問題は同じ既存側溝にどんどん宅地ができて接続した場合です。
質問の5点目、既存側溝に幾つもの新興団地が接続することで容量が不足するのではないかと考えますが、認識をお示しください。
以上、答弁願います。
P.185 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 宅地開発が行われると雨水の地下への浸透量が減少することから、既存側溝への流出量が増加するものと認識しております。宅地開発における排水施設は都市計画法に基づき、開発区域内の雨水を有効に排水し、その排水によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で設計することが定められていることから、開発許可申請者に対して指導を徹底してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.185 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
開発業者への指導はぜひ行ってほしいと思いますが、その宅地の周辺だけ改善しても、その下流側が溢水するという今回のような事例も考えられることから、地域全体の治水と捉える必要があると思います。
質問の6点目、中別府一ケ谷線をはじめ、吉野東地域の既存側溝の容量の調査と改善が必要ではないかと考えますが、見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.185 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 短時間に既存側溝の流下能力を超えるような強い雨が降った際は側溝の水位が急激に上昇することなどにより一時的に道路冠水があることを確認しており、引き続きどのような対策が可能であるか検討を行っているところでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.186 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
対策を検討していただけるとのことで、前向きな答弁と受け止めます。改めて宅地開発が進む吉野東小学校区全体の治水と捉えて対応してくださるよう強く要請いたします。
以上で、私の個人質疑の全てを終わります。