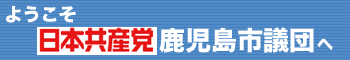P.231 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
初めに、市長の政治姿勢について質問します。
下鶴市長は、引き続き市政のかじ取りを担い、市民のための市政を目指したいと2期目に向けた立候補の決意を表明されました。
そこで、市長にとって市民のための市政とは何かをお聞きします。
市長は、市営住宅入居者の駐車場使用料の約8千万円の負担増や重度心身障害者等医療費助成事業への所得制限の導入による約1億円の負担増を実行に移されましたが、市長が目指す市民のための市政とは市民福祉の後退を前提にした市政なのか、端的にお答えください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.231 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) たてやま清隆議員にお答えいたします。
市営住宅の駐車場管理の見直しについては、国からの通知に基づき、適正な管理をするため行ったものです。
また、重度心身障害者等医療費助成事業の所得制限については、本事業が県の補助事業であることや支給方式の変更や支給対象の追加等に伴い財政的な負担増が見込まれることから、県が示した制度に沿って実施したものです。
いずれも国や県の通知等に基づき、事業の安定的な継続性などを十分踏まえた上で実施が必要と判断したものであり、今後とも市民のための市政を運営するため、新しい時代に対応する持続可能なまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.231 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
持続可能なまちづくりのためには市民の負担増もやむを得ないということでしょうか。市民福祉の後退を前提にした市政は考えていないとなぜ明確に答弁されないのでしょうか。市長が実行に移した市民への大幅な負担増は、市長の1期目のマニフェストにはいずれもなかったものです。にもかかわらず、なぜ実行に移したのか。市営住宅入居者の皆さんや医療費助成から除外された重度心身障害者の方々に対して、市長として説明責任を果たしたと言えるでしょうか。
私ども市議団は、市民の市政をつくる会の皆さんと共に、憲法を市政に生かし、市民による市民のための清潔で公正な市政を目指しています。市長が本人同意もなく自衛隊に18歳の名簿を提供することも福祉予算を削り市民福祉を後退させることも、憲法に照らして市民のための市政とは言えないと考えています。
市長は、2期目に向けたマニフェストを今後検討されるとのことですが、市民に負担増を求めるお考えがあるならば明確に示してください。その上で、市民の審判を求めるべきということを申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
第2回定例会に引き続き、定額減税と調整給付金について、2点質問します。
初めに、補正予算が示されている低所得者支援補足給付金支給事業について、1点目、同事業の補正予算額の内容と専決処分となった理由及び他都市の動向。
2点目、定額減税し切れない調整給付金の現在の支給実績と申請期限までの周知方法、それぞれお示しください。
答弁願います。
P.231 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) お答えいたします。
お触れの事業の補正予算額の内容は、定額減税し切れないと見込まれる方への給付について、国の算定ツールにより給付対象者及び給付額を算出したところ、当初の見込みを上回り予算に不足が生じる見込みとなったことから、給付金と事務費を合わせ9億200万円を計上したものです。また、専決処分については、同給付金の確認書類の送付を行う7月末までに予算措置をする必要があったことから行ったものです。なお、本市を除く九州県都のうち4市で予算に不足が生じており、そのうち専決処分を行ったのは1市です。
調整給付金の給付対象者数、給付額は、令和6年9月10日時点で5万1,025人、23億7,858万円です。また、申請期限までの周知については、引き続き、市民のひろばや市ホームページ、SNS等で行ってまいります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.232 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国の算定ツールで算出したところ、給付の単価も対象者も増加し、当初予算では不足するため今回の補正予算が示されたと理解いたします。既に給付が始まっていますが、現在の到達点は給付額から推定した場合、約50%です。10月末が期限ですので遺漏なき対応を要請します。
次に、定額減税の対象外となる白色、青色申告者の事業専従者への給付について国に動きがあったので、3点質問します。
1点目、本市の令和6年度課税の事業専従者数とその内訳をお示しください。
2点目、事業専従者への給付に関する国の対応とその対象要件をお示しください。
3点目、今後の周知方法とスケジュールをお示しください。
以上、答弁願います。
P.232 ◎答弁 総務局長(遠藤章君)
◎総務局長(遠藤章君) お答えいたします。
お尋ねの事業専従者数については、当初課税において、白色361人、青色2,671人、合計で3,032人でございます。
以上でございます。
P.232 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 定額減税の対象外となる事業専従者への給付は、国によりますと、7年以降に予定されている調整給付に係る不足額給付の対象とするとのことです。また、その対象要件は、本人として定額減税の対象外であること、税制度上、扶養親族等としても定額減税の対象外であること、5年度及び6年度の低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主、世帯員に該当していないことの3つの要件をいずれも満たすものとされているようです。
同給付については、国からの正式な通知が届き次第、速やかに対応する予定で、周知は、市民のひろばや市ホームページ、SNS等で行ってまいります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.232 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
白色の事業専従者の場合、所得税も住民税も課税されませんので不足額給付の対象となりますが、青色の場合、先ほどの要件を満たす必要があることから不足額給付の実際の対象者は減少します。国からまだ詳しい通知が示されていないとのことですが、この給付は本人の申請が必要ですので、一般的な広報だけでなく個別の周知を検討していただくことを要請し、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
本来任意であるにもかかわらず、強制的に取得させられようとしているマイナンバー制度とマイナ保険証について質問します。
初めに、195万8千円の補正予算が計上されているマイナンバーカードの特急発行について、4点質問します。
1点目、直近のマイナンバーカードを所有する市民の数と割合及び国のマイナ保険証の登録率をお示しください。
2点目、特急発行の内容と対象に想定される新生児、紛失を含む再発行、海外からの転入者の数をお示しください。
3点目、特急発行に必要となる機材の配置とセキュリティー体制の確保をお示しください。
以上、答弁願います。
P.232 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) お答えいたします。
令和6年8月末時点の本市のマイナンバーカードの保有枚数は47万9,377枚、保有率は80.6%です。また、デジタル庁によると、7月末時点の全国の保有枚数に対するマイナ保険証の登録率は80%とのことです。
特急発行は、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、地方公共団体情報システム機構が申請者の自宅へマイナンバーカードを直接送付するもので、一、二か月程度を要していた交付までの期間が1週間以内に短縮されます。国が政令で対象としているのは、新生児、紛失等による再交付、海外からの転入者等で、本市における令和5年度のそれぞれの件数は、新生児3,976、再交付1,975、海外からの転入者1,367件です。
特急発行に必要な機材として、国の専用オンライン申請システムへアクセスするためのタブレットや顔写真取り込み用のスキャナーを本庁及び各支所に配置することとしています。また、専用オンライン申請システムは、不正防止の観点から自治体職員のみが取り扱うこととされており、職員ごとに設定するIDとパスワードがなければアクセスできないものとなる予定です。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.233 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
ただいまの答弁で本市の現状を推計すると、約11万5千人の市民がマイナンバーカードを取得していないこと。また、マイナンバーカードを持っていてもマイナ保険証の登録をしていない市民が約9万5千人であることが推計されます。
新生児やマイナンバーカードを紛失した方に申請から1週間以内にマイナンバーカードを届けるための特急発行が12月2日から開始されようとしています。
そこで、質問の4点目、届出が義務づけられている新生児の出生届と任意のマイナンバーカードの申請を一体化することで、カードの申請が義務のような誤解を保護者に与えないか。また、マイナ保険証の手続の一体化も可能かお示しください。
答弁願います。
P.233 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) 新生児について特急発行の対象となってもマイナンバーカードの申請はこれまでどおり任意であり、誤解のないよう案内を行ってまいります。また、マイナ保険証への利用申込みは通常の申請と同様、カード交付とは別の手続となる見込みです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.233 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
マイナンバーカードの普及率が最も低いゼロ歳から4歳の年齢層に着目して、特急発行によってマイナンバーカードの普及率とマイナ保険証の登録率を引き上げることが国の狙いであることは容易に想像することができます。
次に、今定例会に3つの健康保険証に係る条例改正議案が提出されています。
そこで、まず、3点質問します。
1点目、第31号議案の鹿児島市国民健康保険条例の保険税滞納者が被保険者証の返還に応じない場合の過料に係る規定。
2点目、第24号議案の鹿児島県後期高齢者医療広域連合規約の被保険者証及び資格証明書の規定の変更内容。
3点目、第26号議案の鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例の資格確認方法の変更の改正内容。
以上、それぞれの改正内容とその目的をお示しください。
答弁願います。
P.233 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) お触れの改正は、国民健康保険法の一部改正により被保険者証に関する規定が削除されたことに伴い、被保険者証の返還請求に応じない場合等の罰則規定を削除するとともに引用条項の整理を行うものです。
以上でございます。
P.233 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 県後期高齢者医療広域連合規約の変更内容については、令和6年12月2日から現行の被保険者証が廃止され、新たに資格確認書などの交付が開始されることに伴い、被保険者証及び資格証明書という文言を資格確認書等に改めるものです。
また、重度心身障害者等医療費助成条例についても、同じく現行の被保険者証が廃止されることに伴い、資格確認方法について改めるもので、個人番号カードによる電子資格確認や資格確認書などにより被保険者または被扶養者であることを確認する方法に変わります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.234 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
3つの条例改正議案は現行の健康保険証を12月2日から廃止するために必要な改正であると確認しますが、健康保険証を残してと求めている多くの市民の願いに逆行する条例改正であると言わざるを得ません。
次に、条例改正で明記されている資格確認書等の内容とマイナンバーカードやマイナ保険証を所有していない市民が同確認書を無申請で取得できる有効期間について国の方針をお示しください。
答弁願います。
P.234 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 県広域連合によると、同規約の資格確認書等として6年12月2日以降に交付されるのは、資格確認書、資格情報のお知らせ及び特定疾病療養受療証とのことです。また、資格確認書を本人の申請によらず交付する期間は、国から当分の間と示されております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.234 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
資格確認書は12月2日から現行の健康保険証に代わるものとして無申請で交付されますが、国は健康保険証の廃止を大宣伝する一方、資格確認書についてはほとんど報道しません。しかも無申請で交付する期間を当分の間であると曖昧にしています。憲法25条に基づく国民皆保険制度を根底から壊す方針であり問題です。
次に、先ほどの答弁で本市では約38万8千人の市民がマイナ保険証を登録していることが推計されますが、マイナ保険証の利用状況について、3点質問します。
1点目、本市の国保、後期高齢者医療保険のマイナ保険証の4月以降の登録率、利用率の推移とその評価をお示しください。
2点目、市立病院での4月から7月の利用状況と評価、取組内容及び国からの一時金の支給の有無をお示しください。
3点目、市立病院でマイナ保険証を有する患者の健診情報、診療情報を治療に役立てている状況をお示しください。
以上、答弁願います。
P.234 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) 本市国民健康保険におけるマイナ保険証の登録率、利用率は順に、6年4月、67.11、17.45%、5月、67.40、18.44%、6月、67.77、21.53%で利用が進んでいると考えております。
以上でございます。
P.234 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 本市の後期高齢者医療におけるマイナ保険証の登録率、利用率は順に、4月、62.35、10.59、5月、63.12、11.87、6月、63.96、14.45%で利用が進んでいると考えております。
以上でございます。
P.234 ◎答弁 病院事務局長(新穂昌和君)
◎病院事務局長(新穂昌和君) お答えいたします。
当院でのマイナ保険証の利用率を令和6年4月から7月まで順に申し上げますと、10、11、12、14%と増加傾向にあり、マイナ保険証の利用に関する取組としては、ホームページやポスターでの周知、窓口での声かけやチラシの配布などを行っております。なお、国からの一時金については、利用率等の増加量に基づき、当院は40万円が支給されることとなっております。
マイナ保険証を利用することにより、診療の際に健診結果や投薬履歴等の診療情報を確認できることから、過去の経緯を踏まえた治療計画の作成が可能となり、適切な医療の提供につながるものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.234 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国がマイナ保険証の利用率向上のために多額の予算を投入してきているにもかかわらず、国保も後期高齢者医療保険も、また市立病院でも利用率が順調に向上しているとは評価できないのではないでしょうか。市立病院の診療現場でのマイナ保険証の利用状況は具体的な実態が検証されているわけではありません。このような低い利用率の現状に対して新聞社合同によるアンケートが行われています。また、医療団体からもマイナ保険証をめぐるトラブルが発表されていることから、2点質問します。
1点目、8月に実施された地方紙18社のマイナ保険証に関する合同アンケートに見られるマイナ保険証を使わない理由上位4項目と「マイナ保険証導入をやめて」と「選択制にして」の割合をお示しください。
2点目、医療現場でのマイナ保険証をめぐり患者の氏名が正しく表示されない、カードリーダーの接続不良、最新の加入保険情報が反映されていないなどのトラブルが医療団体から発表されていますが、当局の認識と本市の対応をお示しください。
以上、答弁願います。
P.235 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) 新聞報道によると、マイナ保険証を使わない理由は、「従来の健康保険証が使いやすい」、「情報漏えいが不安」、「マイナカードを持ち歩きたくない」、「メリットを感じないため」で、お触れの割合は、「マイナ保険証導入をやめて」が42.0、「選択制にして」が39.8%です。
医療機関等でお触れになった事象が発生していることは承知しております。国においてマイナ保険証の利用時に生じる主な事象、課題への対応を示しており、本市へ問合せ等があった場合は、その対応策の説明や必要に応じて国のコールセンター等を案内しております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.235 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本県の地元紙も参加する合同アンケートであり、全国で1万2,007人が回答していますが、健康保険証を残してと約8割の方が回答しています。また、同アンケートではマイナ保険証を利用している方の47.8%が選択制を支持し、マイナ保険証への一本化を支持する人は全体の2割程度であったと報じています。当局も認識されているように医療機関でのトラブルは今なお続いており、その対応に追われているにもかかわらず、国はマイナ保険証の利用率が低い医療機関に対して、療養担当規則違反として指導することを検討していることが明らかになっており極めて問題です。
そこで、この質問の最後に、市長に伺います。
国がマイナ保険証の普及を強引に進め、健康保険証の存続を求める国民世論を全く省みない中で、林 芳正官房長官が健康保険証の廃止の延期を表明するなど、政府内部からも異論が出されました。市長も市民の不安に応えて、国に対して健康保険証の廃止の延期を提言するお考えはないか。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.235 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 健康保険証の廃止については、制度の安全性や信頼性の確保に向け、国民に対し十分な説明や情報提供を行うよう全国市長会等を通じて要望しており、国においては、住民や医療機関等の理解が得られるよう引き続き適切に対応していただきたいと考えております。本市におきましても、市民の皆様からの問合せ等については、不安解消につながるよう関係課において丁寧な対応と適切な周知・広報に努めてまいります。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.235 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
共同通信が7月、市区町村長を対象に実施したアンケートでは、4割超の首長が延期を求めていると報じています。下鶴市長には国に延期を求める考えはないということは分かりましたが、マイナンバー制度は市長が推進する行政のデジタル化の基盤となる制度です。しかし、マイナ保険証に見られる国の強引な手法は、行政のデジタル化への不信や不安の増加につながるということを厳しく指摘をし、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
平成30年度から県が国保財政の責任主体となる国保の都道府県単位化がスタートしましたが、令和6年度から保険料水準の統一という新たな段階を迎える国保行政について、以下質問します。
初めに、厚生労働省保険料水準統一加速化プランについて、まず、保険料水準の統一の意義と定義をお示しください。
答弁願います。
P.235 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) お触れのプランによる保険料統一の意義は、高額な医療費の発生等による年度間の保険料の変動を抑制できることや、都道府県内のどの市町村でも同じ保険給付を同じ保険料負担で受けられることで被保険者の公平性が確保できることとされており、定義は、国保事業費納付金に各市町村の医療費水準を反映させない納付金ベースの統一と同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険料とする完全統一とされています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.236 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
医療費の変動を市町村単位ではなく県単位で医療費水準の平準化を図り、保険料水準の統一を図ることが保険料の変動をより抑制し国保財政の安定化を図る意義があると理解いたしましたが、そのための手法として、国保事業費納付金ベースの統一と完全統一の2段階があると答弁されました。しかし、そもそも国保の県単位化以前は、医療費の変動は国全体で平準化が図られていました。しかし、医療費削減の役割を都道府県に直接担わせるために、国保の県単位化が導入されたということは指摘をしておきます。
次に、保険料水準の統一に向けた全国と本県の動向について、3点質問します。
1点目、令和6年度から完全統一した都道府県。
2点目、6年度から納付金ベースの統一をした都道府県。
3点目、本県の方針。
以上、それぞれお示しください。
答弁願います。
P.236 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) 令和6年度からの完全統一は大阪府と奈良県で、納付金ベースの統一は北海道や群馬県などです。
第3期鹿児島県国民健康保険運営方針においては、早ければ15年度の納付金ベースの統一を目標とし、最終的には完全統一を目指すとされています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.236 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
既に多くの道府県が納付金ベースの統一、あるいは完全統一を開始しており、本県も完全統一を目指していることが示されました。
では、完全統一した自治体の保険料水準はどうなっているのでしょうか。
そこで、6年度から保険料水準の完全統一を開始した大阪府について質問します。
質問の1点目、6年度の大阪府と本市の保険料率の比較をお示しください。
質問の2点目、4年度決算の1人当たり医療費の大阪府、鹿児島県、鹿児島市の比較をお示しください。
答弁願います。
P.236 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) 6年度の大阪府の保険料率と本市の保険税率は、所得割率、均等割額、平等割額の順に、医療分、9.56%、8.00%、3万5,040円、2万1千円、3万4,803円、2万3,300円、後期高齢者支援金等分、3.12%、2.60%、1万1,167円、6,200円、1万1,091円、7,100円、介護納付金分、2.64%、2.40%、1万9,389円、7,400円、ゼロ円、6,400円です。
4年度の1人当たり医療費は、大阪府41万3,012円、鹿児島県48万9,985円、本市49万8,595円です。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.236 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
大阪府の1人当たり医療費は本県と本市より約8万円も少ないにもかかわらず、33市9町1村で構成される大阪府の保険料率と本市を比較すると、所得割、均等割、平等割が本市の保険料率を大幅に上回っていることが明らかになりました。
では、国保税で比較するとどうなるのか。
質問の3点目、大阪府と本市の6年度の国保税のモデルケース世帯として、夫45歳、給与所得200万円、妻42歳、所得なし、子供2人、小学生、中学生の4人世帯の場合と、年金所得100万円の70歳夫婦2人世帯の場合のそれぞれの国保税の比較をお示しください。
答弁願います。
P.236 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) お触れの給与所得200万円で40歳代夫婦、子2人の世帯で試算しますと、大阪府45万6,120円、本市33万2,300円です。
また、年金所得100万円で70歳夫婦の場合は、大阪府14万1,428円、本市10万2,700円です。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.237 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
いずれのモデルケースも大阪府は本市の37%増の国保税です。なぜこのような重い負担となっているのか。
そこで、質問の4点目、大阪府の保険料水準の完全統一に伴う市町村国保への影響について、4点質問します。
1点目、市町村の保健事業費用を国保事業費納付金への算入の有無をお示しください。
2点目、市町村独自の国保の減免制度の継続の有無をお示しください。
3点目、法定外一般会計繰入金の活用の是非をお示しください。
4点目、保険料を引き下げるために市町村の基金を繰り出すことの是非をお示しください。
以上、答弁願います。
P.237 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) 大阪府などによると、市町村の保健事業費は一部を除いて国保事業費納付金に算入し、市町村独自の減免制度は5年度で終了、法定外一般会計繰入金や市町村の基金は保険料の引下げに活用できないとのことです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.237 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
もともと大阪府の市町村の中には独自の優れた国保税の減免制度がありましたが、5年度で終了、つまり、全て廃止されており、保険料の上昇を抑制するための法定外一般会計繰入金の活用も認められなくなりました。また、市町村が独自にため込んだ基金についても保険料を引き下げるために活用することを大阪府は認めていません。したがって、市町村が府に収める国保事業費納付金を丸ごと保険料だけで納めさせる、これが大阪府の保険料の完全統一の実態にほかなりません。
そこで、質問の5点目、完全統一を目指す本県の国保運営方針は、技術的助言であり、市町村の自主性や自立性が尊重されるべきと考えますが、本県は大阪府のような負担増となる完全統一の国保を目指しているのか。
答弁願います。
P.237 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) 本県においては、現在、保険料水準統一に向けた課題整理を行っており、市町村独自の保健事業や減免の取扱い等は今後、県と市町村で協議していくことになっております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.237 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
課題について今検討を進めているということですが、本県も大阪府のような完全統一をゴールにしていることを否定はされませんでした。
次に、第3期鹿児島県国民健康保険運営方針と本市の今後の方針について質問します。
質問の1点目、県の計画的・段階的に解消を図る解消・削減すべき赤字の内容と本市の方針をお示しください。
質問の2点目、6年度の本市国保の決算補填等目的の法定外一般会計繰入金を国保世帯数で除した額をお示しください。
以上、答弁願います。
P.237 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) 県の運営方針における解消・削減すべき赤字は、決算補填等目的の法定外一般会計繰入額と繰上充用金の新規増加額の合計額とされており、本市としては県の方針も踏まえ、赤字の計画的・段階的な解消・削減を目指してまいります。
本市の6年度当初予算における決算補填等目的の法定外一般会計繰入金22億5,975万9千円を国保世帯数6万9,818世帯で割ると3万2,366円となります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.237 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本市は、県から赤字の解消・削減を求められており、とりわけその対象となる法定外一般会計繰入金を全額解消した場合、1世帯平均3万2,366円の負担増に相当することが明らかにされました。
次に、質問の3点目、県がため込んでいる県国保の財政安定化基金、財政調整事業分について、2点質問します。
1点目、6年度からの同基金の県の活用方針及び6年度当初予算に向けた同基金の活用内容をお示しください。
2点目、本市は国保事業費納付金の上昇を抑制するために同基金の活用を県にどのように求めていくのか見解をお示しください。
答弁願います。
P.238 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) お触れの基金について、6年度からは原則、県平均の1人当たり国保事業費納付金額の対前年度伸び率が10%以上の場合や基金残高が積立て目標額の44億円を上回る場合に活用することとなっており、6年度においては、同納付金の抑制に5億3千万円、予備費分として3億円の活用が見込まれています。
同基金の活用方針は、5年11月の県国保運営連携会議で決定したところですが、国保事業費納付金を抑制いただくよう、引き続き関係会議において要望してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.238 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
政務調査課を通じた調査では、県には市町村が活用可能な同基金が47億8千万円あることが確認されています。来年度予算編成に向けて今年も県内の他自治体と連携して、県当局に基金の活用を強く要請してください。
この質問の項の最後に、市長に伺います。
これまでの質疑で明らかなように、今後、国保の保険料水準の統一による市民の大幅な負担増が危惧されます。市長は、国保の負担増を回避するための方策をマニフェストに掲げるお考えはないのか見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.238 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 国民健康保険制度は、国民皆保険を根幹から支え、地域住民の健康の保持・増進や高度な保健医療を提供できる社会の重要な基盤としての役割を果たしてきておりますが、被保険者の減少や医療費の増大など構造的な課題を抱えており、本市国保においても非常に厳しい財政状況が続いております。このような中、国や県において平成30年度に開始した都道府県単位化の趣旨の深化を図るため、保険料水準の統一や赤字解消に向けた取組が強化されております。
私としましては、国や県の方針も踏まえながら本市国保を安定的に運営できるよう、引き続き、医療費適正化対策としての特定健診受診者へのインセンティブ付与や収納率向上対策等を進めてまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.238 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
ただいまの答弁では、医療費適正化、収納率の向上に努めた結果、医療費削減の目標に到達できなかった場合、負担増もあり得るとも受け取れます。保険料水準の統一のために市町村にだけ負担を負わせるのではなく、市長も述べられたように、国保にはそもそも構造的問題を抱えているわけですから、国や県に財政負担を求めていく運動を市長会ぐるみで取り組むことも国保の負担増を回避する一つの方策であるということを申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
第2回定例会に引き続き、生活保護の障害者加算について質問します。
初めに、第2回定例会の質疑で明らかにした本年5月末で加算されていない354人の内訳と直近の処理状況について、5点質問します。
1点目、障害者手帳の障害種別の人数。
2点目、その後、加算が適用された人数とそのうち障害者手帳を提出した申請の翌月に遡及して加算された人数。
3点目、加算の対象外となった障害者手帳の障害種別の人数とその理由。
4点目、5月末で申請から8か月経過していた被保護者の加算適用の有無。
5点目、加算が適用されていない残りの人数と障害者手帳の障害種別。
以上、それぞれお示しください。
答弁願います。
P.239 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 令和6年5月末で障害者加算の認定をされていなかった354人について、所持する障害者手帳の種別ごとに人数を申し上げますと、身体障害者手帳ゼロ人、精神障害者保健福祉手帳340人、療育手帳14人です。
その後の加算の認定者数は9月10日時点で53人で、そのうち、障害者手帳が提出された翌月に遡及して加算された方はおりませんでした。
また、同時点で加算の対象外となっている人数を手帳の種別ごとに申し上げますと、身体障害者手帳ゼロ人、精神障害者保健福祉手帳94人、療育手帳14人で、対象外となっている理由は、障害の程度が加算の判定に必要な障害基礎年金の支給要件に該当していないことや初診日から1年6か月を経過していないことなどです。
5月末で8か月経過していた1名の加算については同時点で認定されていないところです。
また、まだ加算が認定されていない方は193人で、全て精神障害者保健福祉手帳の所持者です。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.239 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
5月末で申請から8か月経過していた方は既に1年2か月経過する現在も加算が適用されておらず、いまだ193人の方に障害者加算が適用されていません。しかも全員が精神障害者保健福祉手帳を所持する方であります。なぜなのか。
そこで、質問の2点目、精神障害者保健福祉手帳の所持者の加算が遅れている原因を身体障害者手帳との比較でお示しください。
答弁願います。
P.239 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 障害者加算に係る障害の程度の判定は、身体障害者手帳の所持者の場合、その手帳の等級により加算が適用されますが、精神障害者保健福祉手帳の場合、障害基礎年金の受給権の有無を確認する必要があり、受給権を有する場合は、さらに障害基礎年金の手続が必要になることなどから加算の認定に時間を要しているところです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.239 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
身体障害者の場合と異なり精神障害者の場合、障害基礎年金の受給権の有無を確認することに時間を要することが原因であると述べられました。
そこで、質問の3点目、加算の処理を進めるための今後の対策について見解をお示しください。
答弁願います。
P.239 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 加算の認定を速やかに進めるには、障害基礎年金の受給権の確認や受給手続の際の適切な助言や情報提供が必要と考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.239 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
障害者加算の遡及をめぐる県への審査請求では、被保護者に対して障害基礎年金の受給権の確認や受給手続の際の適切な助言や情報提供は行われず、長期に放置されていたことが問題になりましたが、そのような対応が加算適用を遅らせている原因か否か検証が必要ではないでしょうか。しかし、先ほど答弁で示された加算の適用が処理された53名の方々は全員手帳を提出した申請の翌月に加算が遡及されていません。なぜなのか。
そこで、質問の4点目、精神障害者保健福祉手帳2級以上の等級を所持する被保護者が障害基礎年金の受給権の有無を確立した場合、障害者手帳を提出した申請の翌月に加算が遡及されない理由とその根拠をお示しください。
答弁願います。
P.239 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 障害者加算の認定については、精神障害者保健福祉手帳所持者の場合、国の通知により、障害基礎年金の受給手続を行ったこと、もしくは受給権を有しないことが確認できた翌月から加算を行うこととされていることから、申請時に手帳の提示はあってもこれらの要件が確認できない場合は、申請の翌月には遡及されないものです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.240 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国の通知により遡及できないとのことですが、本市では県への審査請求によって申請の翌月に遡及して加算が適用された事例があります。身体障害者手帳所持者と同様に申請の翌月に遡及して加算が適用されるように国に要請すべきと考えますが、答弁願います。
P.240 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 障害者加算の認定に当たっては、身体障害者手帳と同様に精神障害者保健福祉手帳についても認定資料として使用できるよう全国市長会を通じて国に要望しているところです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.240 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
全国市長会を通じて国に要望しているとのことですが、障害者加算は生活保護費の一部です。精神障害1級の場合、月額2万4,940円、同2級の場合、月額1万6,620円の加算が長期にわたって適用されていないことは問題です。残された193人の加算適用が早急に処理されるよう強く要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
病児・病後児保育事業について質問します。
初めに、本市の病児・病後児保育事業の現状と推移について、4点質問します。
1点目、同事業の目的と施設数及び利用定員総数、1施設当たり年間開園日数をお示しください。
2点目、同事業の職員配置基準及び定員上必要な職員総数をお示しください。
3点目、過去5年間の委託料及び延べ利用人数の推移と評価をお示しください。
4点目、キャンセルの状況とその評価をお示しください。
以上、答弁願います。
P.240 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) お答えいたします。
本市の病児・病後児保育事業は、児童が病気の回復期に至らない場合で、当面の症状の急変が認められない場合等において、病院等に付設された専用スペースで一時的に児童を預かることにより、保護者の子育てと就労等を支援することを目的としております。令和6年度の施設数は8施設で利用定員総数は52人、5年度の1施設当たりの年間開所日数の平均は約270日でございます。
職員配置基準につきましては、看護師等が利用児童おおむね10人につき1人以上、保育士はおおむね3人につき1人以上配置する必要がございます。52人の利用がある場合の必要な職員数は、看護師等9人、保育士20人となります。
過去5年間の委託料及び延べ利用人数を順次申し上げますと、令和元年度、1億5,299万9,140円、9,419人、2年度、1億5,751万5千円、6,041人、3年度、1億4,315万5千円、7,155人、4年度、1億3,674万5千円、6,657人、5年度、1億5,931万2,800円、9,892人でございます。2年度から4年度は新型コロナウイルス感染症等により減少しておりますが、5年度は元年度を上回っており、コロナ禍前の利用状況に戻っているものと考えております。
5年度の当日キャンセル加算におけるキャンセル回数は406回となっており、利用を予定していた児童の症状が改善したこと等により一定程度のキャンセルが生じているものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.240 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本市の病児・病後児保育は医療機関併設型であり、開園日数と52人の利用定員総数から試算すると、年間最大1万4,040人の利用が可能となります。延べ利用人数はコロナ禍前に回復しているようですが、委託料は利用児童1人当たりで算定するとコロナ禍前の1万6千円台に減少しているようです。予約キャンセルについては施設経営の影響の検証が必要と考えます。
次に、令和4年から導入されている病児・病後児保育受付システムの「あずかるこちゃん」の登録者数と利用状況及びその評価をお示しください。
答弁願います。
P.241 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 「あずかるこちゃん」の登録者数は6年7月末時点で9,722人で、同月は1,479件の予約がございました。利用者からは、「施設の空き状況がオンライン上で分かって予約しやすい」、施設からは、「電話対応などの事務負担が減少した」などの意見がございました。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.241 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
施設の空き状況がすぐ分かる点や予約受付の事務負担の軽減など、利用者、施設側の双方から評価されていることが分かりました。
次に、認可外保育施設等における病児・病後児保育事業の施設数、利用定員総数と利用状況の現状とその評価をお示しください。
答弁願います。
P.241 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 病児・病後児保育事業を実施している認可外保育施設数及び利用定員総数は、70施設、137人となっております。利用状況は本市への報告事項となっていないことから把握しておりませんが、同事業は各施設の利用者等の子育てと就労等との両立に役立つものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.241 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
認可外保育施設も病児・病後児保育の受皿としての役割を果たしていることを確認します。
ただいま本市の病児・病後児保育の現状について質問しましたが、当局は同事業を持続可能なものにしていくためにどのような課題認識をお持ちでしょうか。全国で1千以上の施設が加盟する一般社団法人全国病児保育協議会は5つの要望を国に要請しています。
1点目、感染症の流行状況等の影響を受け、キャンセル率の高い事業であり、厳しい経営となっていることから、現在の利用児童数によって左右される運営費ではなく定員に基づく交付の要望。
2点目、保育士の処遇改善は病児保育室の保育士、看護師にも適用することの要望。
3点目、子供が幼児教育の無償化対象である場合、その交付金をもって病児保育の無償化を求める要望。
4点目、現行の定員では罹患病児の安全安心の病児保育が行えない状況であり保育士の定員増を求める要望。
5点目、子供を取り巻く病的な状態、環境全てを適用範囲として位置づけ、病児保育の拡大を求める要望。
それぞれの要望について、本市での課題認識と見解をお示しください。
答弁願います。
P.241 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) お触れになった要望書の運営費に関し、定員に基づき助成してほしいとの要望につきましては、経営の安定化のために要望されたものと考えており、国において利用児童数の影響を受けない基本分単価の増額や当日キャンセル対応加算の導入など制度の改善が行われているものと考えております。
保育士の処遇改善の要望につきましては、保育所等の委託費、施設型給付費での対応を踏まえ要望されたものと考えており、国において運営費助成の増額など制度の改善が行われているものと考えております。
無償化の要望につきましては、利用者負担の軽減の観点から要望されたものと考えております。国においては、利用者負担を減らす取組として、市町村民税非課税世帯、生活保護世帯への減免分を助成する制度を設けられているものと考えております。
保育士の配置基準の要望につきましては、国において検討されるものと考えております。
利用要件に関する要望につきましては、病児保育の対象とすべき子供の置かれた状態は、身体的疾患に限らず多様であるとの認識の下要望されたものと考えておりますが、事業の枠組みに関することであり、国において検討されるものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.242 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国において改善あるいは検討されるものだとして市当局としての課題認識は示されませんでしたが、これらの要望事項は同協議会が全国調査を行い、その上で国に要望しています。キャンセル対応加算の導入も同協議会の要望活動が反映しているわけです。また、同協議会は病児保育の専門性を高めるために病児保育専門士の養成にも取り組んでいますが、年々保育士等の人材確保が困難になってきており、その原因の1つは、慢性的な赤字経営のため保育士等の処遇改善に進まないという課題であります。
そこで、この質問の項の最後に、市長に伺います。
病児・病後児保育に従事する保育士等を市独自に支援する方策をマニフェストに掲げるお考えはないか見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.242 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 私は、少子化人口減少時代に対応する中、特に子育て中の世帯や若い世代に選ばれるまちの実現を目指し、これまで子育て支援の充実に重点的に取り組んでまいりました。
このような中、病児・病後児保育事業につきましては、子供が病気の際に保護者が仕事などにより自宅での保育が困難な場合に安心して預けることができる環境を整えることを目指して実施しているところでございます。このため本市では、これまでも国の動向を踏まえ、運営費の基本分単価の増額や当日キャンセル対応加算を導入したほか、保護者の利便性向上のため「あずかるこちゃん」を導入するなど円滑な事業運営に努めてきたところでございます。
今後におきましても、国の動向や保護者、施設のニーズを踏まえ、施設の安定的な運営とともに、保護者の子育てと就労等との両立の支援に資するよう取組を進めてまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.242 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
利用児童の有無にかかわらず、常に保育士を配置しなければならないのが病児・病後児保育です。国任せではなくて市独自の支援策を検討していただくことを要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
在宅介護を支えている訪問介護事業について質問します。
初めに、令和6年度介護報酬改定について、2点質問します。
1点目、全体の改定率と訪問介護の基本報酬の改定内容とその理由をお示しください。
2点目、国の介護報酬改定に対する全国ホームヘルパー協議会と日本ホームヘルパー協会の連名の抗議文の内容をお示しください。
以上、答弁願います。
P.242 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 全体の介護報酬改定率はプラス1.59%で、うち訪問介護の基本報酬は1回当たりの単位数は所要時間ごとに2から3%引き下げられております。改定の理由として国は、令和5年度の介護事業経営実態調査において訪問介護の収支差率が全サービスの平均を上回っていたことなどを挙げているようです。
お触れの抗議文は、人材不足や物価高騰等により閉鎖や倒産する訪問介護事業所が増加する中、6年度介護報酬改定において他のサービスの基本報酬は引き上げられ、訪問介護系サービスのみが引き下げられたことは、さらなる人材不足を招くことが明らかで断じて許されないと強く抗議する内容となっております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.242 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
収支差率がよいのは移動距離が短く多数回訪問できるサ高住などのタイプの事業所ですが、雨や炎天下の中でも一件一件地域を回る事業所の4割が赤字である実態を国は無視し、基本報酬のマイナス改定を強行したことに対してヘルパー団体の皆さんが抗議を表明したことは当然であります。
次に、訪問介護事業の新規・休業・廃止の状況について、2点質問します。
1点目、東京商工リサーチ老人福祉・介護事業の2024年1月から6月の上半期の倒産状況の内容と特徴をお示しください。
2点目、本市の訪問介護事業の平成31年4月から令和6年4月の事業所数、新規・休業・廃止の推移と介護現場の人手不足の課題認識をお示しください。
以上、答弁願います。
P.243 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) お触れの調査によりますと、2024年上半期の全国の倒産件数は81件で、業種別では、訪問介護40、通所・短期入所25、有料老人ホーム9件で、いずれも介護保険法が施行された2000年以降の上半期最多となっております。特徴としては、売上げ不振が倒産の主な要因で、従業員10人未満の小零細規模の事業者が多いことが挙げられます。
お尋ねの実績について令和元年度から6年度まで順に申し上げますと、本市の訪問介護の事業所数は、4月1日時点で、144、146、147、146、154、151か所、新規指定は、10、10、6、12、14、6年度は4月末現在で3件、同様に休止は、1、1、4、3、9、1件、廃止は、6、9、6、8、19、ゼロ件となっております。廃止理由として、人材確保が困難で職員の配置が難しいことが多く挙げられていることから、介護人材の確保や育成が課題であると考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.243 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
2000年の介護保険法の施行後、全国の介護事業者の倒産は過去最多となっています。本市においても過去6年間で新規の事業所数を休業と廃止が上回る傾向が見られ、人材確保が困難との課題認識が示されました。
次に、6年度から8年度までの第9期鹿児島市高齢者保健福祉・介護保険事業計画と介護人材の確保について、2点質問します。
1点目、訪問介護サービス見込み量の積算根拠と全体及び訪問介護に必要な人材確保の見込みをお示しください。
2点目、本市独自の介護人材の確保の支援策の必要性についての見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.243 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 第9期鹿児島市高齢者保健福祉・介護保険事業計画における訪問介護サービスの見込み量は、5年度の利用実績を基礎として、要支援・要介護認定者数の推計や過去3年間の実績から見込んだ伸び率等を考慮した利用者数と利用回数を乗じて算出しております。介護サービス全体の提供に必要となる介護職員については、県の第9期計画において最終年である令和8年には、県全体で3万5,820人で2,572人が不足すると見込まれておりますが、訪問介護サービスを含めサービス種別ごとの人数については示されていないところです。
介護人材の不足が見込まれる中、本市においては、利用者が安心して質の高い介護サービスを受けられるようにするため、介護人材の確保を支援するための取組が必要であると考えており、第9期計画においては、新規就労につながる取組や職場環境改善に向けた取組のほか、介護職場の魅力発信などを今後の方策に掲げ、6年度は本市独自に介護職場の魅力を紹介するリーフレットの作成や関係団体と連携した合同就職説明会の開催に向けて取り組んでいるところです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.243 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
第9期の訪問介護サービス見込み量は、あくまでも実績に基づく需要予測であり、介護職員の必要数の裏づけがありません。また、県全体のデータのみで本市の介護職員の必要量や不足数が示されていないことは課題です。県に対して情報開示を求めるべきです。鹿児島市の介護職員がどのように不足していくのか、県にしっかりと情報開示を求めて鹿児島市の明らかな具体的な不足数を明確にすべきではないでしょうか。
今年の合同就職説明会の成功を期待しますが、若い世代が介護現場にいかに定着できるかが大きな課題であります。
そこで、市長に伺います。
深刻な介護現場の人手不足を打開するための市独自の方策をマニフェストに掲げるお考えはないのか。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.244 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 私としましては、人生100年時代を見据え、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けることができるよう、引き続き、介護人材の確保や育成、介護職場の魅力発信などを行い、将来にわたって安定的な介護サービスを提供できる体制を確保してまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.244 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
明確な方策は示されませんでしたが、市長の世代でもある団塊ジュニア世代が65歳を迎える2040年問題は、現在よりも深刻な事態が予測され、待ったなしの課題であります。介護職員の確保を市政運営の重点課題に位置づけることを強く求めて、私の個人質疑の全てを終わります。