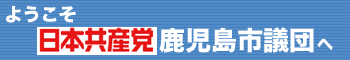P.57 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
初めに、市長の政治姿勢について、2点質問します。
質問の1点目、下鶴市長は、人口減少を乗り越え、選ばれるまちづくりを進めると、11月12日、111項目のマニフェストを発表され、2期目の当選を果たされました。今回の市長選挙は、私どもも参加する市民の市政をつくる会の桂田美智子候補との一騎打ちの選挙戦となりました。
桂田美智子候補は、お金ではなく、市民の声で動く清潔で公正な市政をと、300億円もかかるサッカースタジアム建設よりも物価高で苦しむ市民の暮らしを支える、人に優しい「あったか市政」を実現するためにマニフェスト50を11月2日に発表して支持を広げましたが、市長はこの訴えをどのように受け止め、評価されていますか。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.57 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) たてやま清隆議員にお答えいたします。
お触れの候補者におかれては、マニフェストにおいて自らの政治信条や考えに基づき主張を展開されたものと考えており、その評価は、今回の選挙において有権者の方々が各候補者のマニフェストを比較検討の上、判断された結果であると考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.57 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
大変そっけない答弁で残念です。下鶴市長に敗れたとはいえ、桂田美智子候補には2万1,278人の市民が1票を投じているわけです。この市民の方々がどういう思いで投票したのか、その思いに寄せていただきたいわけです。桂田美智子候補は、現市政で見過ごされている課題に光を当て、一人一人の市民の暮らしに寄り添う「あったか市政」が今こそ必要だと訴えました。下鶴市長が今掲げている選ばれるまちづくりと決して対立するものではなくて、「あったか市政」は選ばれるまちづくりにもつながると思いますので、今後の市政運営に生かしていただくことを強く要望いたします。
次に、今回の市長選挙は過去3番目に低い投票率であったと報道されていますが、投票率の評価に関する下鶴市長のコメントの真意について伺います。
質問の2点目、市長選挙後、地元放送局、「再選の下鶴氏に聞く」、の中で、7割が棄権する中で訴えは有権者に届いたとお思いですかの問いに対して、下鶴市長は、この投票率に関しましては、これまでも現職と共産党推薦の候補の方との一騎打ちの場合、非常に投票率が低くなる傾向がありましたのでと発言されました。投票率の評価は立候補した者同士が共同に責任を持つべきと考えることから、この市長の発言は公党に対する大変失礼な発言だと受け止めました。ぜひこの発言は撤回をしていただけませんでしょうか。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.58 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) お触れの発言は、これまでの市長選における傾向として、前回の投票率が38.16%であったことに対し、今回と同様の構図であった平成28年は25%、20年は25.47%であるなど、過去の経緯に基づき事実を申し上げたところであり、私としてはこの事実を踏まえた上で、投票率の向上に向けて市長選の重要性や今回の選挙への参加などを強く訴えてきたことをお伝えしたものでございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.58 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 再質問します。
事実だと繰り返されましたが、単なる結果の説明と私ども共産党が推薦しているから非常に投票率が低くなることを事実だと評価することとは別問題です。今回の投票率について市長は評価を加えているわけです。このコメントを聞いて私どもは大変不快な思いをいたしました。ぜひ撤回していただけませんでしょうか。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.58 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 先ほども申し上げましたとおり、お触れの発言は、これまでの市長選における傾向として過去の経緯に基づき事実を申し上げたところであり、私としては、この事実を踏まえた上で、投票率の向上に向けて市長選の重要性や今回の選挙への参加などを強く訴えてきたことをお伝えしたものでございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.58 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
私どもがなぜ不快に思ったのか、市長はやはり御理解ができないようです。私は前回4人立候補した市長選挙の38.16%も決して高い投票率だったとは思いませんが、なぜ今回7割の市民が投票しないで棄権をしたのか。桂田美智子候補も立候補表明が大変遅かった、政策を広げることができなかったと振り返っています。投票率の原因を対立候補に求めるのではなくて、市長御自身はどうであったのか、真摯に振り返っていただくことを強く要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
第3回定例議会で明らかになった下鶴市長の政治資金パーティーについて、以下質問します。
このパネルを御覧ください。
令和5年分の政治資金収支報告書を基に、下鶴市長に関係する3つの政治団体、下鶴隆央後援会、資金管理団体の下鶴隆央と未来をつくる会、そして、令和5年、下鶴市長の政治資金パーティーを8回開催し、昨年の12月20日、下鶴隆央後援会に450万円を寄附している鹿児島みらいネットの関係を表したパネルです。なお、下鶴隆央後援会の代表者と鹿児島みらいネットの会計責任者は同一人物ですね。
そこで、政治団体鹿児島みらいネットの政治資金パーティーについて質問します。
質問の1点目、同団体は、市長の政治資金パーティーを開催することを目的にした団体なのかお示しください。
質問の2点目、同団体は、市政報告会の名称で開催していますが、開催に当たり、下鶴市長の政治資金パーティーですと告知しているのかお示しください。
以上、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.58 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) お触れの政治団体は、鹿児島の未来をつくる政治家として、私、下鶴隆央の活動を支援することを目的に設立されたものであり、政治資金パーティーを開催することのみを目的としたものではありません。
また、お触れの告知につきましては、関係法令に基づき告知しております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.59 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
同団体は下鶴市長を支援する団体だと明確に答えられました。政治資金パーティーを開催するための団体ではないとおっしゃいましたが、この団体の政治資金収支報告書を見ますと、下鶴市長の政治資金パーティー以外の活動をしている形跡が全く見られません。参加者は下鶴市長の市政報告会だと認識して出席していることが分かりました。
そこで、次に、質問の3点目、下鶴市長は昨年12月に2回政治資金パーティーを開いていますが、昨年12月6日、岸田首相が政治資金パーティーの開催の自粛を表明し、当時は政治資金パーティーに対する国民の厳しい目が向けられた時期です。12月14日、下鶴市長はそんなときになぜ8回目の政治資金パーティーを開いたのですか、見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.59 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 政治資金パーティーにつきましては、政治資金規正法に基づき適正に開催したものでございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.59 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
適正に開催したので問題はないと、こういう見解が示されました。
当時、政治資金パーティーに対して多くの国民は厳しい目を向けていたわけです。そういう厳しい県民や市民、国民の世論を市長自身全く感じ取っていなかったのでしょうか。その感覚そのものが私は疑問に思うわけです。開催に当たり、ちゅうちょもされなかったのでしょうか。その上で、この8回目の政治資金パーティーが開かれたということを確認いたします。
質問の4点目、8回開催されていますが、令和5年のパーティー券の1人分の価格とパーティー券の購入者数及び出席者人数をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.59 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 政治資金パーティーに係る記載事項は収支報告書にあるとおりでございます。なお、お触れの点については記載すべき事項とはなっていないところでございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.59 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
記載する事項とはなっていない、だからお聞きしたわけです。収支報告書を見て記載されていないからお聞きしているわけです。年間で20万円を超えるパーティー券を購入した人しか公表されない。この政治資金パーティーの仕組みそのものが国民の批判を受けたわけです。20万円以下なら購入者を記載する必要はなく、購入の実態が可視化されないことがそもそもこの政治資金パーティーの問題なんです。そういう制度を利用して下鶴市長は政治資金を集めたわけです。それが政治倫理上、市民の疑いが向けられないのかということを私は危惧しているわけです。
では、質問の5点目、下鶴市長の政治資金パーティー券を企業・団体は購入しているのか、公表して可視化すべきと考えますが、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.59 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 政治資金パーティーについては、20万円を超えるものは支払者の氏名等を収支報告書に記載することになっており適正に処理しております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.59 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 再質問します。
再度お聞きます。企業・団体は下鶴市長の政治資金パーティー券を購入しているのかしていないのか答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.59 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 先ほど申し上げましたとおり、政治資金パーティーについては、20万円を超えるものは支払者の氏名等を収支報告書に記載することになっており適正に処理しております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.60 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
20万円を超えたものしか公表の義務はない、それ以下は公表されない、そして、企業・団体は購入したのかしなかったのかお答えはされなかった、否定はされなかったということを確認しておきたいと思います。私は、購入者が個人であっても、市の公共事業を請け負っている事業者の場合、政治倫理上、市民から疑念を抱かれることになるわけです。
引き続き質問します。
質問の6点目、同団体からの450万円寄附は、今回の選挙活動の資金として活用されているのかお示しください。
質問の7点目、令和6年の下鶴市長の政治資金パーティー開催と収支の状況をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.60 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 選挙費用については、公職選挙法に基づき、選挙運動費用収支報告書を提出することとなっております。
また、政治資金パーティーは令和6年に9回開催しておりますが、収支の状況については、令和6年の収支報告書で公表されることとなっております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.60 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 再質問します。
この450万円の寄附は、今回の市長選挙の活動の資金として使われたということは否定はされないんですね。
答弁してください。
そして、この9回の政治資金パーティー、この会計責任者は下鶴隆央後援会の代表者です。把握していらっしゃると思います。なぜこれを今、公表できないんでしょうか。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.60 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 選挙費用については、公職選挙法に基づき、選挙運動費用収支報告書を提出することとなっております。
また、政治資金パーティーは令和6年に9回開催しておりますが、収支の状況については、令和6年の収支報告書で公表されることとなっております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.60 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
令和6年の政治資金パーティーの収支は、来年の11月30日以降しか市民は把握できないわけです。公表されないわけです。しかもこの令和6年の政治資金パーティーの資金の一部は今回の選挙活動にも使われているわけです。だからこそ市民は市長の政治資金に対する透明性を求めているわけです。そのことを御理解いただきたいと思います。
先ほどの答弁でも、企業・団体から政治資金パーティーは購入されているのかしていないのか否定はされませんでした。
そこで、質問の8点目、政治資金パーティーは形を変えた企業・団体献金の温床となることへの見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.60 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 政治資金パーティーは政治資金規正法に基づき適正に開催されるべきものと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.60 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
政治資金パーティーが形を変えた企業・団体献金の温床になるとの問題認識が全く示されなかったことは残念です。
市長、このパネルを御覧ください。
鹿児島市長の政治倫理に関する条例に照らして、政治資金パーティーを開催して市長が政治資金を集めている行為がなぜ問題なのか認識されていないようですので、同条例が制定された経緯を理解してもらうためにこのパネルを用意しました。これは森前市長が2016年市長選挙後に提出した選挙運動費用収支報告書の中で、88人の会社社長が合計1,449万5千円の寄附をしていることが分かりました。このうち80人の会社社長が経営する企業に対して年額約78億円の公共事業を発注していることが分かりました。森前市長は、個人からの寄附であり違法性はないが、いろいろな御指摘があり、疑念を抱かれないために返金したと答弁しました。このような経緯があって条例が制定されたわけです。
そこで、3点質問します。
質問の1点目、鹿児島市長の政治倫理に関する条例が制定された経緯と同条例第3条第3項「政治活動に関し、政治的又は道義的に批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと」についての認識をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.61 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) お触れの条例は、市長は公正・清廉を保持し、行政への市民の信頼を確保する責務があること等に鑑み、市長の政治倫理に関する規律の基本となるものとして制定されたものと理解しております。私は、政治活動を行うに当たっては、本条例にのっとり適切に対応しているところでございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.61 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
市長は、この政治倫理条例に基づいても、今、市長が今年も9回ですか、政治資金パーティーをやられている、このことについて何ら問題はないと、こういう御認識のようです。
質問の2点目、公共事業の発注責任者である市長には厳格な政治倫理の遵守が求められることへの認識はお持ちですか。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.61 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 条例第2条に規定されているとおり、「市長は、市民全体の代表者として、市政に携わる権能、責務及び倫理性を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない」ものと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.61 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
質問の3点目です。
今回の選挙でマスコミは、市長は約260の業界団体や企業から推薦を得られたと報道していますが、これらの団体に政治資金パーティーを案内し、パーティー券の購入を求めるのですか。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.61 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 政治資金につきましては、今後におきましても法令等に基づき適正に対応してまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.61 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
今回、選挙で市長を応援したこの業界団体や企業の方々にも政治資金パーティーの案内をされると、そういう考えだというふうに私は理解をいたしました。
このパネルを御覧ください。
これは市民の市政をつくる会が天文館で2回にわたってシールアンケートをしたときのその結果です。市長の政治資金パーティーについて、「よいと思う」と答えた市民が13人、11.7%、「やめてほしい」と、98人、88.3%でした。これが市民の声です。
今後、政治資金パーティーの開催をやめると、市長、こういう決断はされませんか。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.61 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 政治活動を行うに当たりましては、今後とも政治資金規正法など関係法令に基づき適切に対応するとともに、同法改正についての国会での議論を注視してまいりたいと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.61 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
市長は政治資金パーティーをやめる考えは一切ないということを確認します。私たちはこのことを市民に知らせて、本当にそれでよいのかどうか、市民の皆さんと一緒に、市長が政治資金パーティーをやめますと、こういうことを決断されるまで市民の方々と力を合わせてこれから4年間頑張っていきたいと思います。
新しい質問に入ります。
健康保険証を残してという市民の声を無視して、12月2日から始まった健康保険証の新規発行停止の影響と今後の課題について、以下質問します。
初めに、本市の国民健康保険及び後期高齢者医療保険の直近のマイナ保険証の登録率、利用率と利用率50%を達成していない要因と見解をお示しください。
答弁願います。
P.62 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) お答えいたします。
本市国民健康保険における令和6年9月のマイナ保険証の登録率は69.76%、利用率は31.14%で、報道等によると、国では過去の誤った情報のひもづけ等による不安が解消されていないことなどが要因で利用率が大きく上がらないとしており、本市でも同様の傾向があるものと考えております。
以上でございます。
P.62 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) お答えいたします。
本市の後期高齢者医療における令和6年9月のマイナ保険証の登録率は67.09%、利用率は20.71%で、マイナ保険証の利用が大きく進まない原因として、国では、マイナ保険証のメリットが十分に浸透していないことや後期高齢者はITに不慣れなことがあるなどとしており、本市でも同様の傾向があるものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.62 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
利用率が依然として低い要因は当初から分かっていたことです。国の強引なやり方が医療や介護の現場でかえってトラブルや不安を広げていることを厳しく指摘しておきたいと思います。
次に、健康保険証の新規発行停止の影響について、5点質問します。
質問の1点目、有効期限まで現行の健康保険証を使用できる被保険者数について。
質問の2点目、マイナ保険証の登録解除の件数と解除されるまでの対応について、国保、後期高齢者医療保険の場合、それぞれお示しください。
答弁願います。
P.62 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) お触れの被保険者数は、国保では6年12月1日までに保険証が交付されている約10万2千人です。
次に、国保における10月28日から11月27日までのマイナ保険証の利用登録解除申請は95件で、窓口等での申請月の翌月末日に国においてオンライン資格確認等システムで解除処理が行われます。なお、解除申請後は、有効な保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付することになります。
以上でございます。
P.62 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 後期高齢者医療において、6年10月末までに保険証が交付されている被保険者数は約8万7千人です。
後期高齢者医療において登録解除申請の受付を開始した6年10月28日から11月27日までの1か月間の申請件数は67件で、解除されるまでの対応は国民健康保険と同様です。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.62 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国保と後期高齢者医療保険を合わせてマイナ保険証の解除申請の件数が162件あり、約18万9千人の市民は有効期限日までは手元に現行の保険証があることが分かりました。問題は12月2日以降、国保や後期高齢者医療保険に加入する方で、マイナ保険証を登録している市民の場合、トラブルが想定されますが、後期高齢者医療保険で新たな動きがありました。
そこで、質問の3点目、12月2日以降、後期高齢者医療保険に加入する被保険者数の推計と資格確認書を職権で交付することとなった理由をお示しください。
答弁願います。
P.62 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 後期高齢者医療に6年12月2日から7年7月末までに加入する被保険者数は、前年の同期間の実績により約5,600人と推計しております。国は、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書を職権交付する理由として、後期高齢者はITに不慣れでマイナ保険証への移行に一定の期間を要することなどを挙げております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.62 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
12月2日以降、75歳の到達によって加入する約5,600人の方には職権で現行の健康保険証に代わる資格確認書が交付されることが分かりました。国もトラブルを回避するための措置を講じたことになります。しかし、問題はまだ残されています。
そこで、質問の4点目、資格確認書が交付されないマイナ保険証の登録者について、第1に、短期保険証の有効期限と国保、後期高齢者医療保険の対象者数の推計とその対応について。
第2に、市外からの転入や失業、退職に伴う国保への新規加入者の推計について、それぞれお示しください。
答弁願います。
P.63 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) 国保の短期保険証の有効期間は6か月で、7年3月末が有効期限となっており、対象者は本年11月末時点3,919人で、マイナ保険証を所有していない方には資格確認書を、所有している方には資格情報のお知らせを期限前に送付することとしております。
次に、国保の新規加入者は5年度が約2万5千人です。
以上でございます。
P.63 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 後期高齢者医療において、現在有効な短期保険証は6年12月末が有効期限となっており、対象者は6年12月1日時点で70人です。対象者には12月中に資格確認書を送付することとしております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.63 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
後期高齢者医療保険については短期保険証の方にも資格確認書を交付することが分かりましたが、国保はマイナ保険証の登録者には資格確認書は交付しないようです。
そこで、質問の5点目、国保もマイナ保険証の登録者に後期高齢者医療保険と同様に資格確認書を交付すべきと考えますが、答弁願います。
P.63 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) 資格確認書については法律等により対象者が定められていることから、本市国保独自でマイナ保険証の登録者に資格確認書を交付することは考えておりません。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.63 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国保と後期高齢者医療保険がそれぞれ別の対応をすることが問題です。職権で資格確認書を交付し、トラブルを回避することができるなら統一すべきということは申し上げておきます。
先日、天文館で健康保険証の廃止について宣伝活動をしていると、市民の皆さんからマイナ保険証について様々な意見や質問が出されましたので、今後の課題と対応について、7点質問します。
1点目、病児・病後児保育等での保険証の管理。
2点目、病気で風貌が変わり顔認証できない場合や視覚障害のため顔認証の位置が分からない場合。
3点目、認知症で暗証番号が言えない場合。
4点目、院外の発熱外来で資格確認をする場合。
5点目、重複投与を防ぐため、マイナ保険証で新たな処方履歴の確認に要する期間。
6点目、高齢者施設等の入所者がマイナ保険証の申請ができない場合。
7点目、マイナ保険証の更新期間を忘れ使用できなくなった場合。
以上、それぞれの場合についてどのように対応するのか答弁願います。
P.63 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎた場合でも、引き続き3か月間はマイナ保険証として使用可能であり、3か月経過しても更新をしていない方については職権で資格確認書を送付いたします。
以上でございます。
P.63 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 認知症でカードリーダーの暗証番号を入力できない場合は、顔認証や暗証番号を代理人が入力するほか、医療機関職員の目視により本人確認を行うことができます。また、認知症等によりマイナンバーカードでの受診が困難な方は、マイナ保険証を持っていても申請により資格確認書の交付を受けることができます。
高齢者施設等の入所者を含めマイナ保険証を持っていない方には資格確認書が交付されます。
以上でございます。
P.64 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) お答えいたします。
本市が委託している病児・病後児保育施設においては、基本的に保険証は預かっていないところでございます。
以上でございます。
P.64 ◎答弁 病院事務局長(新穂昌和君)
◎病院事務局長(新穂昌和君) お答えいたします。
顔認証が困難な状況で暗証番号を思い出せない場合には、カードリーダーを目視モードに切り替えた上で、職員による本人確認を行い同意画面に進むこととなります。また、視覚障害者については、職員のサポートの下、手続を進めることになります。
発熱外来での資格確認は、健康保険の資格情報を簡易的に把握できる資格情報のお知らせ、あるいはスマートフォン等によるマイナポータルの資格情報画面をマイナ保険証と一緒に提示していただくことになります。
次に、マイナ保険証で過去の処方情報の提供に同意した場合、参照できるデータは最新でも2か月以上前のものとなります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.64 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) どう対応するのかそれぞれの課題についてお答えいただきましたが、マイナ保険証の使用を実質強制されることによって今以上に負担や手間がかかる実態が示されました。処方履歴で重複投与を把握するためにマイナ保険証で2か月待たなくてもお薬手帳があれば十分です。マイナ保険証の更新期間が過ぎた場合、職権で資格確認書を交付するぐらいなら、今までどおり現行の健康保険証を使えば何も問題ないわけです。
そこで、最後に、市長にお聞きします。
私は、マイナ保険証ではこれらの課題は解決できないと思います。健康保険証とマイナ保険証の併用を国に求めるべきと考えますが、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.64 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) マイナ保険証に関しては、今回の健康保険証の廃止に当たり、被保険者等に混乱が生じることのないよう周知・広報することを全国市長会を通じて要望しており、国においては、マイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行に向け、後期高齢者への資格確認書の職権交付など、全ての方が安心して確実に医療が受けられるよう様々な取組がなされておりますので、引き続き適切に対応していただきたいと考えております。本市においても、市民の皆様の不安解消につながるよう、関係課において丁寧な対応と適切な周知・広報に努めてまいります。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.64 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
混乱が生じないようにと言われますが、もう既に混乱は生じているのです。認識を改めていただきますよう要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
先日、県国保運営協議会が開催され、令和7年度の市町村国保の税率改定に影響を与える仮算定が発表されたことから、国保行政について質問します。
初めに、県が本市に示した仮算定の影響について、3点質問します。
1点目、仮算定での県国保財政安定化基金の活用と県国保特会の主な収入、支出の内容及び前年度比較とその要因をお示しください。
2点目、令和7年度の県1人当たり国保事業費納付金と6年度本算定との比較、その増減の要因をお示しください。
3点目、7年度の本市の国保事業費納付金額と6年度本算定との比較、その増減の要因をお示しください。
以上、それぞれ答弁願います。
P.64 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) お触れの基金については、7年度の仮算定において財政調整に活用可能な基金残高が目標額の44億円を上回ることなどから2億円の取崩しが行われたところです。また、県国保特会の主な収入は、国費等が1,308億6千万円で、国庫負担金の減により対前年度比13億5千万円の減、主な支出は保険給付費が1,454億円で、被保険者数の減により32億円の減となっております。
次に、7年度の仮算定における県1人当たり国保事業費納付金は14万1,894円で、保険給付費の減により6年度本算定と比べ、6,299円、4.3%の減となっております。
本市の7年度の同納付金は153億9千万円で、同様に、9億3千万円、5.7%の減となっております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.65 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
県は目標を超える基金の中から2億円を取り崩して、納付金の上昇を抑制する措置を講じるようです。また、7年度は被保険者数の減少に伴い保険給付費の減少が見込まれるため、本市が県に収める国保事業費納付金も6年度を下回ることが明らかにされました。県は毎年度納付金を納めるための標準保険料率を市町村に示しています。
そこで、本市に示された標準保険料率に基づくモデルケース世帯の国保税の試算と現行税額との比較について質問します。
夫45歳、給与所得200万円、妻42歳、所得なし、小学生、中学生、子供2人の4人世帯の場合と年金所得100万円で65歳以上の高齢者夫婦2人世帯の場合について、それぞれお示しください。
答弁願います。
P.65 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) 給与所得200万円で40歳代夫婦、子2人の世帯の国保税額を試算しますと、県から示された標準保険料率では41万6,600円、本市の現行税率では33万2,300円となります。
また、年金所得100万円で65歳以上の夫婦の場合は、同様に、12万5,200円、10万2,700円となります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.65 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
県が示す保険料で算定した場合、大幅な負担増になることが分かりました。県に収める納付金が減少しても重い負担増に変わりはありません。
第3回定例議会の質問の中で、県は市町村の医療費水準を反映させない納付金ベースの統一を目指していることが分かりましたが、納付金ベースの統一の場合、本市は標準保険料率による国保税の負担を上回ることになるのかお示しください。
答弁願います。
P.65 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) 納付金ベースの統一の場合、本市の医療費指数約1.2が国保事業費納付金に反映されないことから、標準保険料率は現行より低くなるものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.65 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
医療費指数の高い本市は負担が低くなるとの答弁ですが、医療費水準の低い市町村にとっては負担増となります。医療費水準を下げても負担増となるのが納付金ベースの統一であることが分かりました。
次に、市民の市政をつくる会等から提出された署名数と要請内容及び本市の見解をお示しください。
答弁願います。
P.65 ◎答弁 市民局長(山本倫代君)
◎市民局長(山本倫代君) お触れの署名数は4,040筆で、2025年度に向けて国保税を引き下げることなどの要請があったところであり、被保険者の方々の率直なお気持ちとして受け止めておりますが、国保税については、保険料水準統一の動きや非常に厳しい状況にある本市国保財政の今後の収支見通しなどを踏まえ、総合的に検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.65 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
4千筆を超える署名が提出されています。市民の声として重く受け止めてください。
市長のマニフェストでは国保行政については触れられておりませんが、国保の完全統一に向け、市町村の財政負担が増加しないように県や国に要請すべきと考えますが、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.65 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 国においては、高額な医療費の発生等による年度間の保険料の変動を抑制できることや都道府県内のどの市町村でも同じ保険給付を同じ保険料負担で受けられることで被保険者の公平性を確保するため、保険料水準統一に向けた取組が強化されてきており、本県におきましても国の方針を踏まえながら、県と市町村間で協議を行っているところでございます。国や県に対しましては、保険料水準統一により生じる急激な保険料率の上昇を抑制するため、財政支援による激変緩和措置を講じるよう、全国市長会や関係会議を通じて要望しております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.66 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
県は国保財政の責任主体と言いながら、県は自ら財政負担をすることを全く表明していません。市長、今動くときです。そのことを強く要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
分園を有する保育所等に係る過払い金の返還に関する補正予算が本議会に提出されていることから質問します。
初めに、返還の内訳と返還した保育所等について、4点質問します。
質問の1点目、国庫への返納額、県への返納額、市費の精算確定による返納額をそれぞれ年度ごとにお示しください。
質問の2点目、保育施設からの返納額をお示しください。
以上、答弁願います。
P.66 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 分園を有する保育所等に係る過払い金のうち、施設と協議が調い金額が確定した6,267万2,450円の内訳について、国庫、県費及び市費の精算確定による返納額を年度ごとに順に申し上げますと、令和2年度、962万1,387円、614万2,587円、830万9,148円、3年度、832万5,820円、555万1,620円、743万1,866円、4年度、677万2,095円、509万2,874円、542万5,053円でございます。
国庫及び県費を含め、これまで施設から市へ返納された金額は4施設で1,005万128円でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.66 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
保育施設から実際に返納された額はまだ一部のようですが、合計6,267万2,450円の返納額が確定しているようです。
そこで、質問の3点目、昨年12月の所管の委員会に報告された当初の返還額と今回の金額に差が生じている、その差額の要因をお示しください。
答弁願います。
P.66 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 5年12月に防災福祉こども委員会へ報告した額と施設と協議が調い確定した額との差は1,517万1,665円で、これは協議中の1施設が含まれていないこと等によるものでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.66 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 協議中の施設の返納額が含まれていないことなどが要因とのことですが、では、返納額について協議が調った保育施設とは合意の上の返還か否か、返還に際して施設からの意見をお示しください。
答弁願います。
P.66 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 各施設とは協議合意の上、返還いただいており、返還の時期や支払い方法などについて相談があったところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.66 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 施設側と合意の上で返納額は確定していることを確認します。
次に、返還されていない施設数と返還額及び今後の本市の対応をお示しください。
答弁願います。
P.66 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 今回の補正予算に計上していない施設は1施設で、現在、返還額の確認など協議中であり、金額が確定していないため、引き続き丁寧に協議を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.66 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
現在協議中とのこと、ぜひ丁寧に協議を進めてください。
そもそもなぜ多額の過払い金が発生したのか、過払い金が発生した原因と責任の所在をお示しください。
答弁願います。
P.67 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 今回の過払い金は、国が2年3月30日に発出した公定価格に関するFAQに新たに追加した本園と分園の保育士等の算定方法の項目を見落としたことによるもので、本市に責任があるものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.67 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
過払い金を発生させた責任は全て鹿児島市にあり、施設側に全く責任がないにもかかわらず、民法第703条の不当利得返還請求に基づく本市からの要請に対して、施設側はやむを得ず返還に応じる結果になったと思います。このような問題を二度と起こしてはいけません。
再発防止のための今後の方針をお示しください。
答弁願います。
P.67 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 今回の件につきまして、保育幼稚園課においては、国のFAQ等が更新された場合の確認が十分でなかったことから、国等からの通知について、各係複数の担当で確認を行い体制の強化を図るとともに、こども未来局全体においても関係機関からの通知等について取組の強化を図るよう指示したところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.67 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
極めて当たり前の再発防止対策だと思いますが、今後の当局の取組を注視することを申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
経営者による独断専行の施設経営によって職員への賃金不払い等が大量の退職者を招き、入居者に適切な介護サービスを提供できなくなり、行政指導の結果、多額の介護報酬返還金を求めることになった株式会社心の家問題と有料老人ホーム設置運営指導指針の見直しについて、以下質問します。
質問の1点目、未済となっている介護報酬返還金4,403万977円はその後一部でも回収できたのか。
質問の2点目、未済となる現状を招いている心の家問題の教訓は何か。
以上、それぞれ答弁願います。
P.67 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 心の家に係る介護報酬返還金は、一括返還を請求して以降、回収できておりません。
今回の事例は、経営状況の変化やそれに伴う職員の離職により利用者へのサービスの質の低下につながったものと考えていることから、有料老人ホームの役員等の変更時にもサービス提供の運営体制や経営状況を把握できるような実効性のある仕組みが必要であると考えたところです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.67 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
全く回収できていないことが分かりました。なぜこのような事態になっているのか。その最大の教訓は、設置者による独断専行の施設運営を市当局が止めることができなかったという点であります。
このような問題を二度と起こさないために、私は、鹿児島市有料老人ホーム設置運営指導指針の見直しを求めてきました。11月15日から見直しが実施されているようですので、その主な内容について、2点質問します。
1点目、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を、定期的に開催する目的と期待する効果について。
2点目、運営状況等に関する報告を求める目的と期待する効果について、それぞれ心の家問題との関連で見解をお示しください。
答弁願います。
P.67 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) お触れの委員会は、有料老人ホームにおける業務の効率化、介護サービスの質の向上などに資する取組の促進を目的としており、定期的に開催することで従業者の負担軽減により働きやすい職場がつくられるとともに、サービスの質の向上が図られ、ひいては安定的な事業運営につながるものと考えております。
また、運営状況等に関する報告は、サービス提供の運営体制や経営状況を把握することを目的としており、新規設置時に加え、役員等の変更時などにも求めることで、適正なサービス提供確保のための指導監督の強化が図られるものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.68 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 見直しによる効果が発揮され、再発防止につながることを期待して注視してまいりますが、今後、同指導指針の見直しの周知徹底を図るべきと考えますが、答弁願います。
P.68 ◎答弁 健康福祉局長(福島宏子君)
◎健康福祉局長(福島宏子君) 同指導指針の見直しについては、市内の有料老人ホームを運営する法人へ通知を行ったほか、市ホームページへ掲載しており、今後、集団指導においてさらなる周知を行うこととしております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.68 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
今後、研修の場を設けるとのことですが、とりわけ設置者に対する周知徹底を強く求めて、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
私は、昨年の第4回定例議会で、令和5年度に公募対象となった会計年度任用職員のうち、再度の任用を希望した職員の雇用の継続について質問しましたが、30人の雇用が継続されなかったことが明らかになり、任用回数の見直しを求めました。
そこで、雇用継続の不安を持つ会計年度任用職員について、以下質問します。
初めに、市長事務部局等、各公営企業における同職員数をお示しください。
答弁願います。
P.68 ◎答弁 総務局長(遠藤章君)
◎総務局長(遠藤章君) お答えいたします。
令和6年4月1日現在の会計年度任用職員数は、4企業を除く市長事務部局等2,552、市立病院674、交通局84、水道局28、船舶局29人でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.68 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
全体で3,367人の職員の皆さんが働いておられますが、雇用継続に関して新たな国の動きがありました。今、全国の地方自治体で3年目公募の上限を撤廃する動きが広がっています。
そこで、本市の対応方針をお示しください。
答弁願います。
P.68 ◎答弁 総務局長(遠藤章君)
◎総務局長(遠藤章君) 本市におきましては、会計年度任用職員の公募によらない再度の任用の上限回数について、これまで連続2回までとしていたものを国のマニュアルが改正されたことに伴い撤廃したところです。適用時期は、令和6年度末に任期が終了し令和7年度に再度の任用を行う同職員に対する選考からとしており、適用範囲は公営企業を含んでおります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.68 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
これまで本市は国が示す例示を根拠にしていましたので、本市が3年目公募の上限を撤廃する判断を行ったことは当然の措置だと考えます。
では、今後公募する場合は、欠員や増員が生じる場合、新規の職を設置する場合だけなのかお示しください。
答弁願います。
P.68 ◎答弁 総務局長(遠藤章君)
◎総務局長(遠藤章君) 同職員の公募については、お触れのもののほか、人事評価の結果に基づくものや勤務条件の変更等により実施することが想定されます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.68 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
3年目公募が撤廃されても所属長の人事評価によっては公募の対象となり再任用されない可能性があります。
そこで、公正な人事評価の在り方と所属長が留意すべき点をお示しください。
答弁願います。
P.69 ◎答弁 総務局長(遠藤章君)
◎総務局長(遠藤章君) 同職員の人事評価は、1次評価者、2次評価者による評価を行い、常勤職員と同様、原則面談による結果開示を行うことにより透明性を確保しております。所属長は恣意的な評価とならないよう、評価期間内の職務遂行の実績に基づいて適切に評価することが重要であると考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.69 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
恣意的な評価が行われないように配慮するとのことですが、国は公募を行う場合はトラブルが生じないように十分にコミュニケーションを図ることを求めています。
では、会計年度任用職員は、人事評価や処遇に疑問がある場合、どのように解決を図るのか。
そこで、公平委員会について質問します。
初めに、同委員会の業務内容と過去5年間の実績をお示しください。
答弁願います。
P.69 ◎答弁 総務局長(遠藤章君)
◎総務局長(遠藤章君) 公平委員会は、地方公務員法に基づき、職員の勤務条件に関する措置要求の審査、職員に対する不利益処分についての審査請求の審査及び職員の苦情処理を行うこととなっております。また、令和元年度から5年度までの実績を合計件数で申し上げますと、措置要求1、審査請求1、苦情相談6件でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.69 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 5年間で8件は大変少ないという印象を持ちます。職員の皆さんにとって公平委員会はハードルが高いのではないでしょうか。
そこで、会計年度任用職員への周知と苦情相談を行いやすい職場環境の整備が必要と考えますが、お示しください。
次に、同委員会の公営企業の同職員に対する対応をお示しください。
以上、答弁願います。
P.69 ◎答弁 総務局長(遠藤章君)
◎総務局長(遠藤章君) 公平委員会の役割につきましてはこれまでも庁内掲示板等により周知を図ってきておりますが、今後におきましても機会を捉えて周知してまいりたいと考えております。
また、公営企業の職員については、地方公営企業法により公平委員会の対象外とされており、各企業において対応することとなっております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.69 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 私が危惧する点は、公平委員会に苦情相談したことによって公募の対象となり、雇用が継続されないという不利益を受ける結果にならないかという点です。そのようなことは断じてないということは明確に周知してください。
公営企業の職員は公平委員会の対象外とのことですので、次に、苦情処理共同調整会議の設置について、同会議の法令根拠と業務内容をお示しください。
答弁願います。
P.69 ◎答弁 交通局長(枝元昌一郎君)
◎交通局長(枝元昌一郎君) お答えいたします。
お触れの会議は、地方公営企業等の労働関係に関する法律により設置が義務づけられており、地方公営企業と労働組合が職員の苦情を解決するとされております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.69 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本市では4つの公営企業で合計815人の職員が働いておられます。同会議は法令上設置が義務づけられており、職員の苦情相談の解決に取り組むことになっているとのことです。
そこで、各公営企業での同会議の設置の現状と会計年度任用職員の苦情処理への対応をそれぞれお示しください。
答弁願います。
P.69 ◎答弁 交通局長(枝元昌一郎君)
◎交通局長(枝元昌一郎君) 交通局では同会議は設置しておりませんが、会計年度任用職員からの苦情相談は総務課で対応しております。
以上でございます。
P.70 ◎答弁 水道局長(鬼丸泰岳君)
◎水道局長(鬼丸泰岳君) お答えいたします。
水道局におきましては、苦情処理共同調整会議を設置しております。また、会計年度任用職員からの苦情相談につきましては、随時、総務課で対応することとしており、同会議による苦情の解決について請求があった場合には適切に対応してまいります。
以上でございます。
P.70 ◎答弁 船舶局長(橋口訓彦君)
◎船舶局長(橋口訓彦君) お答えいたします。
船舶局では、苦情処理共同調整会議を設置しております。また、会計年度任用職員から相談があった場合は総務課が窓口となり対応しておりますが、同会議による苦情の解決について請求があった場合は、労働協約に基づき適切に対応することとしております。
以上でございます。
P.70 ◎答弁 病院事務局長(新穂昌和君)
◎病院事務局長(新穂昌和君) 市立病院では苦情処理共同調整会議を設置しております。また、会計年度任用職員からの苦情相談につきましては、随時、総務課で対応しておりますが、同会議による苦情の解決について請求があった場合は適切に対応することとしております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.70 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
交通局以外の3つの公営企業では設置しているとのことです。しかし、労働協約の中で設置を合意しているだけで設置要綱や申立書が見受けられません。このような現状では会計年度任用職員からの相談が適正に処理されるのか疑問であります。
そこで、この質問の項の最後に、市長に質問します。
会計年度任用職員の権利擁護のために、法令上義務づけられている苦情処理共同調整会議の設置を各公営企業管理者に求めるべきと考えますが、見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.70 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 苦情処理共同調整会議は、公営企業において本市の第三者機関である公平委員会に代わるものであり、法令どおり設置されるべきものと考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.70 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
設置している公営企業についても先ほど指摘した課題があると思いますので、その点も含めて各公営企業管理者に要請をしてください。
以上で、私の個人質疑を全て終わります。