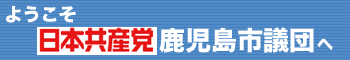P.128 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
11月17日告示、24日投票で行われた鹿児島市長選挙では、私ども日本共産党は、市民の市政をつくる会の構成団体の1つとして、桂田みち子候補を推薦し、憲法を生かした清潔で公正な市政、お金で動くのではなく市民の声で動く市政、7つのチェンジで市民の命と暮らしを守る「あったか市政」の実現を掲げて取り組みました。無投票とならなかったことによって選挙が多様な市民の声に耳を傾ける機会となったのではないかと考えます。私ども党市議団も今後とも7つのチェンジで掲げた50のマニフェストの実現に全力を尽くす決意です。
今回の個人質疑では、下鶴市長のマニフェストの方向性を確認する立場から伺ってまいります。
最初の質問は、市長の政治姿勢についてです。
市長選挙でも注目された多機能複合型スタジアム、いわゆるサッカー等スタジアムについて、以下伺います。
質問の1点目、下鶴市長の1期目の4年間は、スタジアム整備におけるこれまで検討されてきた候補地や新しく提案された北埠頭が白紙となり、鹿児島サンロイヤルホテルの移転方針をめぐって、同跡地の候補地としての可能性が取り沙汰されていますが、9月の第3回定例会以降進展はあったものか、現在の進捗状況をお示しください。
質問の2点目、市長選挙では、桂田みち子候補が市民には市が多大な財政負担となることを懸念する声もあり、主体的にスタジアムを建設しようとする民間企業を後押しする企業主導型でと主張したほか、市民団体の行ったシールアンケートでは、そもそも必要ないとの意見も寄せられました。市長の下にも様々な市民の声が寄せられているのではないかと考えますが、多機能複合型スタジアムの進め方について、市長選挙を経ての変化はあるのかお示しください。
質問の3点目、報道の中で有識者の方が企業主導型について、引き受けてくれる民間企業があるのかそこが非常に疑わしい。引き受け手がないと自治体は考えているし、実際そうなんじゃないかとのコメントが掲載されていましたが、本市で企業主導型は難しいのか、課題認識をお示しください。
以上、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.129 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 大園たつや議員にお答えいたします。
スタジアムの検討状況につきましては、本市の基本的な考え方である中心市街地との回遊性が期待できることなどの条件を県と共有した上で、各面からの情報収集に努めながら、新たな候補地の選定に向けて県と一緒になって取り組んでいるところでございます。
今回の市長選挙の期間中、様々な御意見を伺う中で、選ばれるまちの実現へ向け、若い世代に選ばれる魅力ある環境の創出が重要であり、スタジアムの必要性について改めて思いを強くしたところでございます。今後も引き続き、市議会における論議を踏まえるとともに、クラブや関係団体などの民間も含めたオール鹿児島の体制で取り組んでまいりたいと考えており、まずは県と一緒に候補地の選定を進めてまいります。
今年に入り、民間主導での長崎スタジアムシティ、県、市が中心となったエディオンピースウイング広島など、各都市の実情に応じてスタジアム整備が進んでおりますが、本市におきましては、企業からの協力は必要不可欠でありつつも、自治体が果たす役割は大きいものと考えており、引き続きオール鹿児島での整備に取り組んでまいりたいと考えております。
[大園たつや議員 登壇]
P.129 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
市長選挙を通じて様々な意見をいただき、選ばれるまちの実現に向けて、その必要性に向けて思いを新たにしたこと、そして、企業主導型については、自治体の役割も大きいということを答弁されました。候補地の問題はまだありますが、鹿児島市内外の企業にその熱意を伝えて、主体的にスタジアムを建設しようとする民間企業を発掘し、トップセールスをすることこそ市長にしかできない役割ではないでしょうか。また、サッカー等スタジアムについて、私どもとしては公共丸抱えで本市財政に多大な負担が生じるならば容認することはできない、そのことを申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
子育て支援について、市長選挙のマニフェストを踏まえて、今後の展開を明らかにする立場からの質問です。
まず、マニフェスト「こどもの視点に立った多様な居場所づくりを進めます」について、以下伺います。
質問の1点目、子供の視点に立った多様な居場所づくりの内容と学校に行けない子供たちの居場所づくりとの関連について、市長の見解をお示しください。
以上、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.129 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 今回、マニフェストで掲げました「こどもの視点に立った多様な居場所づくりを進めます」は、地域のつながりの希薄化や少子化の進展等により、子供同士が遊び、育ち、学び会う機会が減少していることを受け、国の指針を踏まえながら、生活基盤となる家庭や学校以外に安心して過ごすことができる子供の居場所づくりを推進しようとするもので、不登校や児童虐待などをはじめ様々な環境にある全ての子供が対象と考えております。
[大園たつや議員 登壇]
P.129 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
全ての子供たちに多様な居場所を提供することをイメージされており、学校に行けない子供たちの居場所も含まれると理解します。桂田候補もマニフェストで、「学校に行けない子どもたちの居場所づくりの充実やフリースクール等との連携を進めます」と掲げており、共通の喫緊の課題ではないかと考えます。
そこで、質問の2点目、学校に行けない子供たちと施策の現状について伺います。
まず、フレンドルーム設置の3校における現状について、不登校となっている生徒の数。
フレンドルーム、フレンドシップ、フレンドステップ・メタバースの登録数と効果。
学校内外の機関等で専門的な相談、指導等を受けていない生徒の数をお示しください。
以上、答弁願います。
P.130 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) お答えいたします。
フレンドルーム設置の3中学校における不登校生徒数は、6年11月末時点で172人でございます。
6年11月末時点の登録者数をフレンドルーム、フレンドシップ、フレンドステップ・メタバースの順に申し上げますと、91、7、3人であり、生徒の状況に応じた居場所として一定の効果につながっているものと考えております。
学校内外の機関等で専門的な相談、指導等を受けていない人数は、6年11月末時点で67人でございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.130 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
フレンドルームを設置した3校においては、学校に行けない生徒の多くがルームなどの施策につながり、設置校においては新たな居場所の1つとして多様な居場所づくりの選択肢になっていることが分かりました。一方で、まだ施策につながっていない生徒も多くおり、特段の配慮が必要と考えます。
次に、今年度における不登校となっている児童生徒の現状の特徴と要因をお示しください。
以上、答弁願います。
P.130 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) 6年度における不登校児童生徒の現状としましては、5年度の同時期と比較し人数は同程度ですが、新たに不登校となった児童生徒は6割程度減少しており、その要因といたしましては、コロナ禍の影響により制限されていた活動の再開、個に応じた学習機会や教育機会の確保等により一人一人が個性を発揮し、安心して登校できる環境が整いつつあるものと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.130 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
だんだんと学校行事も新型コロナウイルスでの行動制限以前の活動に戻りつつあり、そのことが学校での先生方や友人との交流、学校行事での活躍の場につながり、新規での学校に行けない子供の減少につながっていることはよい兆しだと考えますが、まだまだ予断を許さない状況です。
質問の3点目、学校に行けない子供たちの居場所の充実における国の動向として、関連省庁における概算要求について伺います。
まず、こども家庭庁、地域における不登校のこどもへの切れ目ない支援事業の内容。
次に、文科省、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校・いじめ対策等の推進の内容。
概算要求の内容を踏まえて、教育委員会とこども未来局との一層の連携と課題への認識をお示しください。
以上、答弁願います。
P.130 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) お答えいたします。
こども家庭庁の地域における不登校のこどもへの切れ目ない支援事業は、県や市区町村が実施主体となり、学校や地域社会とのつながりが持てずにいる子供を含め、子供が学校を休み始める時期から回復するまでの時期に応じた支援の手法等の開発、実証や関係機関等との連携による包括的で切れ目のない支援モデルの創出を目指すものでございます。
以上でございます。
P.130 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) 文部科学省の誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校・いじめ対策等の推進の内容は、不登校児童生徒の学びの場の確保の推進、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置充実、いじめ・不登校等の未然防止等に向けた魅力ある学校づくりに関する調査研究などとなっております。
不登校児童生徒の中には学校につながりが持てない者もいることから、国の動向等も注視しながら、今後、こども未来局をはじめ、関係部局との情報共有や協議の機会を通して、課題解決に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.131 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
概算要求ですのでそのまま具体化されるかどうかはこれからですが、イメージとしては、教育委員会が所管しているフレンドルームやスクールカウンセラーなどは充実を図りつつ、学校を中心とした地域のフリースクールなどの団体やNPOと協力した居場所づくりをこども家庭庁が充実する内容となっています。これまでも児童クラブやヤングケアラーなど連携が求められてきましたが、この分野においても一層の連携が必要になってくるということは申し上げておきます。
質問の4点目、マニフェストの子供の視点に立った多様な居場所づくりを市長は具体的にどのように進められるのか、見解をお示しください。
以上、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.131 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 子供の視点に立った多様な居場所づくりに関しましては、様々な環境にある全ての子供を対象としており、子供のニーズや既存資源の把握が不可欠と考えておりますことから、国の指針を踏まえながら、まずは子供の居場所に関する実態等を把握してまいりたいと考えております。
[大園たつや議員 登壇]
P.131 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
具体的には子供の居場所の実態の把握からスタートをされるということでした。これまでも本市は親子つどいの広場や地域子育て支援センター、児童クラブや障害児通所支援、そして放課後等デイ、不登校対策としてのフレンドルームやフレンドシップなど子供の居場所づくりに取り組んできました。もちろんこれらの施策の充足と充実にまず責任を持たなければならないと考えますが、その上で、地域のNPOや市民団体、フリースクールなどと協力・連携した居場所づくりとなるよう注視してまいります。
次に、マニフェスト「発達障害の療育支援を行います」について、以下市長に伺います。
さきの第3回定例会では、障害児通所支援等の一部有料化を検討していた本市に対して、市民団体の障害児通所支援利用者負担無料の継続を求める会が現在の制度の継続を求めて2万5,292筆の署名を提出したことを踏まえて質疑を交わしました。
先日の個人質疑で市長は、利用料を無償化している現在の市独自施策について、放課後デイを一部有料化するとの趣旨の答弁をされたことから、以下伺います。
質問の1点目、署名を提出した市民団体は市長に直接お会いして皆さんの気持ちをお伝えしたいと切望しておられましたが、会うことができたのかお示しください。
質問の2点目、「発達障害の早期発見・療育に向け、引き続き取り組みます」とは、現在の利用料無料の独自施策を含め制度のことではないのか、市長の見解をお示しください。
以上、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.131 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 署名を提出された団体の方々とはお会いしておりませんが、担当課には責任を持って対応するよう指示しており、私も署名とともにお寄せいただいた手紙やメッセージを通して、保護者の皆さんなどの率直な御意見を拝見したところです。お触れのマニフェストは、発達障害の早期発見・療育に向け、各種健診や巡回相談等による支援体制の整備や障害児通所支援サービスの提供などに引き続き取り組むものでございます。
障害児通所支援の利用者負担独自助成については、今後も財政的な負担増が見込まれる中、制度を持続可能で安定的に継続するため、これまでの市議会での議論や他都市の状況を踏まえるとともに、利用者の声などにも耳を傾けながら各面から検討してまいりましたが、療育環境の充実や利用促進が図られてきており、中核市62市中、全額助成を行っているのは本市のみで、6年度調査による人口1千人当たりの受給者証所持者数は、中核市平均と比較して、本市は児童発達支援で3.4倍、放課後等デイサービスで2.5倍となっていることなどを踏まえ、児童発達支援は早期療育を推進する観点から全額助成を継続することとし、放課後等デイサービスは7年度中に全額助成から一部助成見直し、引き続き運営状況を注視してまいります。なお、負担率や実施時期など詳細については7年度予算としてまとめ御審議いただきたいと考えております。
[大園たつや議員 登壇]
P.132 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
たくさんの署名が届けられたら、選挙前の9月議会では一旦取り下げて、市民団体とは会わずに、市長選挙では具体性のないマニフェストではぐらかして、当選した途端に一部有料化を明言する、これが当事者抜きで決めないでほしいと集められたたくさんの署名と声に対する市長のやり方なんですか。争点隠し、公約違反と言わざるを得ません。市長がマニフェストで掲げた、「すべての子どもが生まれ育った環境に左右されることなく、等しくチャンスを得て、夢と希望を持ち、健やかに成長していける社会の構築」、そして、「発達障害の早期発見・療育に向け、引き続き取り組みます」と、今回の方針は整合性がないと私は思いますが、再質問します。
マニフェストとの整合性はあるのかないのか、市長の見解をお示しください。
以上、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.132 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 先ほども申し上げましたとおり、お触れのマニフェストは、発達障害の早期発見・療育に向け、各種健診や巡回相談等による支援体制の整備や障害児通所支援サービスの提供などに引き続き取り組むものでございます。
障害児通所支援については、国の制度では、生活保護及び市民税非課税世帯には負担を求めない応能負担制度が設けられていることなどを踏まえ、利用者負担独自助成は今後も財政的な負担増が見込まれる中、制度を持続可能で安定的に継続するために、放課後等デイサービスについて一部助成に見直すものでございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.132 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
全ての子供が生まれ育った環境に左右されることはない、それはお金持ちでも所得が少ない方でも一緒だと私は思います。私は療育を無償化している現在の助成とこども医療費助成制度は市長の目指す「若い世代・子育て世代に選ばれるまち」の根幹をなす制度だと思います。中核市で本市しかやっていないというのなら唯一無二の制度ではないですか。だからこそ選ばれるまちになるんだということは厳しく指摘いたしますとともに、有料化すべきではないということは改めて申し上げておきたいと思います。
桂田候補は、市民のたくさんの署名と声が届けられたことを踏まえて、子供の命と発達に責任を持ち、その未来と可能性を応援するまちにチェンジするとして、「障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイ)の利用料を無償にしている現行制度を恒久的に継続します」とマニフェストに掲げました。私どもは今後ともその立場で市長に求めていく決意であることを申し上げます。
次に、マニフェスト「小中学校の屋内運動場への空調設備の整備を検討します」について伺います。
質問の1点目、同マニフェストを「選ばれる安心安全なまちを目指します」ではなく、「こどもまんなか社会の実現に向けて取り組みます」の項目で掲げた理由と背景について、市長の見解をお示しください。
以上、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.132 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 近年、猛暑日の増加など厳しい気象状況下にある中、子供たちが多くの時間を過ごす学校は健康的で安全な教育環境を整備することが大切であり、小中学校の屋内運動場に空調設備が設置されることで快適な環境で運動や学習活動に取り組むことができるものと考えております。
また、屋内運動場は災害時に避難所としての役割を果たすことから、空調設備が設置されることで、避難者の健康管理等を含めた避難所機能の強化につながることに加え、国においても避難所となる公立小中学校の体育館等への空調設備の整備を加速していくこととされていることから、国の動向を注視しながら検討してまいりたいと考えております。
[大園たつや議員 登壇]
P.133 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
私は、9月の第3回定例会において、この夏が記録的な酷暑となったことも踏まえ、これまでの避難所としての必要性に加え、子供たちの熱中症対策、安心安全な体育の時間の確保のためにも必要と質疑を交わしました。桂田候補のマニフェストにも、「記録的な猛暑に対して避難所ともなっている学校体育館に安全安心な体育の授業の確保のためにも空調を設置します」が掲げられていることから、そのような観点を踏まえてのマニフェストと理解します。
質問の2点目、学校体育館への空調施設の設置について、現在考えられる国の補助の内容をお示しください。
質問の3点目、補助の内容ごとの対象校数及び避難所として指定されている数をお示しください。
質問の4点目、今後の屋内運動場への設置予定をお示しください。
以上、答弁願います。
P.133 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) 国の補助につきましては、旧鹿児島市と旧桜島町は降灰対策に係る補助が活用でき、補助率は3分の2、6年度の補助限度額は補助単価3万5,400円に面積と補助率を乗じた額でございます。その他の地域は大規模改造に係る補助が活用でき、断熱性があることを要件に補助率は2分の1、補助限度額は同じ補助単価に面積と補助率を乗じた額と3,500万円を比較し、低い額でございます。
補助対象となる市立小中学校につきましては、降灰対策に係る補助は93校で、そのうち指定避難所は77校、大規模改造に係る補助は23校で、そのうち指定避難所は16校でございます。
今後建設予定の桜島学校において、屋内運動場への空調設備の設置を予定しております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.133 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) ただいまの答弁から考えられるのは、断熱性を条件とせず、補助率のよい降灰に係る補助を活用し、避難所の指定がされている、かつ大規模改修が予定されている屋内運動場から順次設置していくというのが具体的でしょうか。
そこで、質問の5点目、具体化に向けた基本的な考え方をお示しください。
以上、答弁願います。
P.133 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) 空調設備につきましては、国の補助制度の見直しの動向を踏まえ、避難所としての利用状況や施設改修等の観点から対象校の選定を行うとともに、空調方式について先進地の事例を参考に検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.133 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
第3回定例会での私の質疑への教育長からの答弁は、使用頻度や財政上の制約もあることから難しい状況にあるでした。しかしながら、市長選挙の両候補がマニフェストに掲げたことから、市民要求が1歩前進したことは選挙の効果と言えるのではないでしょうか。市長におかれましては、ぜひ検討に終わらず、スピード感を持って具体化していただきますよう強く要請し、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
今年の9月26日にこども家庭庁が公表した令和4年度児童相談所における児童虐待相談対応件数は、対前年度比3.5%増の21万4,843件、鹿児島県は前年度比15%増の2,423件と伸び率は鈍化しているものの引き続き過去最多を更新しています。令和4年度の結果とはいえ、今後の物価高騰による子供の貧困への影響に伴う児童虐待の増加が懸念されることから、児童虐待防止対策、子ども見守り強化事業について以下伺います。
質問の1点目、現在の実施団体数と対象世帯数及び令和6年度予算との比較をお示しください。
質問の2点目、要保護児童対策地域協議会で把握している配慮の必要な子供の数をお示しください。
質問の3点目、本市の子ども見守り強化事業の奏功事例をお示しください。
以上、答弁願います。
P.134 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) お答えいたします。
子ども見守り強化事業の令和6年11月末現在の実施団体数と対象世帯数は、4団体、19世帯で、6年度当初予算計上時と比べ、団体数は同数で世帯数は1世帯少なくなっております。
要保護児童対策地域協議会に登録されている児童は、5年度末で1,046人となっております。
同事業の奏功事例といたしましては、継続した訪問を通して、訪問員との関係性が構築され、ほかの福祉サービスの利用につながった、体調不良の子供を医療機関受診につなげることができたなどがございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.134 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
令和6年度予算と比べて同じぐらいの数で推移しているようです。また、協議会で把握している配慮が必要な子供は私が初めて質疑したときには800人でしたので、かなり増加しており、福祉サービスとつなげるなど奏功事例もある同事業の実施団体も対象世帯数もまだまだ市域に広げていく必要があると考えます。
質問の4点目、同事業におけるこども家庭庁の概算要求の内容と特徴をお示しください。
以上、答弁願います。
P.134 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 国では、支援対象児童等見守り強化事業を7年度も実施することとしており、事業の内容は、子ども食堂や子供への宅食等を行う民間団体等と連携して食事の提供を通じた子供の状況把握を行うことにより地域における子供の見守り体制の強化を支援するもので、国の補助率は3分の2でございます。特徴としては、おむつ等の消耗品の提供等による巡回活動強化の経費加算や都道府県を介した中間支援法人の活用による事業展開の加速化が示されているところでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.134 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
現在のお弁当の配達だけではなく、紙おむつなどの消耗品の提供の経費への加算のほか、子供自身が申請できる仕組みや都道府県を介した中間支援法人の活用など体制強化を図る内容となっています。
そこで、質問の5点目、これまでも課題として指摘してきましたが、実施団体を広げる取組と制度のさらなる充実についての見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.134 ◎答弁 こども未来局長(浅井孝君)
◎こども未来局長(浅井孝君) 5年度に要綱を改正し、実施団体の範囲を拡大して、NPO法人等に同事業の紹介を行っておりますが、新たな実施団体の増加につながっていないところであり、今後は、社会福祉法人等へも積極的に本事業の紹介を行い、事業の拡大に努めてまいりたいと考えております。また、今後とも実施団体への研修会、意見交換会等を実施し、支援体制の強化を図るとともに、他都市の状況等についても引き続き研究してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.134 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
私は、お困りの子育て家庭に毎週お弁当を配達し見守るアウトリーチ型の支援は非常に効果があると思っています。概算要求での充実案はなかなか支援対象につながらないことや実施団体が増えていかないことへの課題への対応だと考えますので、他都市も研究してさらなる充実を強く求めて、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
物価高騰対策についてです。
10月27日投開票で行われた総選挙から石破政権の初めての本格的な国会論戦の場となる臨時国会が始まっています。総選挙で過半数割れした与党は、単独では法律や予算を通すことはできず、幅広い民意を酌み取り、丁寧な国会運営で国民の納得を得る論戦が求められています。物価高騰で市民生活が厳しい下で総選挙では103万円の壁と呼ばれる所得税の課税最低限度の引上げが注目されましたが、私ども日本共産党は、抜本的には大企業や富裕層に応分の負担を求めて財源をつくり、物価対策や所得の少ない方の暮らしの支えになる消費税の減税を求めています。いずれにしろ、当面の市民生活や地域経済をどう支えるのか、臨時国会で提案されている物価高騰対策の内容を明らかにするとともに、一刻も早く具体化すべきという立場から、以下伺ってまいります。
まず、本市の消費者物価指数の推移について、質問の1点目、消費者物価指数と前年同月比を全国、鹿児島市、それぞれお示しください。
質問の2点目、費目食料の中で特に前年同月比が高い上位3品目をお示しください。
質問の3点目、令和6年度のこれまでの推移の特徴をお示しください。
以上、答弁願います。
P.135 ◎答弁 産業局長(新小田洋子君)
◎産業局長(新小田洋子君) お答えいたします。
令和6年10月の消費者物価指数は、全国109.5、本市108.4で、前年同月比につきましては、全国で2.3%、本市で3.2%それぞれ上昇しております。
次に、食料の費目別で前年同月比が高い上位3品目は、果物、穀類、野菜・海草となっております。
6年4月から10月までの消費者物価指数の推移は、全国、本市ともに上昇しており、全国に比べて本市の上昇幅は0.7ポイント高くなっております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.135 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
皆さんが日々のお買物や肌で感じておられるように、本市の消費者物価指数は今年5月から前年同月比で全国を上回る伸びを示しており、穀物や果物、野菜など食生活に欠かせない品目が特に値上がりしている状況です。
次に、物価高騰の市民生活への影響について伺います。
質問の1点目、金融経済概況での市内の状況をお示しください。
質問の2点目、学校給食費を値上げした学校数と値上げ幅の昨年との比較をお示しください。
以上、答弁願います。
P.135 ◎答弁 産業局長(新小田洋子君)
◎産業局長(新小田洋子君) 日銀鹿児島支店が11月7日に発表した鹿児島県金融経済概況によりますと、県内の景気は緩やかに回復しているとされており、本市においても同様の状況にあると考えております。
以上でございます。
P.135 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) 6年度に給食費を値上げした学校数を小学校、中学校の順に申し上げますと、自校方式校では、36、11校、センター方式校では、31、24校でございます。また、1食当たりの給食費につきまして、5年度から6年度の値上げの額の平均を小学校、中学校の順に申し上げますと、自校方式校では、21.66、27.68円、センター方式校では、12.44、15.65円でございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.135 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
学校給食費はほとんどの小中学校で値上がりし、その幅は昨年の倍にもなろうかという状況です。1食約25円として月20日、10か月と計算しただけでも年間5千円の負担増です。金融経済概況は緩やかな回復基調とのことですが、当局の認識はどうでしょうか。
質問の3点目、市民生活への影響についての認識をお示しください。
以上、答弁願います。
P.135 ◎答弁 産業局長(新小田洋子君)
◎産業局長(新小田洋子君) 国の11月の月例経済報告によりますと、消費者物価の先行きについては当面上昇していくことが見込まれるとされていることから、市民生活は厳しい状況が続いていくものと認識しております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.135 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
市民生活は厳しいとの認識をお示しいただきましたので、まさに今、物価高騰対策の具体化が急がれるということを申し上げておきます。
次に、現在、臨時国会で審議中の国の令和6年度補正予算案について伺います。
質問の1点目、補正予算案における物価高騰対策の内容をお示しください。
質問の2点目、推奨メニューの内容と新しい事業をお示しください。
質問の3点目、令和6年11月22日付、重点支援地方交付金についての事務連絡の内容をお示しください。
以上、答弁願います。
P.136 ◎答弁 企画財政局長(古河春美君)
◎企画財政局長(古河春美君) お答えいたします。
国の令和6年度一般会計補正予算案では、物価高の克服のため、足元の物価高に対するきめ細かい対応として、重点支援地方交付金の追加や冬季の電気、ガス料金の負担軽減などが、また、エネルギーコスト上昇に強い経済社会の実現として、家庭・住宅の省エネ・再エネの推進やクリーンエネルギー自動車の導入支援などが盛り込まれております。
重点支援地方交付金の推奨事業メニューにつきましては、生活者支援として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯や子育て世帯支援などが、また、事業者支援として、医療・介護・保育施設、学校施設等に対する物価高騰対策支援などが挙げられおり、新たに灯油料金上昇抑制に向けた支援などが追加されております。
当該事務連絡においては、都道府県及び市町村に対し、重点支援地方交付金を活用した支援について可能な限り早期の予算化に向けた検討を速やかに進めていただくよう求めております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.136 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
国の補正予算案では、所得の少ない世帯への3万円の給付のほか、冬季の電気、ガス料金の負担軽減、地方自治体の裁量で活用できる重点支援地方交付金の追加となっています。さきの答弁でも明らかになった学校給食費への負担軽減や灯油代の補助が事業に追加されたことを踏まえ、所得の少ない世帯が安心して暖房をかけることができるような対応も検討すべきです。
この質問の最後に、国の補正予算成立後、速やかに具体化すべきと考えますが、当局の見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.136 ◎答弁 企画財政局長(古河春美君)
◎企画財政局長(古河春美君) 今後の対応につきましては、国、県の動向を踏まえ、物価高騰に直面する市民や事業者の負担を軽減するための必要な支援について、時期を逸することなく迅速に行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.136 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
市長選挙でも両候補、物価高騰対策に触れられ、市長のマニフェストでは、「不安定さを増す国際情勢などから物価高騰が続いており、その影響を特に受けている市民や事業者に寄り添った対応について、国の交付金等を活用し、適切に取り組みます」とあります。厳しい市民生活を踏まえて、年末年始でも時期を逸することなく、迷わず提案されることを強く要請し、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
災害に強いまちづくりについてです。
今年の5月26日から危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規定する盛土規制法が施行されました。静岡県熱海市での不法な盛土の崩落による土石流災害から3年、機会あるごとに議会で取り上げてまいりましたが、まず、第60号議案 鹿児島市開発行為、建築等における災害の防止に関する条例及び鹿児島市宅地開発に関する条例一部改正の件について、その内容と本格実施までの取組を明らかにする立場から、以下伺ってまいります。
質問の1点目、条例改正の目的をお示しください。
以上、答弁願います。
P.136 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) お答えいたします。
今回の条例改正は、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することを目的に、宅地造成等規制法が改正されたことを受け、関係条文を整理し、法の適切な運用を図るものでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.137 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
本市はこれまで災害の防止に関する条例等で土捨場等の独自の規制を行ってきましたが、盛土規制法の対象になったことから、条文を削除し、今後は法の下で規制されます。条例では届出制だったものが許可制となり、不法な盛土への規制が強化されます。
質問の2点目、本市は、盛土規制法の本格的な運用の基本となる規制区域案を今年7月に公表し、パブリックコメントを経て条例改正の提案となりましたが、鹿児島市宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の候補区域の設定について、以下伺います。
まず、鹿児島市における盛土規制法に基づく基礎調査に係る検討委員会での検討内容と委員意見。
次に、各区域の指定の考え方とそれぞれの区域での規制の違いをお示しください。
以上、答弁願います。
P.137 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 検討委員会においては、鹿児島市の全域を規制区域とすることや2つの規制区域の区分などについて検討いたしました。委員からは、「規制区域の指定に当たり、隣接地は県が区域指定を行うことから、市境については十分な調整を図るように」との意見があったところでございます。
指定の考え方については、宅地造成等工事規制区域は、市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼし得るエリア、特定盛土等規制区域は、市街地や集落などから離れているものの地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼし得るエリアとなっております。
また、規制の違いについては、宅地造成等工事規制区域内では、盛土により高さ1メートルを超える崖が生じる工事など、特定盛土等規制区域内では、盛土により高さ2メートルを超える崖が生じる工事などで、許可が必要となる盛土等の規模が異なることでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.137 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
市境で自治体同士の矛盾が出ないよう委員意見が出されていることが分かりました。また、規制の内容についてもそれぞれ1メートル、2メートルを超える崖が生じる工事は許可が必要と厳しいものになっていることが分かりました。
次に、各地域での住民説明会の参加人数と特徴的な意見。
あわせて、パブリックコメントの結果をお示しください。
また、これらについての当局の受け止めと今後の対応をお示しください。
以上、答弁願います。
P.137 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 住民説明会は7月20日から26日にかけて、桜島、吉田、喜入、松元、郡山及び中央、谷山地域の7つの会場で開催し、参加人数は順に、1、13、5、2、5、21、14の計61名でございました。参加者からは、2つの区域の違いや申請手続に関する質問などがあったところでございます。
パブリックコメントについては2名から3件の意見がありましたが、候補区域の設定に関する意見はございませんでした。
住民説明会やパブリックコメントにおいて候補区域に対する意見はなかったことから、市全域を規制区域に指定することとしております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.137 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
いずれも候補区域への意見はなかったとのことでした。パブリックコメントの意見にはこれまで届出制だったことに対する行政の甘さへの厳しい指摘もあることから、当局としても不法な盛土による被害を二度と出さない決意で臨まれるよう要請しておきます。
本市は来年4月から盛土規制法の本格的な運用を始めますが、福島県では、住宅地のそばに22メートルの違法な盛土が造成され、災害の危険性があるにもかかわらず、改善の見込みがないことから行政代執行を行いました。福島県は法の適用を前倒しし、全国で初めてとなる盛土規制法違反の容疑で刑事告発となりました。このような事例で私が懸念するのは、本格的な運用の前の業者の駆け込み申請と行政の目をかいくぐろうとする不法な盛土です。
この質問の最後に、本格的な区域の指定と法施行までの課題と本市の対応をお示しください。
以上、答弁願います。
P.138 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 本市においては、令和7年4月1日に規制区域を指定することとしておりますが、現在のところ、指定前の駆け込み申請の傾向は見られません。今後は適切に法の運用が図られるよう市民や関係団体等に周知を行ってまいります。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.138 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
駆け込み申請は今のところ見られないとのことですが、福島県での事例を踏まえ、本格運用までしっかりと対応されるよう強く要請いたします。
次に、市長のマニフェストに、「能登半島地震の教訓を踏まえた防災対策を強化し、災害に強いまちづくりを進めます」とあることから、能登半島地震の教訓を踏まえた防災対策について伺います。
質問の1点目、能登半島地震での建築物のくい基礎の損傷の状況と輪島市でのビルの倒壊についての認識をお示しください。
質問の2点目、ビルの倒壊における国の調査の経過と到達点をお示しください。
質問の3点目、南海トラフ地震における本市の建物被害推計とくい基礎の被害の想定の有無をお示しください。
以上、答弁願います。
P.138 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 能登半島地震における国の調査によると、くいの損傷が原因と推測される鉄筋コンクリート造等の建築物の被害が複数確認されており、そのうち転倒、崩壊に至った建築物はお触れの1棟でございます。
国は、建築物構造被害の原因分析を行う委員会において、建築物の被害要因の分析を行っているところであり、令和6年11月に中間取りまとめを公表しております。当委員会は、今後引き続き分析を行い、対策の方向性を検討するとのことでございます。
南海トラフ地震における本市の建物被害は、県の地震等災害被害予測調査報告書によると、全壊・焼失が2,300棟、半壊が8,200棟と推計されており、くい基礎の被害の想定はございません。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.138 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
輪島市で7階建てのビルが倒壊した事例は衝撃的でした。能登半島地震では建物を支えるために地中に打たれたくいが折れるなど、地下構造物が損傷した可能性が懸念されています。建築物の基礎、地盤被害について、国土交通省国土技術政策総合研究所などが行っている調査研究も中間取りまとめが公表されたものの、さらなる調査が必要とされているようです。また、南海トラフ地震の推定にはくい基礎被害の想定は入っていないことが分かりました。直下型の強い地震に備え注視する必要があるのではないでしょうか。
質問の4点目、くい基礎における建築基準法の耐震基準の経過と現在の構造計算の根拠をお示しください。
質問の5点目くい基礎の耐震基準についての当局の課題認識をお示しください。
以上、答弁願います。
P.138 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) くい基礎の耐震基準は、昭和53年の宮城県沖地震の被害を踏まえ、59年に地震力を考慮したくいの設計指針が示されましたが、法的拘束力はなく、平成13年の法改正時に告示に位置づけられたことで義務化されております。
課題認識については、くいの損傷により被害が生じたと推測される建築物のうち、1棟が現在のくい基礎の基準適用以降に建設されていることから、国の分析結果等を注視してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.138 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
災害のたびに教訓を踏まえて改正されてきた建築基準法ですが、くい基礎の耐震設計が明確に義務づけられたのは2001年のことで、高さ60メートル以上の大規模な建物を除いて、震度5強程度の想定にとどまっているようです。また、その根拠は公示に基づくとのことですが、場所によって違う地盤の影響を考慮しなければならないという困難さと埋めてしまえば確認ができないことが課題ではないでしょうか。輪島市の事例では軟弱地盤でのくい基礎の損傷が複数見られたとのことですが、市長選での桂田候補のマニフェストには、「南海トラフ等の巨大地震に備え、液状化の危険性が高い場所への高層建築物を規制します」が掲げられています。
これまでの質疑を踏まえて、液状化が懸念される地域での高層建築物については規制や液状化の可能性の厳格な判定が必要ではないかと考えますが、見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.139 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 液状化による被害につきましても、国において今後、建設年代との関係を分析予定であることから、その動向を注視してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.139 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
本市は液状化ハザードマップを見ても、海岸沿いに液状化危険度が極めて高い地域が広がっています。また、輪島市のビルの倒壊を調査した近畿大産業理工学部の鉄筋コンクリート構造の専門家の津田教授は、耐震基準の新旧を問わず、くいに問題があれば大地震によるビルの倒壊は全国どこでも起こり得ると警鐘を鳴らしています。国の動向を注視しながらもこの課題に対する他都市の動向等を調査されるよう強く要請し、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
吉野地域のまちづくりについて、第67号議案 令和6年度鹿児島市一般会計補正予算(第6号)中、款土木費、項土地区画整理費、目吉野第二地区土地区画整理事業費の内容を伺います。
質問の1点目、補正予算の事業費と内容をお示しください。
以上、答弁願います。
P.139 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 吉野中学校前の県道鹿児島吉田線の道路築造工事に係る事業費として、1億5,500万円の補正予算を計上しております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.139 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
吉野中学校前の県道の拡幅工事の増額補正ということが分かりました。これまでの質疑でこの工事は3年かかるということから、少しでも工期の短縮につながればと考えるところです。
これまで工期の長さから中学校の行事や生徒の安全対策を求めてまいりましたが、質問の2点目、今後の進捗と中学校行事、特に体育大会への対応をお示しください。
質問の3点目、工事現場北側は朝夕の生徒の往来が多い場所ですが、現在、歩道が確保できない状況となっています。生徒の登下校の安全対策をお示しください。
以上、答弁願います。
P.139 ◎答弁 建設局長(日高謙次郎君)
◎建設局長(日高謙次郎君) 道路築造工事は、現在、北側のおよそ40メートル区間で既設擁壁の撤去と新たなコンクリート擁壁の設置などを行っており、当区間の完了後は残る南側のおよそ60メートル区間の工事に取り組むこととしております。なお、中学校行事への対応については、体育大会の開催等に向けて工事スケジュールの調整など、引き続き中学校と綿密に連携してまいります。
安全対策については、現在、工事区域にカラーコーンや照明を設置するとともに、歩行者が安全に通行できるよう複数の看板を設置して注意喚起を図るなどの取組を行っております。今後も生徒の登下校への影響が最小限となるよう中学校との協議を継続して行うとともに、生徒や保護者への周知を丁寧に行うなど、安全管理の徹底に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.140 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
体育大会をこれまでどおり実施するにはグラウンドの埋め戻しが必要ですので、しっかりと中学校と連携して進めていただくとともに、生徒の登下校には特段の配慮をしていただきますよう強く要請いたします。
以上で、私の個人質疑の全てを終わります。