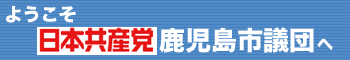P.5 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一員として質疑を行います。
本日の臨時会には、専決処分に関する2つの議案と補正予算等に関する4つの議案が提案されています。
臨時会の質問は提案された議案に限るとされていますので、5つの議案について、以下質問してまいります。
初めに、桜島学校新築に係る工事に関して3つの議案が提案されていますので、質問します。
質問の1点目、7年度の桜島学校整備推進事業の一環として、第3号議案、第4号議案、第5号議案の各工事請負契約締結の内容をお示しください。
質問の2点目、第5号議案の工事請負契約を随意契約とした理由として、地方自治法施行令上の規定の内容をお示しください。
質問の3点目、これらの3つの契約に付随するその他の工事の内容をお示しください。
以上、それぞれ答弁願います。
P.6 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) お答えいたします。
桜島学校の工事請負契約の内容につきまして、第3号議案の本体その他工事は、公民館や児童クラブを併設する校舎等の建設工事を行うもので43億9,450万円、第4号議案の電気設備工事2工区は、同施設の受変電設備や電灯設備等の工事を行うもので3億250万円、第5号議案の電気設備工事1工区は、同施設の電灯設備や動力設備等の工事を行うもので2億7,390万円でございます。
第5号議案につきましては、総合評価一般競争入札の結果、予定価格に達しなかったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の「再度の入札に付し落札者がないとき」及び同条第2項の「予定価格その他の条件を変更することができない」の規定に基づき、随意契約としたところでございます。
その他の工事につきましては、給排水衛生設備工事が2件、空気調和設備工事が2件で、予算額は10億3,577万4千円でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.6 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
3つの工事請負契約を合わせて総額49億7,090万円の契約が締結されたと確認いたします。第5号議案の随意契約については、地方自治法施行令上の規定に基づいて執行されていることを理解いたしました。また、3つの契約に付随して、今後、給排水や空調等の契約が4件残されていることも確認いたします。
今回の工事請負契約の締結成立は三度目の正直と報じられていますが、これまでの工事請負契約の経過と入札不調の要因をお示しください。
答弁願います。
P.6 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) これまでの工事につきましては、当初、県内事業者の受注機会確保の観点から4工区に分けた上で6年7月に入札を実施しましたが、不調となり、工事費や施工面の観点から2工区に変更するなど、全体的に工事を見直し、8月に改めて公告を行い、10月に入札を実施しましたが、再度不調となったところでございます。不調の要因について、入札参加者によりますと、運搬費や資材費等の高騰や民間も含めた建築工事が活発な状況の中で技術員や作業員の確保が難しくなっていることなどがあるとのことでございました。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.6 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
過去2度にわたる入札不調の要因を分析し、その対応について検討されてきたと思いますが、入札不調に対するこれまでの対応と今回の工事請負契約締結の要因をお示しください。
続いて、今後の工事スケジュールをお示しください。
以上、答弁願います。
P.6 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) 過去2回の入札不調を踏まえ、設計単価の見直しや技術員、作業員の確保等のため工期を5か月延長するとともに、工区を1つにするなどの対応により落札されたものと考えております。
今後の工事スケジュールにつきましては、議決後速やかに本契約を締結し、5月末に着工、9年2月に竣工、4月からの供用開始を予定しているところでございます。なお、桜島学校は、既存の桜島中学校の校舎を使用して8年4月に開校することとしております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.7 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
この間、繰り返されてきた入札不調の要因を明確にしてそれぞれに対応してきたことで今回の契約締結にこぎ着けることができたと思われます。人材確保のために一部要件緩和も行われているようですが、工事の安全と質の確保に努めながら21か月に及ぶ工事が円滑に進められることを要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
第6号議案 令和7年度鹿児島市一般会計補正予算(第1号)において、公務災害に対する損害賠償額に関して7,960万円の補正予算が提案されていることについて、以下質問します。
初めに、公務災害に係る損害賠償について、質問の1点目、公務災害の概要と認定内容。
質問の2点目、発症から現在に至る経緯と補正予算額の内訳及び今後のスケジュール。
以上、まとめて答弁願います。
P.7 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) 公務災害に係る損害賠償につきましては、2年7月、指導主事が教職員を対象とした校内研修の指導中に脳出血を発症した件について、3年4月、当該指導主事から地方公務員災害補償基金へ公務災害の認定請求が提出され、4年3月、公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな疾病と認められるとされ、一時金や障害補償年金等の支給を受けております。
その後、5年10月、当該指導主事から安全配慮義務の懈怠等として損害賠償額約1億7,620万円の訴状が提出され、和解協議を経て、6年12月、鹿児島地方裁判所から損害賠償額7,300万円の和解案が示され、7年4月、第10回弁論準備手続において仮和解となったところでございます。補正予算額の内訳は、損害賠償額7,300万円と本市の弁護士費用660万円となっております。今後のスケジュールにつきましては、6月定例会において和解議案を提出することとしております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.7 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
令和2年7月に市教育委員会勤務の指導主事が公務中に倒れ、令和4年3月、地方公務員災害補償基金が原告の公務災害認定を行うまで1年9か月が経過していますが、それから1年7か月後の令和5年10月に本市の安全配慮義務の責任を問う訴状が裁判所に提出され、その後の審議を経て本年4月に仮和解が成立し、今回の補正予算の提出に至っていることと理解いたしました。
次に、なぜ公務災害が発生したのか、再発防止を求める立場から質問します。
質問の1点目、原告の発症前の時間外勤務とその要因をお示しください。
答弁願います。
P.7 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) 疾病の発症前30日間における時間外勤務の合計は自宅作業時間も含め138時間45分であり、訴状によりますと、市立小中学校の学力向上に向けての分析や対策、授業研究や校内研修の準備、指導・助言等の通常業務に加え、コロナ禍による一斉休校に係る学習保障の問合せへの対応や学校再開後の校内体制の指導のほか、市議会関係資料の作成等に従事していたとのことでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.7 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
原告が倒れられた令和2年は、教育委員会の事務局職員の皆さんは通常業務だけでなく新型コロナ対応で追われる大変な時期であったと推察されます。原告の直前1か月の時間外勤務は138時間45分であったことは、公務災害の認定申請をしていく中で自宅での仕事も含めて把握されたと考えられますが、労働者の過労死認定の時間外勤務について、厚生労働省によりますと、発症前1か月間に100時間を超える時間外労働、または発症前2か月から6か月の平均が月80時間を超える時間外労働とされています。
そこで、質問の2点目、公務災害後の当該課の事務局職員の時間外勤務の現状と勤務時間管理及び再発防止対策についてお示しください。
答弁願います。
P.8 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) 公務災害が発生した当時の30日間の当該課指導主事の時間外勤務の平均は約75時間でありましたが、6年度は約44時間でございます。現在は教育の質を確保しながら業務改善に対する意識改革を進めるとともに、職員の増員による担当業務の平準化やICTを活用した業務の見直し等により時間外勤務の縮減や効率化を図ってきており、教育委員会全体として職員が心身ともに健康で安心して働ける職場環境づくりに取り組んでいるところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.8 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
原告だけでなく、当時、当該課の指導主事の皆さんも平均で月75時間の時間外勤務であったことは、当該課全体に慢性的な時間外勤務が続いていたことが推察されます。その後は月平均44時間に減少し、指導主事の増員も行い再発防止に努められていることが示されました。教育委員会は今回のような公務災害を発生させないために教職員の働き方改革の指揮を執る役割を担っていると思います。
そこで、今回の国家賠償請求事件を教訓にした教職員の働き方改革の推進に対する見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.8 ◎答弁 教育長(原之園哲哉君)
◎教育長(原之園哲哉君) 教職員の働き方改革につきましては、市立学校における業務改善アクションプランに基づき継続的に業務改善に係る意識改革を進めるよう指導を行ってきており、定時退校日の定着、校務DXの推進やICT等を活用した事務処理の効率化等による効果もアンケート調査などにより確認されております。今回の案件なども踏まえ、引き続き、質の高い教育を担保しながら時間外勤務のさらなる縮減に向けて学校の勤務実態や業務改善の状況を把握し、実効性のある取組例の積極的な情報提供を行い、教職員の心身の健康の維持・増進を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.8 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
原告の弁護を担当した弁護士の公式ホームページを拝見しますと次のようなことが述べられています。「給特法の下、公立学校教員の時間外勤務は、勤務時間として評価されず、自主的・自発的勤務として「整理されてきた」状況の下で、勤務時間は適正に把握されてこなかった。したがって公務災害認定で終わってしまっては、実効ある職場の長時間勤務の是正や過労死等の予防にはつながらない。責任の問題を問うことなしには、勤務時間の是正、予防は実効性のあるものにならない」と述べています。
今回の公務災害は、教育委員会の内部で発生した事案であることを重く受け止め、自らの働き方改革も進めながら、本市の教職員の働き方改革の一層の推進に取り組まれることを強く要請して、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
第2号議案 専決処分の承認を求める件(鹿児島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について質問します。
初めに、今回の条例改正が専決処分されたことについて、質問の1点目、条例改正の内容とそれぞれの効果をお示しください。
質問の2点目、地方税法施行令の一部改正に至る国会審議の経過と専決処分に至った理由をお示しください。
質問の3点目、県内他市、九州県都市及び中核市における課税限度額の引上げ、専決処分の実施状況をお示しください。
以上、それぞれ答弁願います。
P.8 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) お答えいたします。
今回の条例改正は、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額の引上げと、5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の基準の引上げを行うもので、このことにより、一定の負担能力がある所得層の方々に応分の負担を求めるとともに、低所得者に対する負担軽減措置を拡充することで、負担能力に応じた公平性が確保されるものと考えております。
国会では、2月4日に地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案が衆議院で受理され、3月31日の参議院可決後同日に改正地方税法施行令が公布されております。専決処分については、課税限度額の引上げの遡及適用は不利益となること、軽減判定所得の基準の引上げは法に基づく軽減措置であること、また、6月中旬の当初納税通知書の発送に向け、5月には本賦課処理を行う必要があることなどから総合的に判断し行ったものです。
県内他市では18市全市で、また本市を含む税方式を採用している九州県都市では6市全市で、中核市では28市のうち18市で専決処分されております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.9 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
専決処分されている課税限度額の引上げは、一定の所得を有する方には負担増となる一方、軽減判定所得の基準改正は、低所得者の負担軽減を図るための条例改正であることを確認いたします。本市と同じ税方式の県内他市、九州県都市では本市と同様に全て専決処分を行われているようですが、本市と同様に専決処分を行った18市以外の10市では議会での議決あるいは7年度は改正しない措置が中核市では講じられているようであります。
なお、専決処分に至る経過の中で地方税法の改正に触れられましたが、そこで質問いたします。
質問の4点目、国が地方税法を改正しても、地方自治体の裁量で国保税の軽減判定所得の基準のみを選択し改正することは可能か、本市の認識と対応をお示しください。
質問の5点目、課税限度額の引上げは市民に負担増をもたらすことから、なぜ市民生活に直結する条例改正を専決処分されたのか、見解をお示しください。
以上、それぞれ答弁願います。
P.9 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 軽減判定所得の基準のみを改正している都市もあるようですが、本市では、国保財政が厳しい状況にあること等を踏まえ、課税限度額についても地方税法施行令に定める額と同額としております。
専決処分は、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときなどに行うもので、市民に直接影響を及ぼす案件については慎重な対応が必要であると考えております。今回は、改正地方税法施行令が年度末の3月31日に公布されており、7年度の本賦課処理に向け施行令を踏まえた条例改正を行う必要があったことから専決処分としたところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.9 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国保税の負担軽減につながる軽減判定所得の基準改正は、地方税法上、改正が義務づけられていますので、全ての自治体で実施されることになりますが、課税限度額の引上げは、地方税法で同施行令に定める額を超えることができないと規定しているだけです。事実、7年度、課税限度額の引上げを行わない中核市があるように、軽減判定所得の基準改正のみを実施することは可能であったということは指摘をしておきたいと思います。
次に、さきの第1回定例議会で提案された令和7年度予算の中で16年ぶりに国保税率の大幅な改定があり、国保税の大幅な負担増が6月から実施されようとしています。この国保税率の改定が今回専決処分された課税限度額の引上げによる負担増と法定軽減による負担軽減に与える影響について見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.9 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 7年度の税率改定により、課税限度額の改正では限度額に達する所得水準が低くなること、軽減判定所得の基準改正では税額が増えることで軽減額も増加するなど一定の影響があると認識しております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.10 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
影響があると答弁されましたので、今後の質疑の中で明らかにしていきたいと思います。
まず、7年度の軽減判定所得の基準改正の影響について質問してまいります。
質問の1点目、基準改正の内容をお示しください。
質問の2点目、基準改正に伴う5割軽減、2割軽減の対象世帯数をお示しください。
以上、それぞれ答弁願います。
P.10 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 改正内容は、5割及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定基準を緩和するもので、5割軽減については、算定する際に被保険者数に乗じる金額29万5千円を30万5千円に、2割軽減は、54万5千円を56万円にそれぞれ引き上げ、軽減額の拡大を図るものです。
新たに軽減の対象となる世帯数は、5割軽減、308世帯、2割軽減、362世帯と見込んでおります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.10 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国保の法定軽減制度は、被保険者の申請の必要はなく、一定の所得水準以下の国保世帯の均等割と平等割が7割、5割、2割、それぞれ自動的に軽減される制度であります。所得に関係なく世帯人員数に応じて賦課される均等割と1世帯に一律に賦課される平等割の負担を軽減するための国保世帯の所得判定の基準が今回の改正により、5割軽減の場合、現行の被保険者1人当たり29万5千円を30万5千円に、2割軽減の場合、同じく54万5千円を56万円に改正することにより、法定軽減の対象となる世帯は合わせて670世帯であることが示されました。
では、今回の基準改正によりどのような所得水準が法定軽減の対象となるのか確認します。
質問の3点目、基準改正に伴い2割軽減の対象となる世帯人員数ごとの所得水準の下限、上限をお示しください。
質問の4点目、法定軽減の対象の有無による国保世帯数と割合を改正前との比較でお示しください。
以上、それぞれ答弁願います。
P.10 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 2割軽減となる世帯人数ごとの所得額は、1人、73万5千円を超え99万円以下、2人、104万円を超え155万円以下、3人、134万5千円を超え211万円以下、4人、165万円を超え267万円以下、5人、195万5千円を超え323万円以下、6人、226万円を超え379万円以下となります。
法定軽減の対象となる世帯数と割合は、改正の前と後でそれぞれ4万3千世帯、57.0%、4万3,400世帯、57.5%、法定軽減の対象とならない世帯数と割合は、同様に3万2,500世帯、43.0%、3万2,100世帯、42.5%と見込んでおります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.10 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国保の法定軽減制度は、所得の高低に関係なく、ひとしく賦課される均等割、平等割を減額する制度ですので、所得判定の基準を改正して世帯人員数に応じて所得水準の範囲を拡大していくことが求められています。
今回の基準改正により2割軽減の所得水準が1人世帯では99万円、6人世帯では379万円まで軽減対象の範囲が拡大したことが明らかにされました。5割軽減も同様に所得水準の範囲が広がっています。しかし、法定軽減の対象とならない国保世帯が今回の基準改正でも42.5%を占めています。本市としても国に対してさらなる所得判定の基準改正を要請し、法定軽減の対象範囲を拡大していただくよう要望しておきます。
次に、先ほどの質問で7年度の国保税率の改定が今回の基準改正に影響を与えていると答弁されましたので、7年度、国保税率を改定した場合と改定しない場合の国保税額及び7年度基準改正を適用した場合の影響額について、3点質問します。
質問の1点目、まず、7年度、国保税率の改定による均等割、平等割の改定内容を6年度との比較でお示しください。
答弁願います。
P.11 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 税率改定後の税額及び6年度からの増減は、課税区分ごとに均等割額、平等割額の順に、基礎課税額、3万700円、9,700円の増、2万2,600円、700円の減、後期高齢者支援金等課税額、1万700円、4,500円の増、7,800円、700円の増、介護納付金課税額、1万1,100円、3,700円の増、6,300円、100円の減となります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.11 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
改正前と比較して1世帯に一律に賦課される平等割は、医療分の増加はゼロ、介護分は100円減でありますが、世帯人員数に賦課される均等割は、医療分で1人当たり1万4,200円の負担増、40歳から65歳未満の介護分も3,700円の負担増であります。5割軽減、2割軽減がなければ所得に関係なくこれらを全額負担することになり、特に子育て世帯は大変であります。
そこで、このような税率改定が今回の所得判定基準の改正により7年度から新たに法定軽減制度の適用を受ける国保世帯にはどのような影響があるのかを確認します。
質問の2点目、7年度に2割軽減から5割軽減の対象となる軽減判定の際の15万円控除後の年金所得104万円、65歳夫婦の2人世帯の場合。
質問の3点目、7年度から初めて2割軽減の対象となる夫43歳、給与所得267万円、妻42歳、無職、中学生1人、小学生1人の4人世帯の場合。
以上、この2つのケースについて、それぞれお示しください。
答弁願います。
P.11 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) お触れの2人世帯の6年度の税額は14万8,300円で、7年度基準改正を適用した場合、12万2,900円となり、2万5,400円の負担減、7年度の税率及び基準改正を適用した税額は14万円で、8,300円の負担減となります。
お触れの4人世帯の6年度の税額は45万1,500円で、7年度基準改正を適用した場合、41万9,400円となり、3万2,100円の負担減、7年度の税率及び基準改正を適用した税額は46万5,400円で、1万3,900円の負担増となります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.11 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
ただいま2つのケースについてお示しいただきましたが、7年度税率の改定がなければ2つのケースともいずれも大幅な負担軽減につながったケースであります。しかし、2割軽減から5割軽減の対象となった65歳夫婦のケースについては、税率が改定されても6年度と比較して8,300円の負担軽減となってはおりますが、2割軽減の対象となった子育て4人世帯のケースでは本市独自に小学生の均等割額3万700円を2分の1減額しても1万3,900円の負担増となっているわけであります。
したがって、このパネルを御覧ください。
令和6年度から既に5割、2割軽減の対象となっている2つの国保世帯のモデルケースについて、7年度税率改定の影響を検証しました。
1つ目は、5割軽減の対象となる年金所得100万円の65歳夫婦の2人世帯です。65歳ですから介護保険料は別途徴収されます。6年度税率による国保税額はこの緑の部分で10万2,700円ですが、税率改定によって7年度の国保税額は11万9,200円となるわけです。税率改定によって1万6,500円の負担増、116%の負担増となってしまいます。
2つ目のケースは、2割軽減の対象となっている給与所得200万円の40代の夫婦、小学生、中学生の4人世帯であります。6年度税率による国保税はこの緑の部分で33万2,300円ですが、税率改定によって7年度の国保税額は37万4,900円となり、4万2,600円の負担増、113%の負担増となってしまいます。
この2つのモデルケースの結果も示しているように7年度国保税率の改定によって、法定軽減の対象世帯のうち6年度より負担増となる世帯があることへの当局の見解をお示しください。
答弁願います。
P.11 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 今回の改正は対象世帯の負担軽減を図る観点で行うもので、税率改定前と比較した場合、お触れのような世帯もありますが、御理解をいただけるよう努めてまいります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.12 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
7年度、2割から5割軽減の適用を受ける国保世帯の中で、ただいま2つのケースをお示ししましたように7年度の税率改定によって、所得割、均等割の大幅な引上げによって法定軽減の対象となる国保世帯の大多数が負担増になることを当局は重く受け止めるべきと考えます。
次に、一定の所得水準の方にとっては負担増となる7年度の課税限度額の引上げの影響について、以下質問してまいります。
質問の1点目、引上げの内容をお示しください。
質問の2点目、引上げに伴い負担増となる実世帯数とその割合をお示しください。
以上、答弁願います。
P.12 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 改正内容は、基礎課税額を65万円から66万円に、後期高齢者支援金等課税額を24万円から26万円に引き上げるものです。
改正の対象となる世帯数、割合は、基礎課税額、795世帯、1.05%、後期高齢者支援金等課税額、738世帯、0.98%と見込んでおります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.12 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
7年度の改正により課税限度額は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額を合わせて40歳から65歳未満の国保世帯は最大109万円までは課税され、これを超える額については課税されない措置が講じられることになります。対象となる世帯数がそれぞれ示されましたが、国は課税限度額を引き上げる際、その方針を示しています。
そこで、質問の3点目、国が課税限度額を引き上げた理由と課税限度額世帯の割合についての方針をお示しください。
答弁願います。
P.12 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) お触れの理由等は、国において課税限度額の超過世帯の割合は、医療保険料に関する国民の公平性を確保する観点から1.5%に近づけるよう段階的に引き上げる運用上のルールを設けておりますが、7年度の全国水準における超過世帯割合は、改正前において基礎課税分及び後期高齢者支援金等課税分の超過世帯割合が上昇し、1.59%となることが見込まれたため、合計の限度額超過世帯を1.5%に近づけることを念頭に置きつつ、後期高齢者支援金等分のバランスを整える観点から、基礎課税分が1万円、後期高齢者支援金分が2万円引き上げられたところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.12 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国は、課税限度額世帯の割合を1.5%に近づけることを目標にしている方針が示されましたが、本市の現状を確認したいと思います。
質問の4点目、課税限度額の該当世帯数の7年度推計の国、本市の割合を基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額について、それぞれお示しください。
答弁願います。
P.12 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 課税限度額の超過世帯数の割合は、課税区分ごとに国、本市の順に、基礎課税額、1.69%、1.03%、後期高齢者支援金等課税額、1.82%、0.85%、介護納付金課税額、0.98%、1.68%と見込んでおります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.12 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
国は、医療分、介護分を合わせて課税限度額世帯の実質的な割合を1.5%にするために課税限度額を引き上げる措置を行っています。しかし、ただいまの答弁で示された本市の割合は国の基準を既に下回っていると考えます。
そこで、質問の5点目、国が示す課税限度額の割合を本市の割合は既に下回っていることへの見解をお示しください。
答弁願います。
P.13 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 国は、限度額の超過世帯の割合を1.5%に近づける方針で限度額を改正しておりますが、本市では、国保財政が厳しい状況にあること等を踏まえ、施行令に定める額と同額に改正してきております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.13 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本市独自の判断をされているようですが、課税限度額の引上げを決定するのは国であります。それは課税限度額世帯の割合の全国的に平均的な実態を踏まえて改正の有無が判断されており、地方税法上も国が決めた課税限度額を地方自治体に義務づけていないわけです。したがって、本市の現状は国が求める1.5%の基準をクリアしていると考えることから、引上げを見送るべきであったと考えます。
次に、課税限度額に到達する所得水準について質問します。
質問の6点目、改正に伴い課税限度額に到達する世帯人員数、1人、6人ごとの所得水準とその要因について、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額、それぞれお示しください。
答弁願います。
P.13 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 今回の改正に伴い課税限度額に到達する所得額は、世帯人数ごとに基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の順に、1人、791万1千円、881万6千円、651万円、6人、601万9千円、695万8千円、429万9千円となります。世帯人数により所得水準に差があるのは、世帯ごとに被保険者数に応じて負担していただく均等割額によるものです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.13 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
世帯人員数が多い世帯ほど課税限度額の対象となる所得水準が低くなる要因は、世帯人員数に賦課される均等割額が増加し、その分だけ所得水準は低くなるからであります。したがって、課税限度額の引上げは所得の低い多人数世帯ほど所得に対する負担率が重くなる制度であります。
次に、7年度税率の改定が課税限度額の引上げに影響を与える点について質問します。
質問の7点目、7年度、課税限度額引上げの適用をした場合の税率改定しない場合、改定した場合の国保税額と課税限度額を超える額について2点質問します。
1点目、7年度から基礎課税の上限が66万円となり、単身者の場合、その所得水準は先ほどの答弁のとおり791万1千円であります。そこで、給与所得791万1千円の60歳、1人世帯の場合についてお示しください。
答弁願います。
P.13 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) お触れの1人世帯で7年度課税限度額を適用した場合の税額と課税限度額を超える額は、税率改定前が102万500円、2万3,300円、税率改定後は106万3,900円、3万5,100円となります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.13 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
税率を改定したことにより7年度の税額が増加し、つまり負担増となっていますが、課税限度額を超える額も1万1,800円増加しています。
そこで、2点目、課税限度額の引上げが課税限度額を超える額の削減にならないことへの見解をお示しください。
答弁願います。
P.13 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 今回の改正は、保険税負担の公平性の観点から一定の負担能力がある所得層の方々に応分の負担を求めるものであり、6年度と比較した場合、改定前の税率が低かったことから、お触れのような状況にございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.13 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
課税限度額の所得水準を超えている被保険者の場合、医療分の引上げに相当する3万円の負担増はありますが、税率改定で引き上げられた分は課税限度額を超える額として処理されることになり、高額所得者ほど賦課できない国保税が増えるという問題が残されることになります。
次に、課税限度額の対象となる所得階層の国保税の滞納について質問します。
質問の8点目、5年度、6年度の所得階層別の滞納世帯数と国保世帯数に占める割合、滞納総額について、所得600万円超700万円以下、所得700万円超800万円以下、所得800万円超の所得階層について、それぞれお示しください。
答弁願います。
P.14 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 所得階層別の滞納世帯数、国保世帯数に占める割合、滞納総額は、5年度は決算、6年度は令和7年5月13日時点で順に、600万円を超え700万円以下では、23世帯、8.5%、910万円、44世帯、14.8%、1,820万円、700万円を超え800万円以下では、23世帯、11.1%、1,210万円、25世帯、12.7%、1,070万円、800万円超では、39世帯、5.7%、2,350万円、47世帯、6.5%、2,360万円です。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.14 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
課税限度額の対象となる所得階層の国保税の滞納世帯は、課税限度額を2万円引き上げた6年度は5年度より滞納世帯数も滞納額も増加していることが明らかにされました。7年度は3万円引き上げることによって6年度より滞納世帯がさらに増えることが懸念されます。課税限度額の引上げには先ほどの質疑でも示したように所得階層のより低い多人数世帯から課税限度額の対象となる反面、より高額の所得者の負担率は低いままに据え置かれるという構造的な問題があり、全国市長会もこの点の是正について検討を求めています。
そこで、質問の9点目、令和4年6月1日、第92回全国市長会議で、課税限度額については、市町村の意見を十分に聞きながら、所得階層に応じた設定も含め根本的な在り方について検討することが決定されていることについて、本市の見解をお示しください。
答弁願います。
P.14 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) お触れの全国市長会の提言は、課税限度額設定の制度的な見直しの必要性についてのものと認識しております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.14 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
全国市長会としては応能負担の原則に従って所得階層に応じた税率の検討を求めており、課税限度額を段階的に引き上げる現行方式を見直す時期に来ていると思います。このような点からも今回の課税限度額の引上げは問題であります。
次に、7年度国保税率の改定による7年度予算への影響額について質問します。
質問の1点目、税率改定に伴い10億3千万円の負担増となった当初予算に今回の専決処分の影響額は反映されているのかしていないのか、その有無をお示しください。
質問の2点目、5割軽減、2割軽減の法定軽減による負担軽減の影響額をお示しください。
質問の3点目、課税限度額引上げによる負担増の影響額をそれぞれお示しください。
答弁願います。
P.14 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 専決処分関係の改正については、当初予算案の提案時点においては改正地方税法施行令が公布されていなかったことから歳入予算に反映していないところです。
軽減判定所得の基準改正による影響額は、5割軽減1,437万7千円、2割軽減679万2千円と見込んでおります。
課税限度額の改正による影響額は、基礎課税額785万1千円、後期高齢者支援金等課税額1,377万7千円と見込んでおります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.14 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
今回の専決処分による影響額は当初予算には含まれていないということですが、5割軽減、2割軽減による負担軽減の影響額は合わせて2,116万9千円だと答弁されました。しかし、この影響額は7年度の税率に改定した上で7年度の法定軽減により軽減された影響額であり、必ずしも6年度の税額よりも減少し、負担軽減になっているわけではありません。課税限度額の引上げに伴う2,162万8千円の影響額を踏まえると、市民の負担が増える専決処分であることが明らかになりました。
したがって、法定軽減による実質的な負担軽減が見込めない中で、7年度の国保税の収納率の見込みと7年度の税率改定により大多数の国保世帯が負担増となることへの見解をお示しください。
答弁願います。
P.15 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 7年度の現年課税分の収納率は92.5%を見込んでおります。今年度の税率改定は、厳しい財政状況の中、国や県の方針に基づき本市国保を安定的に運営するために実施するもので、被保険者の皆様の負担が増えることにつきましては、御理解いただけるよう引き続き丁寧な説明等に努めてまいります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.15 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
7年度の税率改定により国保税の負担が増えることによって当局は収納率が低下することを見込んでいるようであります。滞納者が増えるということは、医療を受けることができない市民が増えることにつながり、命に関わる問題であります。丁寧に説明し理解を求めるだけではなく、国保税の減免制度を拡充し、医療を受ける保障を最優先にした対応を行うべきではないでしょうか。
また、今回の専決処分については、これまでの質疑で明らかなように、第1に、法定軽減のための基準改正は7年度税率を改定したことによって法定軽減の対象となる世帯の大多数が6年度よりも負担増となり、低所得者の負担軽減のための基準改正とは言えないということ。第2に、課税限度額の引上げについては、課税限度額世帯の割合が本市では国の基準を既に下回っており、引き上げる必要はないこと。また、引上げによる負担増は、所得の低い多人数世帯ほど負担率が高くなる反面、より高額の所得階層の負担率は低くなり、応能負担の原則に反していること。しかも7年度税率改定によって限度額を超え賦課されない税額が増加する矛盾が拡大すること。
以上の問題点を持った専決処分であることを申し上げ、私の質疑を終わります。