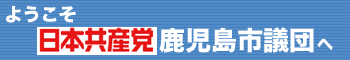P.22 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
市長の政治姿勢について伺います。
本年第1回定例会において私が米高騰の要因を伺ったところ、米不足であるということはお認めにならず、「円滑な流通に支障が生じている状態」などと国の見解をそのまま示されました。ところが、その後も米価の高騰は止まらず、本市の米価は4月時点で5キロ当たり4,649円もの高値となっています。
そこで伺います。
令和2年度産の古古古古米を放出せざるを得ないほどの急激な米価の高騰を招いた米不足の根本要因をどのように考えるものか。また、減反政策をやめ、本市も自給率を引き上げるよう取り組むべきと考えますが、市長の見解をお示しください。
以上、御答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.22 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 園山えり議員にお答えいたします。
米不足の要因につきましては、国によりますと5年産米の生産量の減少や訪日外国人観光客数の回復による需要の増加などが考えられておりますが、今後、国が価格高騰の要因や対応の検証を行うこととしております。また国は、今後、水田政策を見直すとともに食料の安定的な供給に向け国内の農業生産の増大などを目指すこととしております。引き続き、国の動向を注視してまいりたいと考えております。
[園山えり議員 登壇]
P.22 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
政府は米不足を一貫して認めない姿勢ですが、市長とされても国と同様に米不足ということはお認めにはなりませんでした。しかし、農水省は主食用米の増産にシフトし始めたことから、実質的には米不足の状態であるということは認めたものと思います。農水省が示す主食用米の生産の目安、いわゆる生産調整を増やしていることからも明らかです。
農水省は鹿児島県に対して減らし続けてきた生産の目安を今年度は前年度と同じ9万トンとし、据え置きました。県が示した本市への目安は96トン減少した3,193トンでした。しかし、本市はこの目安を自家消費用の農家も含む約2,400戸に示されなかったと伺っております。国はいまだ米価を市場任せにし、主食用米の所得補償を行わず飼料用米への補助金を出し、実質的な減反政策をやめていません。だからこそ、本市は生産者が意欲的に増産できるよう独自の支援が求められているのではないでしょうか。米不足を招いた需要と供給ぎりぎりで示すような生産調整はやめ、米農家の所得補償を国に強く求めていただきたいと思います。そして、本市は消費地にとどまらずに今からでも食料自給率を上げるための取組を要請いたします。
次に、米軍機による低空飛行について県市長会は今年5月に要望書を出されました。鹿児島市も低空飛行訓練が行われている当該自治体として令和2年度から要望していますが、要望の内容と現在も低空飛行が常態化している下で市長は低空飛行訓練そのものの中止を求める立場に立っておられるか伺います。
以上、御答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.22 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) お触れの要望書では米軍機による低空飛行に関して訓練飛行上やむを得ず陸域を飛行する場合は民家上空を避けるなど、安全に最大限配慮することやその他の飛行に当たっても航空法等の国内法を遵守し、住民の不安を招く飛行はしないことなどについて米軍に要請していただくよう県市長会として知事に要望しております。低空飛行訓練については日本で活動する米軍の不可欠な訓練として日米合同委員会において合意されており、私の立場から訓練そのものの中止を求めることはありませんが、我が国の安全保障に関わる事項でもあり、国の責任において適切に対応していただきたいと考えております。
[園山えり議員 登壇]
P.22 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
住民の命と財産が脅かされている下で訓練そのものの中止を求めることはないというのはあまりに他人事のような答弁ではないでしょうか。今年4月、5月ともに2週連続で米軍機による低空飛行が行われており、住民から情報提供が寄せられていますが、特に4月17日の午後4時半頃、郡山小学校上空を機体を左右に揺らしながらの低空飛行が目撃されており、保護者から不安の声が上がっています。島根県西部の5市町では低空飛行訓練に抗議し、中止を求め防衛省に働きかけを行っています。協議会の会長を務める浜田市長は「住民たちは騒音を伴う低空飛行に恐怖を感じている」と述べ、協議会では、今後、広島県の自治体とも連携していく方針です。本市でも住民の実態を伝え、県や国に低空飛行そのものをやめるよう求めることこそ市長の役割ではないでしょうか。近隣の自治体とも連携するために市長がイニシアチブを執るよう要請し、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
川内原発について伺います。
九州電力が策定した九電グループ経営ビジョン2035について、1点目、内容と特徴をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.23 ◎答弁 危機管理局長(水之浦達也君)
◎危機管理局長(水之浦達也君) お答えいたします。
お触れのビジョンは、九州電力グループが2035年におけるありたい姿とその実現に向けた戦略として立案したもので、重点戦略として「カーボンマイナスへの挑戦」、「多様なニーズを叶えるソリューション進化」等が記載されております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.23 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
経営ビジョンにはカーボンマイナスを目指す取組の1つとして、次世代革新炉の開発と新設が2035年度までに示され、国のエネルギー計画の大幅な変更に従ったものとなっています。
次に、エネルギー計画は原発を廃炉にした代わりに電力会社内の別の原発敷地内であれば建て替えを可能としています。
そこで、質問の2点目に、廃炉となった玄海原発1、2号機の建て替えとして川内原発の敷地内での建設は可能かお示しください。
以上、御答弁願います。
P.23 ◎答弁 危機管理局長(水之浦達也君)
◎危機管理局長(水之浦達也君) 国の第7次エネルギー基本計画におきましては、廃炉を決定した原子力発電所を有する事業者の原子力発電所のサイト内での次世代革新炉への建て替えを対象として、地域の産業や雇用の維持発展に寄与し、地域の理解が得られるものに限り具体化を進めていくとしております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.23 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
エネルギー基本計画上、可能であるということは確認しておきます。今後、九電が経営ビジョンで位置づけた次世代革新炉が新設される可能性として、3号機が凍結されている川内原発が最も現実的であるということは言うまでもありません。
そこで、質問の3点目、建て替えの位置づけで川内原発に次世代革新炉が新設される場合、改めて環境アセスメント(環境影響評価)が行われるものか必要性の認識をお示しください。
また4点目に県知事は川内原発敷地内に原発が新設される場合、地元同意手続のやり直しが必要との認識を示されましたが、川内原子力発電所に係る原子力防災に関する協定を結ぶ本市としても地元同意の手続を求めるべきと考えますが、見解をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.23 ◎答弁 危機管理局長(水之浦達也君)
◎危機管理局長(水之浦達也君) 九州電力によりますと、エネルギー基本計画や2050年カーボンニュートラルを踏まえた国のエネルギー政策、原子力事業環境整備の動向、電力システム改革による競争進展の状況等様々な要素を勘案し検討していくこととしており、現時点で決まったものは何もないが、仮に今後川内3号機増設の検討を進める際には改めて環境影響評価への影響を確認する必要があると考えているとのことでございます。
地元同意につきましては、原子力施設の立地自治体である薩摩川内市と県に施設に関する判断を行う役割と責任があるものと考えております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.24 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
九電は環境影響評価への影響を確認する必要があるとのことですが、環境アセスを行うべきものという認識に立っていないことは問題です。川内原発3号機の建設に向けてのアセスの手続が2010年に行われていますが、15年前とは新設される原子炉も違えば、3・11福島原発事故が起き、鹿児島県民の意識も大きく変わっています。住民や自治体に十分説明し、意見を聴取する必要性があるのではないでしょうか。仮に3号機の増設が進む場合には改めて環境アセスを求めていただくよう要望するものです。
最後に、次世代革新炉と廃炉になった玄海原発の川内原発敷地内での建て替えについて反対するべきと考えますが、市長の見解をお示しください。
以上、御答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.24 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 次世代革新炉については、九州電力によると、「革新軽水炉をはじめ、高温ガス炉などの情報収集を行っている段階であり、具体的地点を念頭に置いたものではない」とのことであり、その動向については今後も注視してまいります。
[園山えり議員 登壇]
P.24 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
明言は避けられましたが、市長におかれましては、3号機増設、また新たな原発の新設には反対を貫かれますよう要望いたします。
地元新聞社の今年5月の世論調査では51%の県民が「川内原発の増設に反対」と回答し、その理由として、「安全性に疑問、使用済み核燃料の処分方法が決まっていない」が65%に上っています。鹿児島県知事は全国知事アンケートで核のごみの最終処分場の受入れについて、原発立地自治体の福島県、島根県両知事と共に処分場受入れに反対と示しました。新たな原発の核のごみの行き先が見通せないまま原発の活用が進む矛盾にどう向き合うのでしょうか。原発は廃炉しかないということを申し上げて、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
昨年の衆院選において自民党以外の多くの政党が選択的夫婦別姓の導入を公約に掲げました。世論の高まりとともに夫婦が自分の姓を選択できるようになると期待する人たちは決して少なくないと思います。
選択的夫婦別姓の導入を求める立場で現在の婚姻制度について伺います。
まず、選択的夫婦別姓についての全国で行われているアンケート調査について、1点目、NGO団体「新日本婦人の会」が今年1月に行ったアンケート調査の概要と旧姓の通称使用で困ったことをお示しください。
2点目、一般社団法人「あすには」が今年3月に行ったアンケート調査の概要と調査における事実婚の割合、事実婚の人が選択的夫婦別姓制度の法制化で法律婚にすると回答した割合。加えて、選択的夫婦別姓制度の法制化を待つ結婚待機人数。
3点目、金融庁と内閣府男女共同参画局のアンケートについて、まず、旧姓による預金口座開設等への対応状況。次に、通称を使用している市民の実態の把握状況をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.24 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) お答えいたします。
お触れのNGO団体が行ったアンケート調査は、この団体のサイトによると全国のこの団体の会員等を対象にしたもので、10代から80代以上の3,979人が回答したとのことです。旧姓の通称使用で困ったことについては、銀行窓口での本人確認に手間取る、手続に旧姓併記の住民票が必要なことがあるなどのエピソードが寄せられているようです。
また、お触れの一般社団法人が行った調査は、この団体のサイトによると全国の20歳から59歳の男女を対象にしてアンケートを実施し、そのうちから1万サンプルを性別、年代別及び人口構成比に合わせて回収し分析したスクリーニング調査と1,600サンプルを性別、年代別に均等に割りつけて回収し分析した本調査を行ったものとのことです。このアンケート調査の結果として、事実婚の割合は2.0%、選択的夫婦別姓の法制化で法律婚にすると回答した事実婚の人の割合は49.1%、選択的夫婦別姓の法制化を待つ人としてお触れのアンケートで結婚待機人数とされる人の数は58.7万人とそれぞれ公表されております。
お触れの国が行ったアンケートによると、銀行の約7割、信用金庫の約6割が旧姓名義による口座開設等に対応しております。通称を使用している市民の実態については把握しておりません。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.25 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
あすにはの調査では20代から50代の人の2%が事実婚を選択していることが分かりました。これは内閣府のアンケート調査において明らかになった2%から3%という推計値と合致しており、日本全体では20代から50代の122万6千人が事実婚を選択していると推計され、そのうち58万7千人が法制化を待つ結婚待機人数であるということが分かりました。事実婚を選び、通称使用については課題も残されており、根本的な解決に至っていない実態もあるようです。
そこで、事実婚について伺います。
1点目、本市での事実婚の手続の仕方をお示しください。
2点目、婚姻している人の数と事実婚として未届の夫・妻と記載している人数。
3点目、本市における20代から50代の事実婚をしている人の推計人数をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.25 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 本市では国の事務処理要領に基づき住民異動届の手続の際、届出人からその旨の申し出があった場合には続柄を夫(未届)、または妻(未届)として受理し、住民票等に記載しております。
本市の住民基本台帳で確認できる婚姻者の数、続柄が夫(未届)、妻(未届)の人数を7年5月末現在で順に申し上げますと、26万1,754人、23人、109人でございます。
お触れの推計人数については把握していないところでございます。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.25 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
本市において事実婚として未届の夫、あるいは妻と記載している人数は合わせて132人、264組おられることが分かりました。事実婚の推計人数はお示しいただけませんでしたが、本市の住民基本台帳人口を基に20代から50代の人口27万3,830人のうち2%とすると5,476人が事実婚であると推計できると思います。決して少なくない人たちが事実婚を選択している可能性があると思います。
そこで、質問の4点目、事実婚を選択している方々に不便や不利益があるものかお示しください。
以上、御答弁願います。
P.25 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 事実婚と言われる婚姻の届出をしていないが、事実上、婚姻と同様の状態においては、法律上認められた婚姻関係である法律婚と比較して配偶者の相続権や所得税の配偶者控除がないなど取扱いが異なる権利関係や制度などがあるとされています。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.25 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
お示しいただいたように相続権や配偶者控除ができないなどの不利益がありますが、ほかにも配偶者として医療行為への同意ができない、生命保険の受け取りができないなど様々な不便があるようです。
次に、選択的夫婦別姓に関する国の動向について伺います。
まず、平成8年(1996年)の国の法制審議会の答申の内容とその後の経過。
次に、28年間議論が進まなかった主な要因。
そして、今国会で28年ぶりに審議入りした法案の主な内容をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.25 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 法務省のサイトによると、平成8年の同省の法制審議会において選択的夫婦別姓制度の導入が提言されている民法の一部を改正する法律案要綱が答申され、これを受けて同省は同年及び22年にそれぞれ改正法案を準備したものの、いずれも国会に提出するに至らなかったとのことです。
選択的夫婦別姓制度の導入は婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題であるので国民の理解の下に進められるべきものとの考えを法務省が示しているところであり、そのための時間を要したものと考えますが、お触れの主な要因は判断しかねるところです。
今国会で審議入りした選択的夫婦別姓に関する法案には、選択的夫婦別姓を法制化するものと旧姓の通称としての使用を法制化するものがあり、夫婦別姓を選択した場合の子供の姓については、婚姻時に夫婦いずれかの姓に決定する案と婚姻時に戸籍の筆頭者を定め、その姓と同じくする案が盛り込まれています。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.26 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
法制審の答申から約30年、今国会で3野党から法案が提出され、審議入りしました。法制審の答申が求めている民法改正をせずに通称使用の拡大を求める法案もあるようですが、これでは別姓を望む人たちのアイデンティティーの喪失、個人の尊厳に関わる部分で根本的に解決できないということは指摘しておきたいと思います。
この間、日本は国連女性差別撤廃委員会から選択的夫婦別姓を導入するよう勧告を受けており、夫婦同姓を強制しているのは、もはや世界で日本だけとなっています。
最後に、民間団体、また国も様々な調査に取り組んできており、事実婚を選択している人も一定数推計されることから、本市としても実態把握をすべきと考えます。
そこで、困難を抱えた方の実態を把握するためにアンケート調査等で市民の声を聞く取組を求めるものですが、見解をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.26 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 婚姻制度に関連する実態については、国等による各種の調査がされており、引き続きそれらの結果等の把握に努めてまいります。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.26 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
独自調査は考えておられないようです。情勢の変化や国会で28年ぶりに審議入りするなど、機運は高まっていると思いますので、そのことも踏まえ、市独自に事実婚の不便さや不利益などを積極的に把握していただくよう求め、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
自衛隊への名簿提供について伺います。
18歳市民を対象とした自衛隊への名簿提供の時期が今年も迫ってきました。名簿提供を拒むことのできる除外申請について、6月13日が締切りだったことから伺います。
まず、申請数とその内訳を電子申請、直接申請、郵送別にそれぞれお示しください。
次に、7年度の取組内容と市民から寄せられた声はなかったものかお示しください。
以上、御答弁願います。
P.26 ◎答弁 総務局長(尾堂昭二君)
◎総務局長(尾堂昭二君) お答えいたします。
除外申請の件数は123件で、内訳は、電子申請106件、直接申請4件、郵送13件でございます。
次に、令和7年度は市民のひろばや市ホームページのほか毎月市公式SNSに掲載するとともに、高校等へチラシデータを送付するなど周知・広報に努めたところでございます。また市民からは申請手続の方法や提供された情報の取扱いなどに対し問合せがあったところでございます。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.26 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
今年度は123人が除外申請を行ったということでした。名簿提供はこれからですので、市民から申請の意向があった場合には拒否せずに最後まで柔軟に対応するよう要望しておきます。
また、7年度の取組として高校などへチラシのデータを送るなど初めての取組もあったようです。振り返ってみますと除外申請をした人は、5年度が168人、6年度は101人、今年度は123人といずれも100人を超えています。市民団体の若者の個人情報を守る会の皆さんが駅前などで高校生にチラシ配布をされましたが、多くの生徒さんが知らないと答え、まだまだ周知が不十分であるということは指摘をしておきたいと思います。
次に、県内の自治体において15歳を対象とした誤った名簿提供が行われたようですので伺います。
1点目、高等工科学校の生徒募集のための名簿提供についての考え方。
2点目、鹿児島地方協力本部から県内の自治体へ送付された令和5年12月19日付の通知内容と本市の取扱いをお示しください。
以上、御答弁願います。
P.27 ◎答弁 総務局長(尾堂昭二君)
◎総務局長(尾堂昭二君) お触れの件につきましては、自衛隊鹿児島地方協力本部によりますと、自衛隊法第97条及び同法施行令第120条において、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部が法定受託事務と定められていることから、募集対象者情報の提出をお願いしているところであるが、これに該当しない高等工科学校の生徒募集については自衛隊法第29条を根拠として、住民基本台帳法第11条に基づき閲覧申請を実施させていただいているところ、今回、紙媒体で受け取ってしまったことは不適切であったと認識しているとのことでございます。
次に、お触れの通知は本市には送付されていないことから、内容等については把握していないところでございます。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.27 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
名簿提供について自衛隊は法定受託事務と定められていると示されたようですが、これまで当局と質疑を交わしてきた中で名簿提供は法定受託事務ではないということは繰り返し確認をしてまいりました。だからこそ本市は令和4年度までは名簿提供をしてこなかったわけです。自治体に対して法定受託事務だと示すことは重大な認識不足であるということは厳しく指摘をしておきます。
また、通知については本市に送付されていないということでしたが、鹿児島地本が出したこの通知は、自衛官募集のためとして18歳や22歳に加えて15歳の男子も対象として名簿提供を求めるものでした。しかし、高等工科学校の生徒はあくまでも生徒の位置づけであり、自衛官には該当しません。であるにもかかわらず、自衛官募集を行えるとする自衛隊法第97条や同施行令第120条を根拠に自治体に名簿提供を求めていました。これは明らかな法令違反に当たると考えます。鹿児島地本はその2日後に改めて通知を出し、15歳の男子については閲覧対応すると変更しました。日本平和委員会の発行する平和新聞によると全国では茨城県と鹿児島県で今回のような法令違反が相次いだとのことでした。
そこで、質問の3点目、県内で名簿提供を行った自治体と4点目に鹿児島地方協力本部から名簿提供をした自治体への公式な謝罪はあったものかお示しください。
以上、御答弁願います。
P.27 ◎答弁 総務局長(尾堂昭二君)
◎総務局長(尾堂昭二君) 県内19市のうち2市でお触れの名簿提供を行ったようでございます。
次に、自衛隊鹿児島地方協力本部によりますと、関係自治体に対して説明及び謝罪を口頭で行ったとのことでございます。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.27 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
お示しいただいた2市というのは阿久根市や垂水市、そして、それに加えて東串良町、南大隅町、肝付町、宇検村も名簿提供をしたことが平和新聞の取材で明らかになっています。謝罪したと言われましたが、口頭での謝罪で済ませるとは地本のずさんな対応と言わざるを得ません。自治体側にも住民基本台帳の運用や防衛省、文科省からの通達などへの認識不足を指摘せざるを得ませんが、その認識の不十分さに付け込んで15歳の名簿を受け取ったということは不適切だったで済まされる話ではないと思います。
最後に伺います。
相次ぐ法令違反により防衛省、自衛隊への信頼が問われているのではないでしょうか。名簿提供はやめるべきと考えますが、お示しください。
以上、御答弁願います。
P.28 ◎答弁 総務局長(尾堂昭二君)
◎総務局長(尾堂昭二君) 本市におきましては、自衛隊法や同法施行令、国の通知などを踏まえ、5年度から名簿を提供しているところであり、今後におきましても法令等に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.28 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
自衛隊が法令違反を平然と行っており、まともな謝罪も反省もない、このような組織に対する市民の信頼は損なわれるのではないでしょうか。当局とされては毎年100人を超す18歳市民が名簿提供に同意しないと声を上げていることを重く受け止めていただき、改めて名簿提供はやめるべきと考えます。そのことを要望し、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
市営住宅の空き室について伺います。
高齢者の方々が住まいに困っておられる深刻な相談が寄せられています。実質、年金は減らされ、家賃の支払いに苦しむ人たちが「市営住宅に入れないだろうか」という声を上げるのは当然だと思います。しかし、エレベーターなどのある住宅は倍率が高いからと諦める高齢者を数多く見てきました。そのような実態がある下で市営住宅の近くに住む住民から、「エレベーター付の市営住宅は希望する市民が多いが、住宅の空きが目立っている、なぜ活用しないのか」という素朴な疑問が寄せられました。
そこで、空き室の活用を求める立場から、以下伺います。
まず、空き室の現状について伺います。
1点目、住宅の戸数と空き室の数、割合を三和、鴨池新町、真砂本町それぞれお示しください。
2点目、空き室の期間はどれくらいか、平均と最長期間をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.28 ◎答弁 建設局長(山中浩平君)
◎建設局長(山中浩平君) お答えいたします。
住戸数と空き住戸数及び割合を住宅ごとに順に申し上げますと、三和、318戸、26戸、8.2%、鴨池新町、300戸、24戸、8%、真砂本町、143戸、9戸、6.3%でございます。
空き住戸の平均と最長の期間を順に申し上げますと、三和、2年4か月、6年11か月、鴨池新町、2年6か月、7年6か月、真砂本町、1年8か月、3年4か月でございます。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.28 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
3つの住宅を合わせると59戸が空き室であり、その割合は、平均で7.5%、最長で7年6か月もの間、空き室であることが分かりました。空き室が出たならば速やかに募集できるよう努めるべきと考えます。
そこで3点目に空き室の主な理由と課題認識。
4点目に対応状況と今後の募集についての考え方をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.28 ◎答弁 建設局長(山中浩平君)
◎建設局長(山中浩平君) 空き住戸の主な理由は退去者の修繕費未払いにより修繕費用の確保が難しいことであり、指定管理者と連携し改修に努めることなどが課題であると考えております。
空き住戸については指定管理者と協議し、修繕費用の確保などに努めており、今後も早期の募集に取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.28 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
修繕費の回収に努めることが課題と言われましたが、もちろん未払いを放置していいなどとは思いませんが、空き室の60件のうち修繕費の未払いに加えて市の独自の責任で修繕をする住まいもあると伺っています。次の募集につなげるため、速やかな修繕を行うためにも財源の確保が課題ではないでしょうか。
次に、募集申込み状況について、1点目、募集住宅の戸数と申込者数、募集倍率を三和住宅のシルバーハウジングとそれ以外、また、鴨池新町、真砂本町それぞれお示しください。
以上、御答弁願います。
P.29 ◎答弁 建設局長(山中浩平君)
◎建設局長(山中浩平君) 令和6年度の募集戸数、申込者数、募集倍率を住宅ごとに順に申し上げますと、三和のシルバーハウジング、1戸、49名、49倍、シルバーハウジング以外、6戸、77名、12.8倍、鴨池新町、12戸、168名、14倍、真砂本町、1戸、47名、47倍でございます。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.29 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
三和と鴨池新町はいずれも15倍に迫る倍率であり、三和シルバーハウジングと真砂本町では50倍に迫る高い倍率となっていることが分かりました。
そこで2点目に、なぜこのように需要があるのか当局の評価をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.29 ◎答弁 建設局長(山中浩平君)
◎建設局長(山中浩平君) 需要の要因としては、周辺に大規模な商業施設や医療施設などがあることやエレベーターが設置されていることなどがあると考えております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.29 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
当局が示されたようにエレベーターも設置されており、利便性のいい住宅だからだと私も思います。6年度のほかの住宅の倍率を見てみますとエレベーターのない紫原や星ケ峯は募集に対して応募ゼロということも少なくありません。倍率の低い住宅に誘導したい気持ちは分かりますが、倍率から見ても利便性のいい住宅が特に求められているということは明らかです。
そこで最後に伺います。
高齢化に伴いエレベーターが設置されていることや利便性のよい立地であることなど、市民から需要のある住宅は速やかに募集するべきと考えますが、当局の見解をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.29 ◎答弁 建設局長(山中浩平君)
◎建設局長(山中浩平君) お触れの住宅については市民からの需要も高いことから、指定管理者と協議しながら、引き続き早期の募集に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.29 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
空き室が放置され、市民の重要な財産が活用されていないという状況は問題であると考えます。修繕費の確保に努められ、特に利便性のいい空き室は速やかに募集するよう要望し、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
地域課題について、唐湊地域の里道(中央1号生活道路)の側溝整備について伺います。
この道路は何十年と変わらず地域住民の生活道路となっており、欠かすことのできない道です。側溝のない狭隘な道であることから、近年繰り返される豪雨によって行き場のない雨水が里道の上を流れ落ちていくので大変危険だと住民から要望が出されていました。加えて、鹿児島大学農学部の果樹園に面しており、果樹園側に大量の雨が流れ、路肩も崩れたままの状況が数年間放置されています。
そこで1点目に、これまでの経緯と7年度の取組。
2点目に、今後の見通しと住民への説明はなされるものかお示しください。
以上、御答弁願います。
P.29 ◎答弁 建設局長(山中浩平君)
◎建設局長(山中浩平君) お触れの側溝整備については、令和元年度に要望があり、2年度に法定外公共物等整備審査会で承認し、その後、隣接土地所有者等の同意が得られたことから、6年度に申請書が提出されたところでございます。また、7年度は整備予定区間の一部路肩の補修を行う予定でございます。
法定外公共物等の整備は着手までに期間を要しており、住民への説明については着手のめどが立った時点で行うこととしております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.29 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
住民の要望からおよそ7年、令和2年の審査会で承認されていながらなかなか進まない状況です。住民からの申請が提出されたことからも側溝整備を進めていただきたいと強く思います。
そこで、3点目に、里道整備の市独自の予算について伺います。
まず、5年間の予算の推移。
次に、法定外公共物等整備審査会が認めた件数と着工までの期間。
そして、住民の申請後、却下されたものはないものかお示しください。
以上、御答弁願います。
P.30 ◎答弁 建設局長(山中浩平君)
◎建設局長(山中浩平君) 法定外公共物等の整備に係る予算を3年度から7年度まで順に申し上げますと、およそ3,060万、2,910万、2,910万、2,760万、ゼロ円でございます。
平成18年度以降、審査会で採択した件数は令和6年度末時点で298件、申請書提出から着工までの期間はおよそ4年から6年でございます。
また、これまで住民が申請した後に却下したものはございません。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.30 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
これまで3千万円前後で推移してきた予算が7年度はゼロになったことが分かりました。審査会で採択された件数はおよそ300件に上り、住民は着工まで4年から6年も待っている現状があるようです。今年度は予算もゼロで、このペースで要望に応えられるのか大変疑問であり、見通しが立ちません。市単独事業のため厳しい財政の下で市民は我慢しろということでしょうか。
最後に、このような実態に対する当局の課題認識をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.30 ◎答弁 建設局長(山中浩平君)
◎建設局長(山中浩平君) 法定外公共物等の整備については優良財源がないことなどから着手までに期間を要しておりますが、引き続き限られた予算の中で早期着手に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.30 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
早期着工に努められるといっても予算がゼロになっているわけですから、早期着工は望めないと受け止めざるを得ません。私はこのような生活に密着した事業がなぜ予算ゼロなのか理解に苦しみます。年々激しさを増す雨の降り方を見ても一刻も早い側溝整備が必要です。改めて速やかな整備を求めて、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
特別職、ここでは市長と議員に絞って報酬等の引上げについて伺います。
令和7年第1回定例会で下鶴市長は、厳しい財政を理由に施設使用料の大幅値上げや敬老祝い金の引下げ、放課後等デイサービスの有料化に踏み出すなど、市民サービスの大幅な切捨てや福祉の削減が行われたものと認識しています。ところが今議会では特別職の報酬等の引上げが提案されました。私はこの引上げに疑問を持つ立場で以下伺います。
まず、1点目に特別職の報酬等の推移をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.30 ◎答弁 総務局長(尾堂昭二君)
◎総務局長(尾堂昭二君) 平成9年度及び18年度の報酬等改定時における改定率と市長及び議員の改定後の月額を順に申し上げますと、9年度がプラス約6%、119万円、70万7千円、18年度がマイナス約3%、115万4千円、68万6千円でございます。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.30 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
平成9年度の改定では6%と大幅に引き上げられており、その後マイナス改定が行われたとは言え、決して低い水準ではないということは指摘をしておきたいと思います。
2点目、特別職報酬等審議会について伺います。
まず、今年5月に行われた審議会での議論と答申内容。
次に、期末手当を審議対象にすることについて報酬審での意見をお示しください。
以上、御答弁願います。
P.31 ◎答弁 総務局長(尾堂昭二君)
◎総務局長(尾堂昭二君) 今回の特別職報酬等審議会におきましては、現行の二役の給料及び議員報酬の額は18年度のマイナス約3%の改定以来19年間据置きが続いているが、その間、本市の消費者物価指数や県内の民間賃金水準等は上昇しており、市民感情等を考慮しても引き上げる時期に来ていること、一般職の職員の給与改定率が18年度から累積で3.05%となっていること、本市の人口規模は中核市62市中3位だが、市長の年収ベースは32位であり、年収水準は低いと言わざるを得ないことなどを総合的に勘案し、3%の増額改定が適当とされたところでございます。また、政務活動費につきましては、会派ごとの執行率を勘案しても現時点において積極的に額の改定を行う必要があるとまでは言えないとして、据置きが適当とされたところでございます。
期末手当を審議対象にすべきとの意見があったことにつきまして同審議会で説明いたしましたが、このことについて特に議論はなかったところでございます。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.31 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
報酬審では一般職の職員の給与改定率が18年度から累積で3.05%となっていることを引上げの根拠の1つにされておりますが、特別職は一般職員の引上げに従う必要はないということは指摘をいたします。
次に、特別職報酬等改定議案、特に市長と議員を対象とした第19号議案と第23号議案について伺います。
1点目、特別職の報酬等の引上げの影響額。
2点目、他都市との月額、年収別の比較を中核市、同規模中核市、九州県都でお示しください。
3点目、同規模中核市の平均額を月額、年収でお示しください。
以上、御答弁願います。
P.31 ◎答弁 総務局長(尾堂昭二君)
◎総務局長(尾堂昭二君) 市長及び議員の報酬等改定による年間の影響額は約1,590万円でございます。
中核市人口50万人以上の同規模中核市、九州県都における市長及び議員の報酬月額等と年収ベースの金額の改定前後の順位について順に申し上げますと、中核市62市中、市長が7位から2位、32位から22位、議員が3位から1位、16位から10位に、同規模中核市6市中、市長が3位から1位、6位で変動なし、議員が1位で変動なし、4位から3位に、九州県都8市中、市長が3位で変動なし、4位から3位、議員がどちらも2位で変動なしとなっております。
同規模中核市における市長及び議員の報酬月額等と年収ベースの平均額を順に申し上げますと、市長は114万1千円、2,027万6千円、議員は65万1千円、1,125万9千円となっております。
以上でございます。
[園山えり議員 登壇]
P.31 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
年間で約1,600万円の影響があり、同規模中核市で比較しますと月額で市長、議員いずれも1位ということが分かりました。特に議員は引上げ前も1位であり、高い水準にあるということが分かりました。また、同規模中核市の平均額は市長が114万1千円、議員が65万1千円であり、今回の改定で市長は118万9千円に、議員は70万7千円になることからもいずれも平均を上回ることが分かりました。
最後に市長に伺います。
急激な物価高の下で市民の生活が厳しい中、市長は答申に示された昨今の物価高騰で厳しい社会経済状況にある中での引上げであることをどのように受け止められたものか。また、物価高を理由に市独自予算の大幅削減が行われる中で特別職の報酬等の引上げはやめるべきと考えるものですが、見解をお示しください。
以上、御答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.31 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 今回の審議会におきましては、各界各層の代表者等である委員の皆様が職員の給与改定状況や他都市との均衡、社会経済情勢など様々な資料を基に各面から十分に議論をされ、その結果を答申として取りまとめていただいたものであり、私としましてはこの内容を尊重することとしたところでございます。答申書の附帯意見にありますとおり、厳しい社会経済状況にある中での改定であることを十分認識し、市民の皆様の期待に応えられるよう今後より一層市勢の発展に力を尽くしてまいりたいと考えております。
[園山えり議員 登壇]
P.32 ◆質問 (園山えり議員)
◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。
報酬審の議論を尊重されたとのことでしたが、市長は政治判断ができるはずです。市長はなぜ引き上げる必要があるのか、また3%という大幅な引上げ率に対しても市民が十分に納得できるよう説明責任を果たすべきではないでしょうか。
市長におかれましては、初当選された2020年の公約で市長給与を50%カットしてコロナ対策に充てるという意気込みがあったではありませんか。今回質疑を交わしてまいりましたが、市営住宅や生活道路の整備など、暮らしに直結する予算は厳しい財政を理由に削減しながらも特別職の給与や報酬は引き上げる、物価高で苦しむ市民の理解が得られるとは到底思えません。
そのことは強く申し上げ、私の全ての質問を終わります。