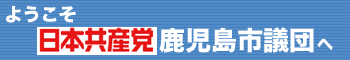P.42 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
一部割愛する項目あるいは重複する項目があることをあらかじめ申し上げておきます。
初めに、市長の政治姿勢について、2点質問します。
このパネルを御覧ください。
鹿児島市の消費者物価指数と消費税の影響をグラフにしたものです。これまで4回にわたる消費税率の引上げが行われています。1989年の消費税3%で2.0ポイント物価が上昇しております。そして、1997年の消費税5%で2.5%物価が上昇しております。2014年の消費税8%で2.7ポイント物価が上昇しております。そして、2019年の複数税率のとき、この10%の導入のときに0.8ポイント増加しているわけです。この結果からも分かるように、物価高騰対策として消費税5%減税が最も効果的で合理的な提案であると考えますが、市長の見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.42 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) たてやま清隆議員にお答えいたします。
国においては、物価高の克服などを柱とする国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策に基づき各種施策に取り組まれているところであり、本市としても国の交付金を活用し、市民や事業者に対する支援を行っているところでございます。私といたしましては、消費税は持続的な社会保障制度の構築やその安定財源の確保に資するものであるとともに、地方自治体の貴重な財源となっていることから、今後とも、社会保障の充実や持続可能な地方財政の運営につなげていくことが肝要であると考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.42 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
消費税5%減税について否定的な御見解でしたが、消費税はそもそも社会保障の改善につながったと言えるでしょうか。消費税の増税は、一方で法人税や所得税、大企業や富裕層の減税の穴埋めにされてしまった。それがこの36年間の結果ではなかったでしょうか。政府は現金給付を検討しているようですが、財源を示していません。消費税5%減税は、平均的な勤労者世帯で年間12万円の減税効果があり、その財源は赤字国債ではなく、大企業、富裕層への減税、優遇をただすことで確保できるということを私どもは市民に訴えてまいります。
質問の2点目、学問の自由を侵害する日本学術会議法案、日本学術会議解体法案が国会で成立しましたが、このことを市長はどのように受け止めておられますか、見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.42 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 今国会で成立したお触れの法案につきましては、日本学術会議が科学の向上発達等を通じて、国民の福祉と我が国の発展に貢献できるよう、その機能強化を図るため独立した法人格を有する組織として必要な枠組みを定めるためのものとされておりますが、様々な意見もあることから、国において適切な運用等が図られることが肝要であると考えております。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.42 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
様々な懸念があるという言葉だけで表現をされましたが、同法案は、日本学術会議の独立性・自主性・自律性を奪い、科学者の総意の下に、科学と平和と人類社会の福祉に貢献させるという学術会議の理念を削除し、科学を軍事に従属させようとするものです。法案撤回を求めた学者の皆さんは、市民と力を合わせ、学問の自由を守る闘いに踏み出しています。私たち市議団も目前に迫る参議院選挙に向け、「消費税減税で暮らしを守れ」、「学問の自由を守れ」と市民に訴えていく決意を申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
令和7年度は16年ぶりに国保税率が改定され、1世帯当たり1万9,700円の負担増となる国保行政について、以下質問します。
初めに、令和7年度税率改定の影響について、3点質問します。
質問の1点目、所得10万円以下の加入世帯数、滞納世帯数、割合、滞納総額をお示しください。
質問の2点目、所得10万円以下の1人から4人の世帯人員数ごとの7年度国保税と6年度との比較をお示しください。
質問の3点目、所得10万円以下の国保世帯と生活保護基準の70歳単身、母と子1人の世帯のモデル世帯との収入の比較をお示しください。
答弁願います。
P.43 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) お答えいたします。
6年度における所得10万円以下の国保の加入世帯は2万5,353世帯で、うち滞納世帯は、2,593世帯、10.23%、その滞納総額は7,485万円でございます。
所得10万円以下の世帯の国保税額は、世帯人員ごとに7年度、6年度の順に、1人、2万1,400円、1万7,100円、2人、3万3,900円、2万5,300円、3人、4万6,300円、3万3,500円、4人、5万8,700円、4万1,600円となります。
70歳の単身世帯について、所得10万円以下の国保世帯の公的年金収入額と生活保護受給世帯の保護基準額を比較すると、120万円以下と125万8,800円、母と子1人の世帯について給与収入額と保護基準額を比較すると、65万円以下と218万400円となります。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.43 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
7年度税率改定により7割軽減が適用されても、所得10万円以下の4人世帯の場合、6年度の税額より負担が3万5,800円増加し、7年度の税額は5万8,700円となり、所得に対する負担率は58.7%です。所得10万円以下の1世帯当たりの滞納額が約2万9千円ですから容易に返済できる額ではありません。また、2つの国保のモデル世帯が示すように、所得10万円以下の所得層は生活保護基準の所得層であり、国保税の減免制度の拡充が必要です。
そこで、国保税の減税について、4点質問します。
質問の1点目、生活保護基準の所得層の国保税減免の拡充について見解をお示しください。
答弁願います。
P.43 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 本市においては、倒産、解雇等による所得の激減や災害、生活保護を受給するようになった場合など、特別な事情のある方を対象として国保税の減免措置を行っているところであり、お触れになられた減免制度の拡充などについては現段階では考えておりません。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.43 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
考えていないとの答弁ですが、現行の減免制度は恒常的な低所得者に対しては適用されない制度であるということは申し上げておきます。
次に、質問の2点目、所得減少による国保税の減免件数と減免額の3年間の推移をお示しください。
質問の3点目、倒産、解雇等による離職者に対する特例措置による減免件数の3年間の推移をお示しください。
答弁願います。
P.43 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 所得激減による減免件数と減免額は、4年度から6年度まで順に、134件、1,365万8千円、159件、1,574万1千円、146件、1,574万4千円となっております。
倒産、解雇等による離職者に対する特例措置による減免件数は、同様に1,266件、1,307件、1,396件でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.43 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本市の所得減少による減免は、前年度の合計所得の合算額が600万円以下で3割減少した場合に適用されますが、減免件数は増加傾向にあるとは言えません。また、所得減少の要因には自己都合による退職は認められないことも課題であります。また、控除に左右される所得減少から収入減少の基準に変更することで減免対象の拡大につながることも考えられます。
そこで、質問の4点目、所得減少の要因を緩和し、収入減少による国保税減免の拡充を検討すべきと考えますが、答弁願います。
P.44 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 本市の所得激減による減免制度は、ほかの中核市と比較しても狭くない範囲で減免を行っていることや本市国保財政が非常に厳しい状況にあること等を踏まえ、お触れになられた制度の拡充は現段階では考えておりません。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.44 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本市の減免の範囲は狭くないと答弁されましたが、現行の減免制度は、16年前の平成21年に国保税率を改定し、引き上げる際につくられました。当時の市民局長は、中核市や九州県都市の中で比較すると、本市の減免制度は減免対象事由が限られていることや前年所得の減少率の面で低い水準にあるとの認識を示しています。今回の国保税の引上げは16年前を上回る負担増であります。他都市の減免制度を改めて再調査され、減免制度の拡充を検討されることを重ねて要請します。
次に、国保税の滞納について、4点質問します。
質問の1点目、滞納件数を世帯数としてお示しいただき、滞納総額と差押件数とその額の3年間の推移をお示しください。
質問の2点目、特別療養費、すなわち10割負担となる対象世帯数及び被保険者数の3年間の推移をお示しください。
答弁願います。
P.44 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 滞納世帯数等について、4年度から6年度まで順に、滞納世帯数、8,293世帯、7,728世帯、7,830世帯、滞納総額、6億4,413万円、6億2,190万円、6億4,754万円、差押件数、2,579件、2,353件、2,801件、差押額、1億8,394万円、1億3,844万円、1億5,283万円となっております。
また、特別療養費は同様に、対象世帯数、1,365世帯、1,410世帯、1,413世帯、被保険者数、1,838人、1,935人、1,926人となっております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.44 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
滞納世帯に対して差押件数の増加傾向が見られますが、特別療養費の対象、つまり実質無保険状態の国保世帯が若干増加傾向にあることは懸念されます。
そこで、質問の3点目、改正国民健康保険法による特別療養費の規定の内容と周知の徹底を図るべきと考えますが、見解をお示しください。
質問の4点目、児童手当等の差押禁止債権の留意事項と誤って差し押さえた場合の本市の対応をお示しください。
答弁願います。
P.44 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 改正後の国民健康保険法では、納付勧奨などの納付に資する取組を行ってもなお納付しない滞納者に対しては、政令で定める特別の事情がある場合を除き、療養の給付等に代えて特別療養費を支給するとされており、またその際は、あらかじめ通知することとされております。本市では、このことを催告書等に記載し、対象となり得そうな方に対して周知しております。
差押えの執行に当たっては、児童手当等の差押禁止債権に該当しないかどうかなどの確認を含め、滞納者の生活状況等を勘案し対応しているところです。税負担の公平性を図る観点からも厳正な滞納処分は必要と考えておりますが、滞納者の状況を確認の上、生活維持が困難となるような場合は適切な対応を図っております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.44 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
特別療養費の方は、滞納している国保税の一定額を納めない限り無保険状態が続くことになります。それでは市民の命を守ることはできません。横浜市では、特別療養費の対象であっても保険証を交付した上で滞納処分は別途行う措置を講じ、医療を受ける権利を保障しています。本市も市民の命を守ることを最優先してください。子育て世帯から相談が寄せられていますが、児童手当は差押禁止債権であり、誤って差し押さえることがあってはならない行為であります。速やかな対応を求めます。
次に、マイナ保険証と資格確認書について質問します。
質問の1点目、本市国保の被保険者数とマイナ保険証の直近の登録率及び利用率をお示しください。
質問の2点目、昨年の12月2日以降に交付された資格確認書と資格情報のお知らせの件数をお示しください。
質問の3点目、マイナ保険証の利用が困難な方へのこれまでの資格確認書の交付件数をお示しください。
質問の4点目は先ほど質疑されたので割愛します。
以上、3点について答弁願います。
P.45 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 本市国保における7年3月の被保険者数は10万3,169人、マイナ保険証の登録率は72.91%、利用率は47.19%でございます。
本市国保で本年5月末までに交付した資格確認書は9,623件、資格情報のお知らせは1万3,890件でございます。
マイナ保険証での受診が困難な高齢者などの要配慮者からの申請による資格確認書の交付件数は、5月末現在で10件でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.45 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
現在の国保被保険者でマイナ保険証を持たない人は2万7,949人、登録している人は7万5,220人であることが推計されます。現行の保険証が廃止された12月2日以降、約4割のマイナ保険証を持たない人には資格確認書が交付され、登録している人には資格情報のお知らせが交付されていますが、全国保険医団体連合会(保団連)の調査では、資格情報のお知らせのみを持参して来院することがトラブルの要因にもなっているようであります。なお、高齢や障害などを理由にマイナ保険証を持っている人も申請により資格確認書を交付することができますが、僅か10件とは少ないです。周知が徹底されていないと思います。マイナ保険証の利用率は、国民全体で28.65%、国家公務員の29.57%と比較すると本市の後期高齢者医療保険の利用率35.34%は決して低いとは言えません。利用率が低いからではなくトラブルを回避するために職権で資格確認書を交付することになったわけであります。
質問の5点目、世田谷区、渋谷区が国保加入者全員に資格確認書の交付を決定した法的根拠と国の事務連絡の内容をお示しください。
答弁願います。
P.45 ◎答弁 市民局長(大山かおり君)
◎市民局長(大山かおり君) 国によりますと、資格確認書の職権交付は自治体の判断であり、両区はマイナ保険証の利用率が低い中、国民健康保険証の有効期限が到来することによって混乱が生じることを懸念して、被保険者全員に資格確認書を交付するとしているとのことでございます。また、国の事務連絡では、資格確認書は、法律上、被保険者が「電子資格確認を受けることができない状況にあるとき」に交付することとされているが、国民健康保険の被保険者には様々な年代・属性の方が含まれており、後期高齢者のように、マイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が一般的に高いと言える状況ではなく、資格確認書を被保険者全員に職権交付するコスト等も考慮すると、全員一律に資格確認書を交付する状況ではないと考えているとされております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.45 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
法的根拠は示されませんでしたが、改正健康保険法第15条に基づいて保険者が必要があると認めるときは職権で資格確認書を交付することは可能であり、国も自治体の判断として実質認めています。世田谷区長は、区民が保険診療を受ける権利を保障するための判断だとコメントしています。
そこで、市長にお尋ねします。
本市もトラブルを回避するために国保加入者全員に資格確認書を交付すべきと考えますが、見解をお示しください。
答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.46 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 資格確認書については、法律等や国の通知などを踏まえ、本市国保独自で全ての被保険者に交付することは考えておりませんが、11月末に紙の保険証からの一斉更新の時期を迎えることから、市民の皆様に混乱が生じないよう関係課において丁寧な対応を行うなど適切に対応してまいります。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.46 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
保団連の調査では、9割の医療機関でトラブルが発生していても8割の方が持ち合わせていた健康保険証で確認することができています。しかし、確認できず10割負担となった事例が全国で1,891件に上ったとのことであります。一人の市民も無保険になることだけは避けなければなれません。再検討を強く求めて、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
現在、令和6年度から8年度までの第9期高齢者福祉・介護保険事業計画が進捗中ですが、深刻な人手不足に直面している介護保険行政について、以下質問します。
初めに、東京商工リサーチの2024年度「老人福祉・介護事業」の倒産調査について、1点目、介護事業者の倒産件数と前年度比較。
2点目、訪問介護、通所・短期入所、有料老人ホームの業種別の倒産件数。
3点目、倒産の原因別及び介護報酬や訪問介護員(ホームヘルパー)の影響について、それぞれお示しください。
答弁願います。
P.46 ◎答弁 健康福祉局長(松尾健志君)
◎健康福祉局長(松尾健志君) お答えいたします。
お尋ねの調査における介護事業者の倒産件数は179件で、前年度と比べ48件増加しております。
業種別の倒産件数については、訪問介護86件、通所・短期入所55件、有料老人ホーム17件です。
倒産の原因別で主なものは、売上げ不振や赤字累積、事業上の失敗となっており、介護報酬のマイナス改定や訪問介護員の不足などの影響を挙げております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.46 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
介護事業者、とりわけ訪問介護事業者の倒産件数は過去最大です。倒産以外の休廃業・解散の介護事業者も612件と過去最大であり、そのうち訪問介護事業者448件を占めています。倒産等の原因は、昨年4月の介護報酬の改定により訪問介護の基本報酬が2%から3%引き下げられたことによって多くの事業者が赤字経営となり、ヘルパーの賃上げや人材確保ができない事態に直面していることが原因であることは明らかです。
では、このような事態に対して、当局の介護職員の人材確保について、2点質問します。
1点目、本県、本市における介護職員の不足数の現状をお示しください。
2点目、介護職員の人材確保のための本県及び本市の施策と効果をお示しください。
以上、答弁願います。
P.46 ◎答弁 健康福祉局長(松尾健志君)
◎健康福祉局長(松尾健志君) 本県の介護人材の現状は、令和5年度の介護労働安定センターの介護労働実態調査によると、人材不足と回答している事業所は、県全体で56.4%となっており、本市においても同様の状況と考えております。
人材確保のための施策等について、県においては、介護職の魅力に関する情報発信のほか、介護職員の資格取得やICT導入の支援などに取り組んでおり、人材確保に一定の効果を上げているとのことです。また、本市においては、合同就職説明会や職場体験などを行っており、介護職場の魅力発信や新規就労につながっているものと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.47 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
先ほどの質疑の中で、令和5年度のこの同センターの調査によって、訪問介護員(ヘルパー)の不足が80.6%、介護職員が67%という質疑がございましたが、これは平成30年度と比較しますと、平成30年度は、ヘルパーの不足が69.4%、介護職員が60.8%であります。したがって、この6年間でまさにヘルパーも介護職員も不足する割合が非常に高くなっている現状があるわけです。
ただいま、本県、本市の人材確保の施策について答弁をいただきましたが、その次に、令和6年度鹿児島県介護職員人材確保対策事業について質問します。
この事業の対象法人、事業要件、対象経費、補助上限額、補助予定人数及び補助人数をお示しください。
そして、この事業は既に介護の資格を有する者は対象なのかお示しください。
答弁願います。
P.47 ◎答弁 健康福祉局長(松尾健志君)
◎健康福祉局長(松尾健志君) 県の人材確保対策事業は、指定介護サービス事業所や養護老人ホームなどを運営する法人を対象としており、新規雇用の職員に対して介護職員初任者研修を受講させること等の要件を有しております。対象経費は新規雇用者の人件費や通勤手当などで、補助上限額は1人当たり42万円となっております。また、6年度の補助予定人数20人に対し11人が補助を受けたところです。
同事業においては、採用時、既に介護の資格を有する者は対象外としております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.47 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
新規採用する職員の人件費や資格取得のための研修費用の2分の1を補助する制度ですが、県全体で募集定員20人は少ないと思いますが、11人の補助人数にとどまっていることも課題ではないでしょうか。しかも、この事業は既に介護の資格を有する者は対象外とされています。ある介護事業所の方からは、初任者研修修了者の雇用を前提とする訪問介護事業所を排除する事業であり、ヘルパーの人材確保には生かせないという厳しい批判、声が寄せられています。
そこで質問します。
赤字経営やヘルパーの人材確保の困難に直面している市内の訪問介護事業所への就労を予定する人への初任者研修費用や就業支援を資格の有無にかかわらず市独自に支援することについて、当局の見解をお示しください。
答弁願います。
P.47 ◎答弁 健康福祉局長(松尾健志君)
◎健康福祉局長(松尾健志君) お尋ねの支援内容については、今後、他都市の状況を調査してみたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.47 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
介護職員の人手不足、とりわけ訪問介護事業所の倒産や休廃業を防ぐためにはやはり直接支援が必要です。他都市の状況を調査してみたいと答弁されましたので、新潟県村上市の取組について質問します。
村上市は新潟県北部に位置し、日本海に面するまちで人口約5万2千人ですが、面積は鹿児島市の約2倍であり、山間部は豪雪地帯を抱えるまちです。この村上市では訪問介護事業所に対して支援金を支給する事業が行われており、3点質問します。
1点目、予算規模と事業実施期間をお示しください。
2点目、訪問介護事業所支援金の内容をお示しください。
3点目、訪問介護事業所燃料費支援金の内容をお示しください。
以上、それぞれ答弁願います。
P.47 ◎答弁 健康福祉局長(松尾健志君)
◎健康福祉局長(松尾健志君) 村上市の支援金は、6年度から8年度までを事業の実施期間としており、7年度の予算額は1,400万円となっております。
訪問介護事業所支援金は、報酬改定の影響額として、5年度と6年度との差額等を支給するものです。
訪問介護事業所燃料費支援金は、車両1台につき、ひと月3千円を基本とし、事業所から7キロメートル以上の訪問介護の場合は、1回当たり50円を加算して支給するものです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.48 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
村上市では、昨年4月の介護報酬改定で、訪問介護の基本報酬が削減されたことを問題視して、市長が現場にアンケート調査を指示し、事業者の声を聞き取りました。その後の議会での質疑等を通じて、市長は3年後の介護報酬の改定を待てないと判断し、介護報酬引下げによる減収分を4月に遡及して市独自に補助する事業を昨年の12月議会で成立させました。市議会も訪問介護報酬引上げの再改定を行うことを求める意見書を全会一致で採択するなど、市の取組を後押ししています。
では、村上市の事業開始から1年が経過しましたが、これらの支援金の実績と効果をお示しください。
答弁願います。
P.48 ◎答弁 健康福祉局長(松尾健志君)
◎健康福祉局長(松尾健志君) 村上市によると、訪問介護事業所支援金は、17事業所で618万2千円、燃料費支援金は、16事業所で372万9千円を6年度に支給したとのことであり、事業所の負担軽減や安定的なサービス提供体制の確保が図られたとのことです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.48 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
村上市の実績と効果が示されました。訪問介護サービスの継続を維持することにつながっていると言えるのではないでしょうか。村上市は、事業者だけでなく介護に従事する人への直接支援にも取り組んでいます。
そこで、村上市の介護人材確保推進事業給付金について、2点質問します。
1点目、給付金を受給できる要件と受給額をお示しください。
2点目、令和4年4月からの受給要件の拡大による実績と効果をお示しください。
以上、答弁願います。
P.48 ◎答弁 健康福祉局長(松尾健志君)
◎健康福祉局長(松尾健志君) 介護人材確保推進事業給付金の受給額は、1人当たり3万円から20万円までの4種類となっており、受給要件は、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士のいずれかの資格を有する者で、市外から市内への介護事業所に転職し、3年以上継続して勤務する等の条件を満たす者等となっております。
同給付金については、4年4月に資格取得などに対する受給要件が追加され、3年度と比較して16件の増となり、就業の促進等が図られたとのことです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.48 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
この事業は村上市では平成29年度から行われており、要件拡大による効果も現れているようです。介護従事者への直接支援を本市も検討すべきではないでしょうか。
本市は村上市のこれらの取組をどのように評価しておられますか、見解をお示しください。
答弁願います。
P.48 ◎答弁 健康福祉局長(松尾健志君)
◎健康福祉局長(松尾健志君) 村上市の取組は、地域の実情に応じた介護人材確保の取組の1つであると考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.48 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
大変素っ気ない答弁ですが、どんな地域に住んでいても、在宅介護サービスの提供を求めている市民へのサービスが中断されないように訪問介護事業所を支援する村上市の取組をもっと評価していただきたいと思います。
村上市は、訪問介護事業所を支援するための支援金の財源として介護保険給付費等準備基金を活用しています。
そこで伺いますが、本市の6年度介護給付費準備基金残高の見込みをお示しください。
答弁願います。
P.48 ◎答弁 健康福祉局長(松尾健志君)
◎健康福祉局長(松尾健志君) 6年度末の基金残高見込みは約64億4千万円でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.49 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
6年度末の基金残高が約64億4千万円であることが示されました。6年度介護保険特別会計の決算は今後明らかにされると思いますが、単年度収支は恐らく大幅な黒字決算だと推察されます。なぜ黒字決算なのか、その要因として、介護保険2割負担導入による利用抑制、介護報酬の引下げや人手不足等が影響していると考えられます。基金をため込むのではなく、第9期計画の途中でも介護事業のために基金を活用することが求められているのではないでしょうか。
したがって、介護職員、ホームヘルパーの確保のために従事者や事業者を支援する本市独自の施策を検討すべきときと考えますが、見解をお示しください。
答弁願います。
P.49 ◎答弁 健康福祉局長(松尾健志君)
◎健康福祉局長(松尾健志君) 介護人材確保の支援策については、第10期高齢者保健福祉・介護保険事業計画の策定に向け、7年10月に介護サービス事業者を対象とした調査を行う予定であり、その中で人材確保に向けた好事例などを把握してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.49 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
先ほどの答弁と全く同じですが、10月に調査するのでは遅いと思います。早急に実施し、介護事業所の要望をくみ上げるべきです。人材確保の好事例として村上市の取組を紹介しました。また、基金の活用について村上市は、県を通じて国の見解を確認したところ、国からは、「問題ない」との回答が示されているということは申し上げておきます。村上市に続いて東京都品川区でも経営悪化の訪問介護事業所を支援するために、介護報酬改定前との差額分を補填する支援策を発表しました。本市においても介護従事者と事業者を支援する施策を検討することを強く求めて、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
他自治体において支給漏れが確認されている生活保護費の家族介護料加算について質問します。
質問の1点目、家族介護料加算の内容と過去3年間の実績の推移をお示しください。
答弁願います。
P.49 ◎答弁 健康福祉局長(松尾健志君)
◎健康福祉局長(松尾健志君) 生活保護の家族介護料加算は、身体障害者の障害等級1級もしくは2級などに該当する障害のある方が、その障害により日常生活の全てについて介護を必要とし、その方と同一世帯の方が介護する場合に、月額1万3,150円が支給されるものです。同加算の令和4年度から6年度までの支給実績を3月末時点で順に申し上げますと、11、10、6件です。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.49 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
家族介護料加算とは、障害により日常生活の全てについて介護を必要とするものを、その者と同一世帯に属する者が介護する場合において加算されます。本市では加算件数は減少しているようですが、大阪府堺市では、昨年、住民から家族介護料加算等の支給漏れに関して行政不服審査請求が行われたことなどを契機に大量の支給漏れの実態が明らかになりました。
質問の2点目、堺市が発表した家族介護料加算の支給漏れの内容をお示しください。
答弁願います。
P.49 ◎答弁 健康福祉局長(松尾健志君)
◎健康福祉局長(松尾健志君) お触れの堺市の事例は、令和5年12月に生活保護受給者から家族介護料加算等の支給漏れについての申入れを受け調査したところ、平成19年からの支給漏れが判明し、5年分の遡及支給を行うとともに、当案件以外も順次調査を行い、必要な世帯へ追加支給を行ったものです。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.49 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
堺市が昨年発表した資料によると65名の方々の支給漏れが確認されています。我が党の田村貴昭衆議院議員がこの問題を国会で取上げ、生活保護の研究者らでつくる市民団体「生活保護情報グループ」の全国調査を基に、各自治体の生活保護受給者数に対して家族介護料加算の認定件数にばらつきがあることから、全国的に大きな支給漏れがないか全国調査と原因究明を求めました。厚労大臣からは必要な対応を行うとの答弁が示されました。
そこで、質問の3点目、算定基準について自治体ごとにばらつきがあるとの指摘を受け、国から自治体に示されている通知内容をお示しください。
答弁願います。
P.50 ◎答弁 健康福祉局長(松尾健志君)
◎健康福祉局長(松尾健志君) 国は7年度から改正する生活保護問答集の中で、家族介護料の基準告示にある日常生活の全てについて介護を必要とするものとは具体的にどのような状況なのかや福祉サービスを利用している場合の認定の留意点などについて新たに示しています。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.50 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
ただいまの答弁では、改正内容が具体的に伝わってきません。私から申し上げたいと思います。
国からは、本年3月31日付の事務連絡として、生活保護問答集の一部改正が示されております。堺市での支給漏れの原因を踏まえて、一部改正では、家族介護料加算について3つの見解が新たに示されています。1つ目は、障害により日常生活の全てについて介護を必要とするものとは、食事、排便、入浴の3つの基本動作の全てについて介護を必要とする状況を指すこと。2つ目は、ヘルパーなどの障害福祉サービスを利用している場合でも一律に認定できないものではない、介護の実態を踏まえて適切に認定するとしています。堺市では、ホームヘルプサービスを利用したことで加算をしなかった事例が見られたからであります。3つ目は、加算の対象となる障害者が複数人ある場合は、それぞれ加算を認定して差し支えないということであります。
質問の4点目、今回のこのような新たな国の通知を踏まえて、本市のこれまでの対応と支給漏れがないか総点検を実施すべきと考えますが、見解をお示しください。
答弁願います。
P.50 ◎答弁 健康福祉局長(松尾健志君)
◎健康福祉局長(松尾健志君) 家族介護料加算については、基準告示に基づき、世帯の状況に応じた支給を行っているところであり、国からの通知等も踏まえ適切に対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.50 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
令和6年度の実績では先ほど6件という答弁でした。現時点では支給漏れはないとの認識をお持ちのようですが、障害者加算あるいは重度障害者加算を算定している生活保護受給世帯の中に、今回の通知を踏まえて家族介護料加算の対象となる保護世帯はないのか改めて調査を求めて、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
第9号議案 鹿児島市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例制定の件と乳児等通園支援事業について質問します。
初めに、今回の条例制定に至る関係法令の改正の経緯をお示しください。
次に、乳児等通園支援事業、いわゆるこども誰でも通園制度の目的、内容をお示しください。
次に、本市の一時預かり事業の実績と乳児等通園支援事業との違いをお示しください。
以上、それぞれ答弁願います。
P.50 ◎答弁 こども未来局長(新小田洋子君)
◎こども未来局長(新小田洋子君) お答えいたします。
乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定に係る関係法令の改正の経緯でございますが、令和6年6月に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による児童福祉法の一部改正により、市町村は内閣府令が定める基準を基に、同事業の設備及び運営について条例で基準を定めることとされ、7年1月に内閣府令が公布されたところでございます。
同事業は、在宅で子育てをする世帯の乳児等が保護者の就労要件等を問わず月一定時間までの利用可能枠の中で保育所等に通園することにより、乳児等に家庭とは異なる経験などの機会を与えるとともに、保護者の孤立感、不安感の解消を図るもので、保育所等が市の認可を受けて実施いたします。7年度は、ゼロ歳6か月から満3歳未満で保育所等に通っていない乳児等を対象とし、1人当たり月10時間を上限に利用できるもので、実施施設おいては、1時間当たり300円程度を標準に利用料金を設定するとともに、児童の年齢に応じた1人1時間当たりの単価に基づき本市から補助金の交付を受けることができます。
本市の一時預かり事業の5年度の実施施設数と利用児童数の実績は、一般型は、92施設、延べ5万1,785人、幼稚園型は、55施設、延べ39万6,032人でございます。一時預かり事業の乳児等通園支援事業との違いとしましては、家庭において保育を受けることが困難な場合等に保育所等において一時的に預かる制度であること、利用時間の上限がないこと、ゼロ歳から5歳児で保育所等を利用していない児童や満3歳以上の幼稚園等に在籍する児童が対象であること、年間の延べ利用児童数等に応じた補助金の交付を受けられることなどがございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.51 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
児童福祉法に乳児等通園支援事業が位置づけられたことから条例を制定する必要があると理解いたしますが、乳児等通園支援事業と一時預かり事業との目的や定義面の違いだけでは理解が困難であります。一時預かり事業の実績が示されましたが、全ての施設で実施できるように公的支援の充実を図るべきではないでしょうか。条例では乳児等通園支援事業について2つのタイプが示されています。
まず、余裕活用型施設について、2点質問します。
1点目、同施設の規定と新たな職員の配置の必要の有無をお示しください。
2点目、乳児等が1時間単位で出入りする環境の下で、保育士の増員や専用の部屋の必要性の見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.51 ◎答弁 こども未来局長(新小田洋子君)
◎こども未来局長(新小田洋子君) 乳児等通園支援事業の余裕活用型は、保育所等において利用児童数が利用定員の総数に満たない場合に利用定員の範囲内で同事業を行うものであり、その場合の職員配置は、保育所等の在園児に同事業の乳幼児を加えた児童数に応じた保育士の配置を必要とするもので、同事業での専従の保育士の配置は求められていないところでございます。
また、余裕活用型においては、保育所等での利用定員の範囲内で同年齢の在園児と合同で預かることが基本となりますが、状況に応じて別途保育士を配置し、在園児と分けて預かることも可能でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.51 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
利用児童数が定員内であれば専従の保育士の配置の必要はないとのことですが、状況に応じて別途保育士を配置し、在園児と分けて預かることが可能であるならば条例に明記すべきではないでしょうか。
次に、一般型施設について、6点質問します。
質問の1点目、同施設の規定と専従の保育士等の確保の必要の有無をお示しください。
質問の2点目、保育士の資格を有しない職員の配置も可能かお示しください。
質問の3点目、規定では、職員2人を下回ることはできないとあるが、併設施設と一体で運営を行う場合、職員の配置の規定をお示しください。
質問の4点目、利用児童が乳幼児3人以下の施設で、併設施設の同一保育室等内において、保育士の支援を受ける場合、保育士の資格を有しない職員の配置は可能かお示しください。
質問の5点目、併設施設は規定にあるその他の施設に認可外保育施設も含まれるかお示しください。
質問の6点目、併設施設に基準違反がないことが条例に規定されているのかお示しください。
以上、それぞれ答弁願います。
P.51 ◎答弁 こども未来局長(新小田洋子君)
◎こども未来局長(新小田洋子君) 同事業の一般型は、定員を別に設け、在園児と合同、または専用室を設けて受け入れるもので、単独で実施する場合や保育所等に併設する場合がございますが、併設する場合であっても、併設施設の職員配置基準とは別に同事業の職員配置基準を満たす必要があり、専従の保育士等の配置が求められるものでございます。
一般型に従事する職員につきましては、保育士とすることが望ましいとされておりますが、職員配置基準上、必要な人数の半数以上を保育士とした上で、保育士の資格を有しないが、鹿児島県が実施している子育て支援員研修等を修了した職員の配置が可能でございます。
従事する職員は2人以上が原則となりますが、併設される保育所等と一体で運営を行い、乳幼児の数により同事業に係る職員配置基準が1人で足り、かつ当該施設の保育士等の支援を受けることができる場合においては、保育士等を1人とすることが可能でございます。
利用児童が乳幼児3人以下など職員配置基準が1人の場合、併設施設の同一保育室等において在園児等の保育を行っている保育士の支援を受けることができる場合は、保育士の資格を有しない職員の配置も可能でございます。
一般型乳児等通園支援事業を行う施設として、その他施設には認可外保育施設も含まれるものでございます。
保育所等において、一般型乳児等通園支援事業を併せて実施する場合は、併設施設については、本来、児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等を遵守していることが前提となることから、併設施設の基準の遵守については、今回上程している乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例において規定していないところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.52 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
一般型の施設については、専従の保育士等の配置が必要ですが、保育士の資格を有しない職員の配置も可能とのことであります。これは保育の質に関わる問題であります。また、併設施設に基準違反がないことが前提と言われましたが、条例上規定されないことは問題ではないでしょうか。併設施設の人員配置を減らして、そこで浮いた人員を回す事態が起きないか、こういう点が懸念されるからであります。
次に、乳児等通園支援事業の利用について、3点質問します。
質問の1点目、定期利用、自由利用、柔軟利用とも言いますが、組合せ等による利用方法の内容をお示しください。
質問の2点目、月曜日から土曜日までのゼロ歳児を1こま3人、1日4時間受け入れた場合の補助金額をお示しください。
質問の3点目、利用の際の事前の面談の義務づけや補助の有無、キャンセル時の対応をお示しください。
以上、答弁願います。
P.52 ◎答弁 こども未来局長(新小田洋子君)
◎こども未来局長(新小田洋子君) 乳児等通園支援事業の利用方法は、特定の施設を定期的に利用する定期利用、利用する施設、曜日や時間を固定しない柔軟利用、二、三か所の施設を継続して利用するなど、乳児等の状況等によって利用のパターンを組み合わせる方法がございます。なお、本市では定期利用を基本に制度を検討しているところでございます。
同事業を実施する施設において、月曜日から土曜日まで、ゼロ歳児を1日3人、1人当たり4時間受け入れた場合に基本単価で積算いたしますと、7年度の補助金額はひと月当たり最大42万1,200円でございます。
国の乳児等通園支援事業実施要綱において、初回利用の前に施設は保護者と事前の面談を行い、利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、乳児等の特徴や保護者の意向などを把握することとされており、事前面談も含め同事業に要する経費は乳児等の利用時間に応じて交付される補助金に含まれております。キャンセル時の対応については、自治体または施設においてキャンセルポリシーを定めることとされており、今後、他都市の例を参考に本市において標準例などを策定する予定でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.53 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
本市は定期利用を基本に制度を検討するとのことです。1か月の補助金額が示されましたが、公定価格との関係で必ずしも全額保障されるわけではないようです。この事業の理念を考えれば保護者との面談を重視すべきですが、面談に取り組む事業者への補助がないのは問題です。
既に実施されている一時預かり事業の課題と条例上の問題を指摘してきましたが、一時預かり事業の充実と2026年度に向け、人員配置等の本市独自の基準改正の上乗せを検討すべきと考えますが、答弁願います。
P.53 ◎答弁 こども未来局長(新小田洋子君)
◎こども未来局長(新小田洋子君) 一時預かり事業は、家庭において保育を受けることが困難な場合等に一時的に児童を預かる制度であり、今後も必要とされる方が利用できるよう事業の推進に努めてまいります。なお、乳児等通園支援事業に係る本市独自の人員配置等の基準改正につきましては、現在のところ考えていないところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.53 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
人員配置基準の基準改正は考えていないとのことですが、まず、地域子ども・子育て支援事業としてスタートしますが、事業者や保護者の要望を酌み上げながら保育の質を確保するための基準改正を行うことは可能ですので、再検討を求めて、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
危険な暑さから市民が避難できるクーリングシェルターについて質問します。
初めに、昨年の6月1日から9月30日までの鹿児島市消防局、県全体の熱中症の疑いによる救急搬送状況をお示しください。
答弁願います。
P.53 ◎答弁 消防局長(斎藤栄次君)
◎消防局長(斎藤栄次君) お答えします。
令和6年6月1日から同年9月30日までの熱中症疑いによる救急搬送人員は、本市619人、県全体2,187人でございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.53 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
鹿児島市消防局管轄では、熱中症疑いによる救急搬送件数が県全体の28%を占めていることが分かりました。気象庁から今後の気温の見通しが発表されていますが、全国的に暖かい空気に覆われやすいため、向こう3か月の気温は高いとの予報が示されています。今年も梅雨が明けましたら、救急搬送件数が一気に増加するのではないかと思います。
本市では危険な暑さから市民を守るために昨年からクーリングシェルターが指定されていますが、熱中症特別警戒アラートの発表の有無にかかわらず施設を開放されているようであります。
そこで、同施設の現状について、3点質問します。
質問の1点目、施設を利用した市民からの意見や要望をお示しください。
質問の2点目、本市では97の公共施設と民間施設も12か所指定されていますが、昨年の指定施設の利用状況と指定施設の拡大の必要性についてお示しください。
質問の3点目、指定施設の周知方法についてお示しください。
以上、それぞれ答弁願います。
P.53 ◎答弁 環境局長(濱田孝行君)
◎環境局長(濱田孝行君) お答えいたします。
市民からは、「クーリングシェルターの存在を広く市民に周知することが必要」、「冷房があまり効いていない施設がある」などの御意見がございました。
クーリングシェルターは、市民等が気軽に利用できるように自由に出入りできる場所を指定していることから、指定施設の利用状況の把握は難しいところでございます。熱中症リスクの低減のため、暑さをしのぐ場所をあらかじめ確保することが大切であることから指定施設を増やしていきたいと考えております。
指定施設については、市ホームページやSNSなどで発信するとともに、各施設にクーリングシェルター・マークの表示を行うなど、周知・広報を行っているところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.54 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
不特定多数の方が出入りする施設の利用状況の把握は確かに難しいと理解しますが、本市のホームページでは指定施設の受入れ可能人数として、97の公共施設で合計1,240人、12の民間施設で合計1,574人が利用可能だと発表されています。周知という点では、昨年から始まったクーリングシェルターですので、市民の認知度はまだ低いのではないか。指定施設が可視化されるような工夫が必要だと思います。また、市内の県有施設がクーリングシェルターとして指定されていない点は課題だと思います。
市民の要望という点では、私にも福祉館を利用した方々から要望が寄せられています。福祉館は住民にとって身近な施設であり35の施設が指定されているようですが、福祉館のホールにエアコンがないため大変暑い思いをした、改善してほしいとの要望です。
そこで、福祉館での対応の改善や市内の県有施設等も一体となった周知の検討について見解をお示しください。
答弁願います。
P.54 ◎答弁 環境局長(濱田孝行君)
◎環境局長(濱田孝行君) 地域福祉館においては、熱中症特別警戒アラート発表の際など、館の利用状況を見ながら柔軟な対応を検討してまいります。また、県有施設のクーリングシェルターへの指定については、現在、県に相談しているところでございます。
以上でございます。
[たてやま清隆議員 登壇]
P.54 ◆質問 (たてやま清隆議員)
◆(たてやま清隆議員) 答弁いただきました。
ぜひ、福祉館については柔軟な対応をよろしくお願いいたします。また、市内の県有施設についてはクーリングシェルターの実態が明らかにされておりません。やはり市と県が一体となって市民に周知していくことが必要ではないかと思います。今後もクーリングシェルターの役割が市民に周知され、熱中症予防の効果が一層発揮されることを求めて、私の個人質疑の全てを終わります。