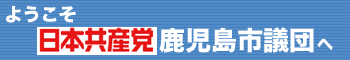P.110 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。
最初の質問は、市長の政治姿勢についてです。
現在、国会で政府提出の年金制度改正法案が自民・公明・立憲民主党の3党による修正を経た上で、先日、参議院で可決・成立しました。修正によって年金削減に歯止めがかかり、基礎年金の底上げがされるとのことですが、実際は、毎年の年金改定率を物価や賃金より低く抑えることで年金を実質減額するマクロ経済スライドはすぐには終わらず、今の高齢者はもちろん、現役世代の将来受け取る年金まで削減が継続されることになります。
そこで、市長に伺います。
成立した年金制度改正法案の内容と、私どもとしては、マクロ経済スライドを廃止し、物価・賃金に応じて引き上がる年金にする必要があると考えますが、見解をお示しください。
以上、答弁願います。
[市長 下鶴隆央君 登壇]
P.110 ◎答弁 市長(下鶴隆央君)
◎市長(下鶴隆央君) 大園たつや議員にお答えいたします。
今回の年金制度の法改正は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、高齢期における生活の安定等を図るため、被用者保険の適用拡大や在職老齢年金制度の見直しなどを行うものです。
また、今後の社会経済情勢の変化を見極め、次期財政検証において基礎年金の給付水準低下が見込まれる場合には、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとしており、国の責任において引き続き、国民が安心し信頼できる持続可能な制度の構築に努めていかれるものと考えております。
[大園たつや議員 登壇]
P.110 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
市長としては、持続可能な制度をつくるという中で検討されるということでした。修正は5年ごとに制度の在り方を検討し、厚生年金の積立金を基礎年金の給付維持に活用することなどマクロ経済スライドの終了を早めるための措置を行うこととしており、実行されれば将来の年金削減の幅は小さくなりますが、その後もマクロ経済スライドは温存され、経済状況が過去30年変わらない場合、2037年の12年間に10%削減されるというのが政府と3党が示す想定です。私ども日本共産党は、マクロ経済スライドを速やかに撤廃し、総額290兆円に上る年金積立金を今すぐ活用して、全世代に物価・賃金に応じて引き上がる年金を保障する立場であることを申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
本市の公共交通の維持・確保についてです。
去る5月下旬、党市議団で、運転士確保非常事態宣言を発出して人材の確保や路線維持に取り組む京都市を訪問し、調査をさせていただきましたので、そのことを踏まえ、特に運転士確保の観点から伺ってまいります。
まず、交通局バス事業の現状について、以下伺います。
質問の1点目、最近の民間委託路線の引き戻しの内容と影響をお示しください。
質問の2点目、7月からの路線・ダイヤ見直しの内容と影響をお示しください。
以上、答弁願います。
P.111 ◎答弁 交通局長(枝元昌一郎君)
◎交通局長(枝元昌一郎君) お答えいたします。
委託路線については、委託先の運転士不足により現在までに20勤務が引き戻しされ、交通局において運転士不足が生じております。
お触れの見直しについては、伊敷、玉里団地方面など7路線において平日22便などの減便を実施するほか、11番鴨池・冷水線など2路線において路線を分割することとしており、運転士7名分の業務量縮減を見込んでおります。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.111 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
交通局としては、平日22便の減便など7名の縮減を図るなど、民間を含めて依然として運転士不足から来る厳しい経営環境ということを確認します。さきの第1回定例会では、2月補正予算で本市としても国の補正予算を活用した運転士確保策や物価高騰対策が提案されたところです。
そこで、質問の3点目、交通局としての運転士確保策の活用状況と効果をお示しください。
質問の4点目、運転士の不足状況をお示しください。
以上、答弁願います。
P.111 ◎答弁 交通局長(枝元昌一郎君)
◎交通局長(枝元昌一郎君) 運転士確保策については、7年度に大型二種免許の取得費用の支援を開始し、現在募集中でございます。
運転士数については、本年6月時点で必要数103人に対し102人で、1名不足しております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.111 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
運転士確保策についてはまだ募集中と効果が見られないものの、現在の運転士の不足状況は1名ということを確認します。
次に、交通局のバス運転士の処遇改善について、冒頭申し上げた京都市では、令和6年6月から日々50名から60名の人員不足が生じ、7月に新規採用の募集をしたところ極めて少ない状況があり、現行の路線・ダイヤを維持することが難しくなると判断し、非常事態宣言を発出しました。宣言の発出については局内でも様々な意見があったようですが、最終的にはこの事態に背水の陣で臨む覚悟で判断されたとのことでした。その後、改めて新規採用者を募集するとともに、離職者を抑制できる手法の検討など、選ばれる交通事業者にするという考えを本市の今後の取組にも生かしてはどうかと考えることから、以下伺います。
質問の1点目、京都市では、令和6年度から、勤務時間を選べ、副業も可能で年齢上限のない週20時間の会計年度任用職員、短時間勤務バス運転士も進めていますが、基本は全て正規職員です。交通局でもその方向で進んでいると考えますが、正規職員化の現状と今後の取組をお示しください。
質問の2点目、京都市は、労働時間等の改善基準告示に定められている勤務間インターバルの遵守や他のバス事業者が導入している週休2日を実現できるよう、そのために必要な人員数も不足数に入れて募集を行っています。交通局として週休2日制の考え方をお示しください。
質問の3点目、京都市は、人事院勧告に沿った給与改定を基本にさらに改善を図るとしていますが、賃金の改善状況と今後の取組をお示しください。
質問の4点目、京都市交通局は、市バス運転士の職に魅力を感じ、これまで以上にやりがいを持って働くことができる職場環境を目指して処遇改善に取り組んでいることが新規採用につながっている手応えを感じているとのことでした。交通局は運転士の確保における処遇改善の必要性をどのように考えておられるのか見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.112 ◎答弁 交通局長(枝元昌一郎君)
◎交通局長(枝元昌一郎君) お触れの採用については、会計年度任用職員からの選考試験を再開し、7年4月に7名採用しており、7年度も選考試験を実施いたします。
週休2日制については処遇改善につながると認識しておりますが、必要人員増の課題がございます。
賃金については人事院勧告に基づく給与改定のほか、局独自の取組も実施しており、今後も経営状況を踏まえ改善を図ってまいります。
運転士を確保するため賃金や労働環境など様々な観点から処遇改善を行う必要があると考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.112 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
市交通局の取組と処遇改善の考え方をお示しいただきました。週休2日制については、京都市交通局でもまだ道半ばとのことでしたが、ぜひ、市交通局でも位置づけて努力されるよう要請します。
質問の5点目、京都市は、先ほど述べた処遇改善の取組に加え、民間交通事業者に配慮して、免許がない方だけを募集し育てることが今後、民間を含めた市全体の運転士確保につながると努力されていました。このような京都市の取組の評価についてお示しください。
以上、答弁願います。
P.112 ◎答弁 交通局長(枝元昌一郎君)
◎交通局長(枝元昌一郎君) 京都市では賃金の改善や免許取得支援制度のほか、公休日数増などに取り組まれ、運転士確保につながっていると伺っております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.112 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
私は運転士確保の肝は処遇改善と思っていますし、当局とも認識は一致すると受け止めておきます。今後の一層の御努力を要請します。とはいえ、京都市交通局は黒字、本市交通局は赤字であり、一定の財源や負担軽減策が必要だと思います。
6月9日の地元紙では、市内在住の70歳以上を対象に運賃を補助する敬老パス、全国各地の自治体が高齢者の外出促進や社会参加を目的に独自の支援を打ち出す中、県内では鹿児島市のみ事業者負担が生じていると報道しました。本市財政も大変厳しいところではありますが、交通事業者の負担軽減として一考する余地があるのではないかと考えることから、次に、敬老パスの事業者負担金について、以下伺います。
質問の1点目、利用状況を過去3年間でお示しください。
質問の2点目、市、事業者、市民の負担額及び事業者ごとの内訳をお示しください。
以上、答弁願います。
P.112 ◎答弁 健康福祉局長(松尾健志君)
◎健康福祉局長(松尾健志君) お答えいたします。
敬老パスの利用状況について、令和3年度から5年度まで順に申し上げますと、400万5,861回、413万5,062回、428万5,483回となっております。
敬老パスのシステム負担金を除く5年度の市負担金は約3億1,958万円となっており、負担割合をおおむね3分の1ずつとしていることから、事業者、利用者の負担も同程度となっております。また、市負担金のうち、事業者ごとの内訳は多い順に、市交通局が1億4,402万円、いわさきコーポレーション株式会社が8,421万円、南国交通株式会社が7,678万円、市船舶局が976万円、JR九州バス株式会社が479万円となっております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.112 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
新型コロナの行動制限前までとはいかないものの一定の利用が回復しており、交通局で約1億4,402万円、他の民間事業者もそれぞれ負担しており、免除できれば大きな負担軽減となります。
質問の3点目、ただ負担軽減をするのではなく処遇改善に努める事業者へ免除を検討してはどうかと考えますが、当局の見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.113 ◎答弁 健康福祉局長(松尾健志君)
◎健康福祉局長(松尾健志君) 敬老パス制度は、高齢者の生きがい支援や外出促進を図る重要な施策の1つとして、利用者、事業者、本市それぞれの負担により制度を維持しているところであり、引き続き事業者の御協力をお願いしたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.113 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
制度を維持していくために事業者にも負担の協力をこれからもお願いしていきたいとの答弁でした。先ほど申し上げたとおり、本市も厳しい財政状況ではありますが、現在、交通事業者が置かれている状況は、新型コロナの行動制限からの回復や物価高騰など自助努力ではどうすることもできない部分もあると考えます。運手士の確保、ひいては本市全体の公共交通を守り維持していくための財政出動として検討されるよう強く要請し、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
市営住宅退去時の原状回復費用について、募集案内等には30万円から40万円かかると記載されているが、50万円、70万円かかると業者等に言われて不安になった市民から相談を受け、令和6年第2回定例会において、政務調査課を通じての独自調査で、人口同規模の中核市と比較して、本市が突出して高いことを指摘いたしましたが、この間の取組などを明らかにするとともに、さらなる負担軽減を求める立場から引き続き伺ってまいります。
まず、原状回復費用について、過去3年間の推移、最高額、最低額、平均を伺います。
質問の1点目、本市負担分をお示しください。
質問の2点目、居住者負担分をお示しください。
質問の3点目、それぞれの主な内容をお示しください。
以上、答弁願います。
P.113 ◎答弁 建設局長(山中浩平君)
◎建設局長(山中浩平君) お答えいたします。
原状回復費用について、本市負担分と退去者負担分の最高額、最低額、平均額を順に申し上げますと、本市負担分は、令和4年度、123万、10万、54万円、5年度、137万、12万、44万円、6年度、104万、11万、45万円。
退去者負担分は、指定管理者によると、4年度、40万、11万、22万円、5年度、44万、10万、24万円、6年度、46万、10万、24万円とのことでございます。
退去者負担の主な内容は、畳の表替えやふすまの貼り替え、居室の壁塗装などであり、これら以外は市の負担でございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.113 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
原状回復費用について、令和6年度は総額で約1億8,700万円、そのうち約6,500万円が入居者負担となっているようですが、平均で約24万円となっています。前回示した独自調査のとおり、回答のあった人口同規模の中核市の平均を見ると、盛岡市は10万円、川越市が4万8千円など、平均が10万円を下回っています。また、昨日の県議会本会議では、本市と同じ指定管理者の県営住宅の平均は約18万円との答弁があり、こちらも高くなっていますが、本市はさらに突出して高いということは改めて指摘いたします。
次に、令和7年度の取組について伺います。
質問の1点目、改善内容をお示しください。
質問の2点目、期待される効果と奏功事例をお示しください。
以上、答弁願います。
P.113 ◎答弁 建設局長(山中浩平君)
◎建設局長(山中浩平君) 改善内容は退去者負担分の居室の壁塗装について、全面塗装から汚れた箇所の部分塗装へ見直しを行っております。
期待される効果は、退去者の負担軽減であり、指定管理者によると、退去者からは、「支払いが想定より安くてよかった」などの声が複数寄せられているところでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.113 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
これまで3か月住んでも30年住んでも壁を全て貼り替えていたものを、傷み具合を勘案して部分補修にする対応が図られました。私ども党市議団にもこの通知を見てからお引っ越しされた入居者の御家族から、「新しい基準になってから聞いていたよりもずっと安くなった。これから引っ越しをされる方にも適用されれば皆助かると思います」との声をいただき、一定の評価をしているところです。
ところで、この公営住宅の高過ぎる原状回復費用について、全国的な問題として、令和7年3月24日の参議院国土交通委員会で質疑が交わされましたので、その内容と当局の受け止めをお示しください。
以上、答弁願います。
P.114 ◎答弁 建設局長(山中浩平君)
◎建設局長(山中浩平君) お触れの委員会では、公営住宅の退去時原状回復費用の負担の在り方などについて質疑がなされており、国は過去の事務連絡に基づき、自治体が適切に判断することが重要との認識を示され、これまでと同様の見解であったものと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.114 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
私ども日本共産党の大門実紀史参議院議員が、家賃が低いことを理由に本来家主が負担すべき修繕費用を入居者負担にして、退去時に高額の原状回復費用を請求するという運用は、憲法の生存権に基づいて住宅に困窮する所得の少ない方々に低廉な家賃で住宅を提供するという公営住宅法の考え方から逸脱するものと厳しく指摘しました。
次に、先ほどの国会での質疑で示された国土交通省事務連絡「公営住宅の原状回復費用の取扱いについて」伺います。
質問の1点目、内容をお示しください。
質問の2点目、経年劣化についての本市の考え方をお示しください。
以上、答弁願います。
P.114 ◎答弁 建設局長(山中浩平君)
◎建設局長(山中浩平君) お触れの事務連絡では、公営住宅は家賃が低廉であることから、民法と異なる特約を設けることは否定されないことや特約とする場合には、入居予定者に十分理解・合意していただくことが重要であることなどが示されております。
経年劣化について、公営住宅では、家賃に修繕費用を含んでいないことから、退去者に一部御負担いただくこととしております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.114 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
前回の質疑では、平成29年の民法改正で通常使用による損耗や経年劣化の修繕費は入居者負担にしないことを原則としたことから、国土交通省も原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを策定しましたが、公営住宅では、先ほど答弁があったとおり、条例や内規で定めるいわゆる特約で運用し、ガイドラインが適用されないとのことでした。答弁いただいた事務連絡については、この特約を容認するものの、民法の規定と異なる特約とするに当たっては、民法に明文化されたことの影響の大きさも十分考慮の上で、引き続き適切な御対応をお願いいたしますと締めくくられていることから、先ほど述べられた本市の考え方が適切な対応と言えるのかが問われています。
そこで、次に、京都市「市営住宅の明渡し検査及び原状回復等の費用の徴収に関する事務取扱要綱」の特徴をお示しください。
以上、答弁願います。
P.114 ◎答弁 建設局長(山中浩平君)
◎建設局長(山中浩平君) 京都市の要綱の特徴は、退去費用について、塗装など項目ごとに入居期間に応じた金額を定めていることなどでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.114 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
京都市では、答弁いただいた要綱とともに、何に幾らかかるのかを示した徴収金額表も公開されています。このパネルは京都市の徴収金額表ですが、例えば上から6列目の畳の表替え、1畳のところを御覧ください。5年未満は5,700円、5年超10年未満は4,300円、10年超15年未満で2,900円、そして15年超でゼロ円と居住年数で4段階に分かれています。注目していただきたいのは、畳やふすまなどの徴収が15年超の部分でゼロ円なっていることで、先ほど申し上げた民法改正に配慮したものとなっています。
次に、こちらのパネルを御覧ください。
これは質疑冒頭で市議団に寄せられた市民の声を紹介しましたが、その方が最近、本市の市営住宅を退去されたときの実際の明細書です。「聞いていたよりもずっと安くなった」とのことでしたが、それでも支払いは31万5,285円となっています。詳細を見ますと、畳の表替えが単価4,710円の17枚で8万70円、ふすま関連の項目がその後続き、小計は16万5,890円となっています。この方は39年間入居されていましたので、京都市であれば小計の部分は支払わなくてよかった可能性があります。このことから、本市の高過ぎる原状回復費用の問題点は、民法に明文化されたことの影響の大きさを十分考慮していない対応にあると厳しく指摘いたします。
これまでの質疑を踏まえて、京都市を参考に徴収金額表を公開するとともに、民法改正の影響の大きさを考慮して経年劣化を居住者負担に転嫁しない検討をすべきと考えますが、当局の見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.115 ◎答弁 建設局長(山中浩平君)
◎建設局長(山中浩平君) 原状回復費用については他都市を調査し、必要に応じて見直しを検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.115 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
高齢の方であれば自分が施設入所して退去したときや亡くなったときに残された親族や連帯保証人に多額の原状回復費用が請求されると考えるととてつもない不安の中で日々過ごすことにもなりかねません。当局も今回の質疑を通して他都市を調査して見直しを検討するとの答弁でしたので、その動向を見守り、私も今後とも取り上げてまいりたいと思います。
一言申し上げておけば、私は、原状回復や業者の仕事を安上がりにしろと言っているわけではなく、市営住宅の管理者としての責任を果たすべきとの考えですので、そのことを踏まえて対応されるよう強く要請し、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
資源物回収活動補助金についてです。
同補助金につきましては、令和6年度予算で実施回数補助が廃止されましたが、資源物回収活動をやめる市民活動団体が多いと耳にすることから、その影響と資源化の現状について、以下伺います。
まず、取組内容と意義をお示しください。
以上、答弁願います。
P.115 ◎答弁 環境局長(濱田孝行君)
◎環境局長(濱田孝行君) お答えいたします。
資源物回収活動補助金は、資源物の回収活動を行う市民団体に対して補助金を交付することにより、ごみの減量化や生活環境の保全を図るとともに、回収活動の促進や地域におけるリサイクル意識の醸成等が期待されるものでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.115 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
本市ホームページでは、活動のメリットとして、「地域の環境や資源のことを考える貴重な機会になり、リサイクル意識が高まります。子どもから大人まで一緒に活動できるので、地域の連携を深めることができます。売上金や補助金を活用して団体活動の活性化が図られます。」を挙げられており、啓発活動の一環であることも確認しておきます。
次に、過去3年間の実績の推移について伺います。
質問の1点目、登録団体数及び活動団体数、延べ活動回数をお示しください。
質問の2点目、令和6年度の実施回数補助の廃止の理由と影響についての見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.115 ◎答弁 環境局長(濱田孝行君)
◎環境局長(濱田孝行君) 登録団体数及び活動団体数、延べ活動回数について、令和4年度から6年度まで順に申し上げますと、423、393、381団体、401、388、373団体、6,301、6,174、6,329回でございます。
実施回数補助の廃止の理由につきましては、補助金総額における回収量補助の割合が減少し、実施回数補助の割合が増加する傾向にあったことや令和5年度の行政評価において、事業開始後に始まった計画収集により一定程度事業目的が達成されていることから、事業のスリム化への検討が必要であるとの方針が示されたことによるものでございます。また、実施回数補助を廃止した6年度においては活動団体数は僅かに減少しておりますが、延べ活動回数には大きな影響は見られなかったものと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.116 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
登録団体数についてはこれまでも減少傾向にあったようですが、答弁にもあったとおり、活動団体数の減少は令和6年度が多いことから回数補助金の廃止が少なからず影響していると考えます。また、廃止の理由については、実施回数補助金が回収補助金を上回る現状も出てきた、行政評価でも指摘をされたとのことですが、冒頭申し上げた啓発活動としての位置づけを考えたとき、今後の団体数の減少を危惧するところです。
質問の3点目、補助金総額及び対象品目別の回収量をお示しください。
質問の4点目、回収量の減少の要因分析をお示しください。
以上、答弁願います。
P.116 ◎答弁 環境局長(濱田孝行君)
◎環境局長(濱田孝行君) 補助金総額及び対象品目別の回収量について、4年度から6年度まで順に申し上げますと、補助金総額は、1,470万2,280、1,347万5,120、1,229万2,110円で、また、回収量としては、古紙類は1,619、1,454、1,316トン、金属類は、58、54、52トン、空き瓶類は、34、25、22トン、廃食用油は、11、10、11トンでございます。
回収量が減少した要因としては、人口減少をはじめ、コロナ禍以降の実施団体数や活動回数の減少のほか、ペーパーレス化や瓶からペットボトルへの移行により古紙や空き瓶の回収量が減少したことなどが考えられるところでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.116 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
対象の品目については1トン以上のものについてお示しいただきました。資源回収活動の大部分を占める古紙類がペーパーレス化などで減少していることが分かりました。
このような資源回収活動をめぐる現状は、本市の環境基本計画にも影響を与えるのではないかと考えることから、次に、環境基本計画との関係について伺います。
質問の1点目、資源化率の目標と進捗及び評価の推移をお示しください。
質問の2点目、資源物回収活動の回収量が資源物回収の総量に占める割合をお示しください。
質問の3点目、資源物回収の課題と今後の見通しをお示しください。
以上、答弁願います。
P.116 ◎答弁 環境局長(濱田孝行君)
◎環境局長(濱田孝行君) 第三次環境基本計画における資源化率につきましては、最終年度である令和13年度の目標値を25.5%と設定しております。また、これまでの実績としては、4年度が16.0%、5年度が15.4%であり、目標値に対する進捗率の評価は両年度ともCとなっております。
資源物回収活動による回収量が資源物の総量に占める割合は、近年5%前後で推移しております。
資源物回収の課題といたしましては、資源化率の向上のため、家庭ごみ等に混入する資源物の分別の徹底やこれまで資源物として取り扱っていない品目についての資源化であり、今後それらの方策について検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.116 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
計画の進捗としては資源化率の取組は目標に届かず、取組に対する評価はCが続いています。資源回収活動の回収量は総量の5%ほどとのことですが、以前は7%台でしたので、取組自体が新たな局面、取組が必要ではないかと考えるところです。
とはいえ、啓発活動としての側面を踏まえて、実施回数補助を元に戻して市民や団体の資源回収を促進すべきと考えますが、見解をお示しください。
以上、答弁願います。
P.117 ◎答弁 環境局長(濱田孝行君)
◎環境局長(濱田孝行君) 資源物回収活動補助金につきましては、6年度に実施回数補助を廃止した一方で、市民団体による回収活動を促進するため回収量の減少幅の大きい古紙回収に対する補助単価を引き上げたところであり、また、6年度においても回収活動回数は例年並みであったことから、実施回数補助の再開については考えていないところでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.117 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
資源回収活動をやめた団体から耳にするのは費用対効果が伴わないという理由です。しかし、現環境基本計画での減量化・資源化の推進の項目では、「市民・事業者・市民活動団体・行政が連携して3Rをさらに推進していくため、広報啓発の充実による実践的な取組を推進するとともに、市民活動団体等が行うリサイクル活動等への支援を行い、ごみの減量化・資源化を進めます」となっていることから、市民活動団体と回収量がこのまま減少し続けることのないよう、新たな取組の検討を要請し、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
消防活動が困難な地域についてです。
近年、消防も火災やその他の災害などへの対応から複雑多様化し、消防警備活動の困難性が高まっているとされています。7月の操法大会に向けて消防団でも訓練が始まっているところですが、日頃の備えが重要なことから、以下伺ってまいります。
まず、準消防警備強化地域について伺います。
質問の1点目、指定基準と指定されている地域数及び主な地域名をお示しください。
質問の2点目、準消防警備強化地域消防警備計画におけるこれまでの取組をお示しください。
以上、答弁願います。
P.117 ◎答弁 消防局長(斎藤栄次君)
◎消防局長(斎藤栄次君) お答えします。
準消防警備強化地域の指定基準は、大型の消防車が進入できる最終地点から100メートル以上あって、隣接する住宅の間隔が30メートル以内の戸数が10戸以上ある地域及びこれらに準ずる地域となっており、現在、郡元2丁目田園地区、長田町長田神社付近など9か所を指定しております。
本警備計画のこれまでの取組状況につきましては、確認できる記録によりますと、昭和58年に37か所、現在では9か所策定しているところでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.117 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
準消防警備強化地域とは、大型の消防車等が入れない地域のことであり、消防局としては現状の確認に取り組み、昭和58年37地域だったものが、現在は9つの地域が指定されているようです。これはまちづくりが進み、消防車等が入れる規格の道路が整備されてきたものと理解します。
次に、消火栓設置要望について伺います。
質問の1点目、令和6年度消火栓設置要望の箇所数と主な地域名をお示しください。
質問の2点目、要望からの経過が最も長い地域と年数をお示しください。
以上、答弁願います。
P.117 ◎答弁 消防局長(斎藤栄次君)
◎消防局長(斎藤栄次君) 令和6年度の消火栓設置要望は18か所で、主に吉野分遣隊が管轄する地域などでございます。
要望から経過が最も長い地域と年数は、吉野町、川上町などで、平成20年度から17年が経過しております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.117 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
消防局が現状を把握し、水道局に消火栓の設置を要望していますが、地域によっては17年以上も要望している地域があるようです。
当局に頂いた資料、そして答弁を伺うと、18か所のうち6か所は吉野分遣隊管轄となっており、最も多くなっていることから解消できないものか考えるところですが、質問の3点目、設置における課題をお示しください。
以上、答弁願います。
P.118 ◎答弁 水道局長(遠藤章君)
◎水道局長(遠藤章君) お答えいたします。
消火栓の設置について、国の消火栓を使用する際の基準では、水道管内が正圧に保たれていることとされており、水道管の増径が必要な場合などは更新と併せた検討が必要であり、期間を要する場合があることや財源を確保することなどが課題でございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.118 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
設置については、聞くところによると、100ミリ管で1分当たり1トンの放水量が確保できる能力が求められますが、周辺地域の人口などや資本を構築するに当たっての財政上の課題があるようです。ただ10年以上も要望している箇所について、特に吉野東地域は、近年次々とミニ団地が造成され、人口も増えてきているなどの変化があると考えますので、現状を把握しながらの判断を要請します。
これまでの質疑を踏まえて、消防活動が困難な地域への対応と今後の考え方をお示しください。
以上、答弁願います。
P.118 ◎答弁 消防局長(斎藤栄次君)
◎消防局長(斎藤栄次君) 当該地域においては、ミニ消防車やホースカーなどを活用した効果的な消防活動を行うこととしており、今後におきましても、地域特性に応じた資機材を有効活用するほか、警備計画に基づく訓練や定期的な実態調査による状況把握を行い、地域の安心安全に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.118 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
消防局としては当該地域の市民への周知や消防団等を含む訓練、資機材の充実などで防災に努める意思をお示しいただきました。
今回の質疑を聞いてお分かりのとおり、消防車が入れるように道路を広げたり、消火栓を設置するのは建設局や水道局の所管ですので、一朝一夕とはいかないまでも、活動困難な地域を少しでも解消できるよう局横断的な連携を深めての一層の御努力を要請いたします。自治体によっては消火活動や災害活動の困難な地域など、町丁目ごとに危険度を調査し、ランクづけして公表している事例もあるようですので、今後とも取り上げていくこと申し上げ、この質問を終わります。
新しい質問に入ります。
吉野地域のまちづくり、県道鹿児島吉田線ののり面崩落を防ぐ対応についてです。
気象庁は九州南部が5月16日に梅雨入りしたとみられると発表しましたが、平年より14日ほど早く、初めて全国で一番早く梅雨入りし、土砂災害警報など予断を許さない状況です。私の地元吉野地域でもこの間の強い雨で側溝から水が噴水のようにあふれ、道路が川のようになり、地域住民から心配の声が上がっています。特に、この間何度ものり面崩落を起こし、長期にわたって車線減少を伴う応急対策をしてきた滝之神周辺ののり面について抜本的な改善を求める立場から、以下伺います。
質問の1点目、県道鹿児島吉田線、滝之神周辺ののり面崩落の経過と対応をお示しください。
質問の2点目、現在実施されている事業の内容と工期をお示しください。
質問の3点目、梅雨時期の安全対策の考え方をお示しください。
以上、答弁願います。
P.118 ◎答弁 建設局長(山中浩平君)
◎建設局長(山中浩平君) お触れの路線については、県によると、「令和5年4月の被災については、のり枠内の植生部分をイノシシが掘り返したことにより落石が発生したもので、当該のり面の全てののり枠内をモルタルで覆う工事を行っているところである。また、6年6月の被災については、豪雨に伴い、道路のり面より上部の民有地の斜面が崩壊したもので、浸食防止のための植生マットを設置するとともに、道路沿いには防護柵を設置したところである。被災箇所周辺のこれまでの調査において、道路のり面については、モルタルの浮きや剥がれなどの軽微な損傷が確認されたことから、現在、補修工事を進めており、工期は11月末までを予定している。定期点検や日常パトロール等を行い、道路の状況把握に努め、変状が生じた場合には必要な対策を講じてまいりたいと考えている」とのことでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.119 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
現在実施されている工事は、11月末までの維持補修の範囲であることが分かりました。県道鹿児島吉田線は、吉野地域の住民にとって重要な生活道路であるとともに、災害時に鹿児島空港や他自治体から物資を受け入れる緊急輸送道路、国道10号線が通行止めになったときの迂回路となっている。本市にとっても重要な道路であると認識していますが、道路側溝からの溢水やのり面崩落など非常に災害に弱い道路となっているのではないでしょうか。
そこで、質問の4点目、のり面崩落を防ぐ抜本的な対策への県の見解と今後の見通しをお示しください。
以上、答弁願います。
P.119 ◎答弁 建設局長(山中浩平君)
◎建設局長(山中浩平君) 県によると、「6年6月の被災を受け、道路のり面のみならず、のり面上部の民有地等についても引き続き必要な調査等を行ってまいりたい」とのことでございます。
以上でございます。
[大園たつや議員 登壇]
P.119 ◆質問 (大園たつや議員)
◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
冒頭の答弁でこの間の経過をお示しいただきましたが、のり面崩落が起こるたびに地域住民からなる住みよい吉野をつくる会が抜本的な改善を求めて県当局に要望書を提出してきました。今年1月、会と県当局がこの間の進捗について懇談する機会が得られ、私も同席させていただきました。当時、県当局は、「令和6年度予算で計上した調査費で引き続き全体的な調査を行い、終了次第、工法等を検討し、改善に取り組みたい」と述べられていました。それなので、先ほどの答弁は若干トーンダウンした印象を持つものですが、県道鹿児島吉田線の重要性を鑑み、早急な抜本的対策の具体化を県に求めてくださいますよう強く要請いたします。
以上で、私の個人質疑の全てを終わります。